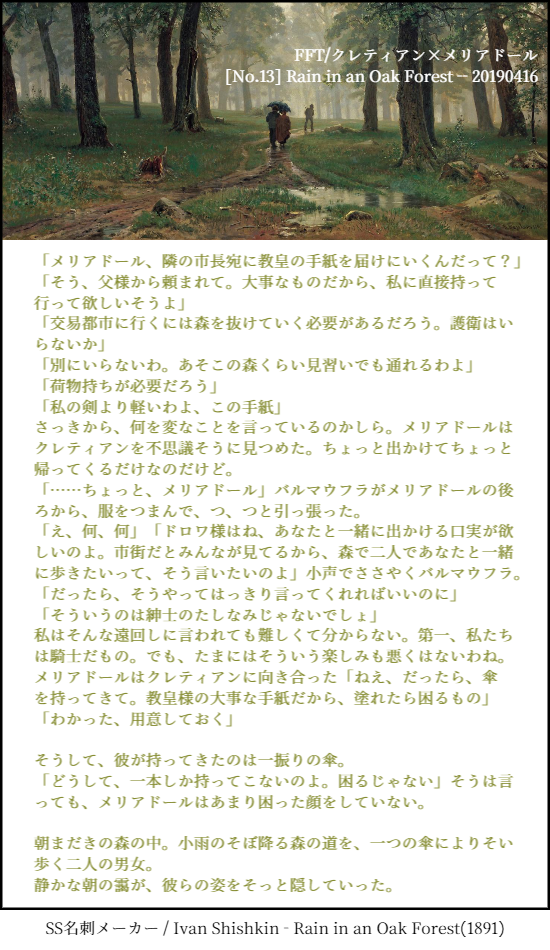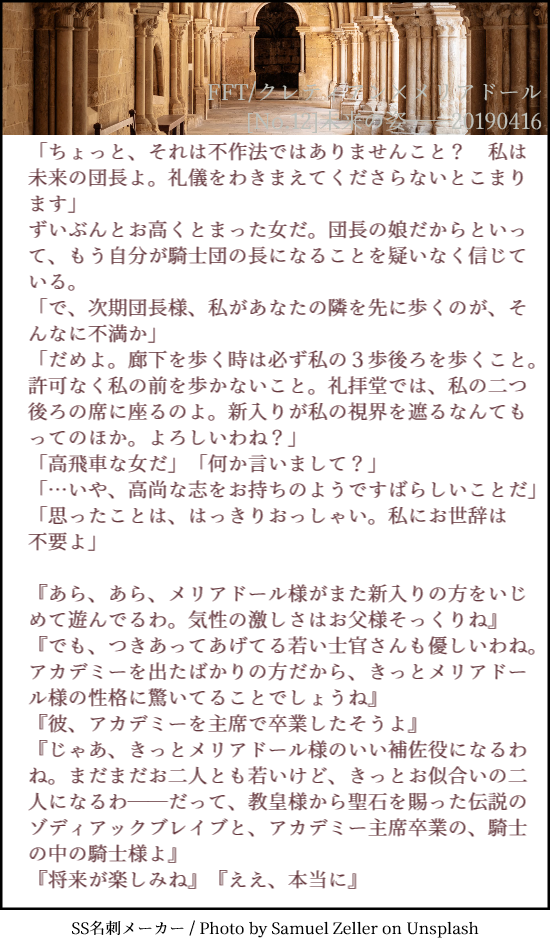.
・エルムドア侯爵の過去話。レディがメインです。
・レディとセリアについて激しい捏造設定を含んでおります
◆登場人物
・メスドラーマ…領主の嫡男。アルビノ(白子)。
・レディ・アデレード…伯爵家のご令嬢。メスドラーマより年上。
・セリシア…アデレードの侍女。アデレードよりさらに年上。アデレードのことをお嬢様と呼ぶ。
・「主」…セリアとレディの主人。メスドラーマの肉体に宿った死の天使ザルエラ。
・レディ・アデレード(レディ)…闇の眷属。暗殺者。セリアのことをお姉さまと呼ぶ。
・セリシア(セリア)…闇の眷属。暗殺者。
「レディの肖像」
*レディの涙
「今日からおまえは私のしもべとして生きるがいい」
そうして私たちは主によって命を与えられた。主は白銀の髪を持つ、年若い人間の男性。主は私たちに人間の形を取るように命じた。
「私は人間の形を知りません。主様はどのような人間をご所望ですか」
もう一人の私が主に訊ねた。主は、私たちをある部屋に案内した。そこにはたくさんの肖像画が飾られていた。男、女、子供、年寄り、犬、馬。皆、美しい衣服を纏い、私たちの方にまっすぐな視線を向けている。
「ああ、そうだな、これがいい」
主が指をさしたのは、二人の女性が描かれた肖像画だった。一人の若い女性がタペストリーで飾られた壁を背にして立っている。その隣にもう一人の女性が寄り添っている。こちらの女性の方が年上のようだ。二人とも同じブロンドの髪だ。もしかしたら二人は姉妹かもしれない。寄り添う二人は親密そうな雰囲気を醸し出している。けれども肖像画はかなり痛んでおり、所々に破損と修復の痕が見える。
「おまえは、この女になるがいい。名前はセリシアだ」
そうして、もう一人の私はセリシアになった。肖像画の中の年上の方の女性だ。私は絵の中のもう一人の女性になった
「私の名前は何でしょうか」
私は訊ねた。
「レディ・アデレードと名乗るがいい。高貴な女性の名前だ」
私は喜び、自分の名前を何度も繰り返した。
私はレディ・アデレード。私は高貴な女性。それが主からいただいたもの。それが私のすべて。
「お姉さま、どうやら私たちは『お嬢様』と呼ばれる人だったらしいの。肖像画の部屋で、お城の人が私たちの絵の前で話しているのを聞いたわ。『お嬢様』は伯爵家のご令嬢だったって」
「レディ、あまり城の中を歩いてはだめよ。私たちは主様にお仕えするためにここへ呼ばれたのよ。主様はもうこの城の中では故人なのだから……」
「お姉さま、お姉さま、でも、主様は、私たちにこの姿と名前を与えてくださったわ。主様は私たちに『お嬢様』になることを望んでいるのではなくて?」
「レディ、くだらない夢想にふけるのはやめなさい。私たちに人間の姿を与えたのは、異形の私たちの素性を隠すための便宜よ」
「で、でも……」
「言い訳はだめ。もう少し分別を持ちなさい、レディ」
私たちは同じ闇の中から生まれた。「セリシア」となったもう一人の私は、「レディ・アデレード」となった私より少し年上の姿だった。そのせいか、もう一人の私は、年長者のように振る舞い、私も、もう一人の私のことをお姉さまと呼ぶようになった。主は私に「高貴な女性」の姿を与え、「高貴な女性」は姉のことを名前で直接呼ばずに「お姉さま」と呼ぶらしいという人間の習慣を知ったからだった。
私は常に主のことを思っていた。主を愛し、主から愛されたかった。どうすればもっと主に愛されるのかを始終考えていた。もう一人の私は、あまり人間の暮らしに深入りするなと、ことあるごとに忠告したが、私は人間の暮らしに興味津々だった。主は私たちに人間の姿と名前を与えたのだから、私は人間になりたかった。主が望んだ存在に私はなりたかった。
だから、時々、「高貴な女性」が着るような服を来て、こっそり城の中を歩いた。城の中では、主は私たちの世界の名前ではなく、「侯爵様」と呼ばれていた。
「メスドラーマ様……」
私はそっと主の人間の名前をつぶやいた。私たちの主のことを人間の名前で呼ぶことは、もう一人の私が許してはくれなかった。だが、私はこの名前の方が好きだった。だって、こっちの方がとてもきれいな響きだったから。なんて美しい名前なのだろう。
私は人目を偲んで、何度も肖像画の部屋に通った。レディ・アデレードとセリシア。二人の高貴な女性を、私は時が忘れるほど見つめた。だが不思議なことに他の肖像画の下には描かれた人の名前が刻まれているのに、この二人だけは名前が削り取られていたのだ。レディ・アデレードとセリシア。主は私たちをそう呼んで名前を与えた。だけど、どうして私たちの名前は絵の中から消されているのだろう。私は疑問に思った。消された名前を私たちに与えた主の真意が知りたかった。でもそんなことは怖くて聞けなかった。
人間の暮らしに紛れるようになってしばらく経つと、闇の生まれである私にも人間の文化が分かるようになってきた。肖像画に描かれた細部の意味も分かるようになった。背景のタペストリーは、人間だった主が治めた土地とは遠く離れた辺境の地の貴族の紋章が描かれている。それはある伯爵家のものだった。伯爵は侯爵と呼ばれる主よりも一つ上の階級だった。主が私を「高貴な女性」と呼んだことに偽りはないようだった。
絵の教養など全くない私が見てもはっきりと分かるくらいに肖像画は痛んでいた。下地の布地ごと切り裂かれ、何度か修繕された痕跡がみえる。この女性は斬られたことがあるのだ。私は不思議と悲しくなった。主も戦場で命を落としたと聞いた。
「あなたも、メスドラーマ様と一緒ね……」
絵画の中の女性に、そっと手をのばす。この貴婦人もきっと亡くなっているのだ。なんとなく、そんな気がする。主が私を見つめる目はいつも悲しそうだったから。
「――私の許可なく、その人に触れるな」
「メスドラーマ様……?」
背後から、突き刺さるような低い声がした。私は驚いて、手を引っ込めた。いつの間にか主が私の後ろに立っている。
「あ、あの、すみません……勝手に触れるつもりは……」
しどろもどろの言葉が口から出てくる。主の気を悪くしてしまったらしい。
「そこから立ち去りなさい」
「待ってください! 私は別にふざけていたつもりはありません! 私は……ただ、この方のことが気になって……」
主は、おそろしいほど冷たい視線を私に向けた。
「おまえが知る必要はない」
「でも、私もこの方と同じレディ・アデレードです。私は少しでも、この方に近づこうと思って……」
私は主に顔を近づけた。
「見てください、このドレス。綺麗でしょう?」
赤いベルベッドのスカートを持ち上げて、私はその場でくるりと身を翻した。肖像画の中のレディが着ているような綺麗なドレス。これで私も少しは絵の中のレディに近づけたかもしれない。私はもっと美しく、綺麗に、艶やで、気品のある女性になる。そして私が本物のレディ・アデレードになるのだ――そうすれば主はもっと喜んでくれるはずだ。
「ふっ……」
主は笑った。私も笑った。よかった、主も喜んでくださる――
「馬鹿だな。おまえは何をやっているのだ。悪魔がドレスを着てどうする」
「え……」
私は、主にそんなことを言われるなど想像していなかった。体がこわばった。そうだ、そうだった、私は悪魔だ……
「おまえは悪魔。私の眷属。おまえの役目は人の命を喰らうこと。だというのに、戯れにドレスを着飾り、人間の真似ごとをして、私を愚弄するつもりか」
「いえ、そんなつもりは……ござい……ません……」
主を怒らせてしまった。私は慌てふためていて、頭を下げた。消え入りそうな声で謝った。膝の前で握りしめた両手がふるえた。そして、崩れ落ちるように床に座り込み、わっと泣き出した。
「申し訳ございません……もうしわけ、ございません……メスドラーマ様のお気を悪くなさるつもりはなかったのです……私は、ただ、メスドラーマ様に喜んでいただきたくて……」
涙がとめどなくあふれてくる。主に喜んでもらいたかっただけなのに、主を気持ちを逆なでして怒らせてしまったなんて。
主は何も言わない。両腕を胸の前で組み、無言で私をにらみつけている。私はとんでもない過ちを犯してしまったようだ――でも、何を?
「……だって、メスドラーマ様が、私に、このお姿とお名前をくださったから……だから私は……この肖像画の中の女性になろうと思って、必死で努力してきたんです……」
涙で視界がぐしゃぐしゃになって、主の姿も絵の女性も見えなくなった。
「私が悪魔なら、どうして私に人間の姿と名前を与えてくださったのです――」
私はあなたによって生み出された存在。あなたのためだけに生きる存在。あなたに嫌われてしまったら、私はどうやって生きていけばよいのだろう。私はひたすら泣きながら、主に謝り続けた。
*消された名前
私は非情な男だと言われてきた。人間だった頃はまるで悪魔のように命を刈り取る、などと噂され、いつしかついた称号が「銀髪鬼」だった。
私は悪魔よりたちが悪い。なぜなら、悪魔を泣かせてしまったのだから。レディが声をあげてないている。たかが悪魔のくせに、どうしてそんなに泣きわめくのだ。あんまり声をあげて泣きじゃくるせいで、身体がまっぷたつに折れてしまいそうだ。悪魔はこんなにも繊細な存在なのか。
床に崩れ落ちたレディと、その前に掲げられたレディの肖像画を見比べた。私の気まぐれな思いつきで、悪魔の眷属は、この肖像画の中の令嬢と同じ姿形をしている。我を忘れたように泣いているレディにつられ、私の視界も混乱してきた。絵画の中のレディも涙を流している。今、私の前で二人のレディが泣いている。
――くそ、記憶がおかしくなってきた。
記憶の中のレディは涙を流したことなどなかった。そうだったはずだが……いや、私の記憶にないどこかで泣いていたはずだ。記憶が逆流してきて、ますます混乱してきた。私もその場に倒れそうだ。
「――どうされました! 何かございましたか!」
乱れた気配を察知して、私の優秀な護衛がやってきた。セリシアだ。彼女は壁に身体を預けてしかめっ面をしている私と、床で号泣しているレディを順番に見た。そして、冷静にこの状況を分析したらしい。
「レディ、落ち着きなさい。何があったかは知らないけれど、主様を困らせてはだめ。一体何をしでかしたのよ」
セリシアはレディの腕を引っ張り上げて立たせようとした。
「もう! しっかりしなさい! 小娘みたいに泣いちゃって――主様、申し訳ございません。この子は使命を忘れて人間の暮らしに馴染みすぎているんです。ここは私が片づけておきますので、主様は、お部屋でお休みください。顔色が悪うございますので」
「顔が悪いのはもとからだ。無愛想だとよく言われるが、別に頭が痛いわけではない。それと、レディを泣かせたのは私だ」
「あら。でもいつものこと、きっとレディが粗相をしたのでしょう」
「いや……」
私は何と答えようか迷った。レディを泣かせたのは、私の発言のせいだ。レディの涙には責任がある。私の眷属のレディと、もう一人のレディに対しても――
「心ここにあらず、という様子ね。主様、しっかりなさってください。あなたは私たちの主人、あなたがいてくださらないと、私たちも使命を果たせません」
セリシアは靴と靴下の間に仕込んでいた短刀を取り出した。
「私の使命は、人の命を刈り取ること……私は、次に葬るべき標的がわかりました。『私たち』です」
セリシアは短刀の切っ先を迷うことなく肖像画に向けた。
「主様、私はレディより少しだけ分別があります。だから私には分かってしまいました。なぜ、主様が私たちにこの女性の姿を模倣するように命令したのか――主様は、この女性たちに対して負い目や迷いを抱えている。それは主様が肖像画と同じ似姿をしている私たちに向ける視線で分かります。私たちを見つめる目は、ザルエラ様のものではなく、あなたの骸のエルムドア侯爵のもの。主様、お目覚めください。あなたはもう侯爵ではありません――『私たち』の存在が主様を迷わせるというのなら、私は容赦しません。今すぐ死んでいただきます」
セリシアは短刀を絵画に向かって振り上げた。暗殺者が狙いを外すことはない。私は彼女の手を制止した。
「おまえの言うことはおおむね当たっている」
「ならば、どうして私のナイフを止めたのです」
「おまえが殺す必要はない。彼女らはもう死んでいる。二度も殺す必要はないだろう」
私はセリシアから短刀を取り上げると、床に投げ捨てた。そして肖像画を眺めた。傷だらけの絵画。記憶がよみがえってきた。かつて、この絵画にナイフを叩きつけた女がいた。奇しくも、その人こそが、この絵画に描かれた女性――セリシアだった。
「セリシア、君は生まれ変わってもやはりこの絵を切り刻もうとするとは」
私はため息をついて首を振った。
「感傷に浸りすぎた。そうだな、おまえの言う通り、私はもう侯爵ではない。混乱して申し訳ない。私は部屋に戻って先に休む。レディの面倒を頼んだ」
セリシアに泣きじゃくるレディを託すと、私は自分の部屋に戻った。ここは私がかつて領主だったころに使っていた部屋だ。セリシアには、人間だった頃の記憶に引きずられるなと叱られたが……この部屋にいて、領主だった頃の記憶を思い出さない方が難しい。
机の引き出しから布に包まれた一枚の板を取り出した。これは、あの肖像画の下につけられていたプレートだった。肖像画の中の二人の女性の名前が刻まれている。遠い昔に、私が自らの手で絵の中から削り取ったものだ。
『アデレードとセリシア。我らの幸福な時を祝福する』
私はため息をついた。レディに泣かれたように、そもそも悪魔の眷属に人間の彼女の名前を与えてしまったことがすべての間違いだった。私はなぜそんな狂ったことをしてしまったのだろうか?
――今更、二人に会いたいなど思うものか……私を憎んだ女たちに……ああ、頭が痛い。今日は早く寝よう。過去のことなど思い出すものか。
*灰色の記憶
過去のことを思い出したくないのは、過去の記憶があまりにも悲惨だったからだ。
私はランベリーの領主である父の嫡男として生まれた。私には未来の領主として何もかもが保証されていた――はずだった。この銀髪さえなければ。
私はイヴァリースでは誰も見たことのない白い髪をもって生まれた。白い髪、白い肌、白い目、いわゆる白子だった。父は生まれてきた跡取りが異形の生まれだったことにショックを隠せずにいた。そして、白い髪を持った私の存在が、父の統治者としての仕事を脅かすのではないかとおそれた。そして、私を城の塔の一室に隠して育てた。おそらくは、私を幽閉し、そのまま存在を闇に葬って次に生まれた子を嫡子として育てるつもりだったのだろう。だが、私にとっても、父にとっても不幸なことに、私の後に生まれた男子は全て死んでしまった。そのうち母も亡くなった。父は私が呪いをかけて弟たちを殺したのではないかと、私の存在をますます恐れた。だから、私は塔の中で幽閉されて育ったが、父は金を惜しむことなく、私にあらゆるものを与えた。私に自由はなかったが、この上なく豊かに育った。私は誰とも会うことを許されなかったが、私の部屋は父が買い集めた美しい調度品であふれかえっていた。父は私が欲しがるものは何でも買い与えてくれた。
私は自分の暮らしが不幸なのか、幸福なのか、自分でも分からなかった。父以外の人間には会った記憶がなかったから、比べようがなかったのだ。だが、やがて15歳になり、成人を迎える頃になると、さすがの私も父への反抗の気持ちが芽生えていた。私は父を困らせようと、無理難題を父にふっかけた。イヴァリースは決して手に入らないような異国の珍品が欲しいと私は父に言った。父が困る姿を見たかった。だが、父は難なくその珍品を私のもとに持ってきた。父には莫大な財産があったのだ。金を積んで、交易人を動かしたのだろう。そこで私は考えた。金で買えないものをねだろうと考えた。
「父上、僕は女が欲しい」
「そうか、おまえも成人した。そろそろ嫁が必要だな。私がとびきり綺麗な娘を見つけてきてやろう。どんな女が好みだ?」
「僕が欲しいのは妻じゃない。ただ一緒に遊びたいだけだ」
「ふっ……女の遊び相手が欲しいとは、大人になったな。いいだろう。畏国で一等美しい高級娼婦をおまえのために用意する。おまえは昔から金のかかる息子だった」
私は女遊びなどしたことはなかった。だから、本当に女と遊びたかったわけではない、ただ、父を困らるために言ったことだ。そして、友達が欲しかった。一人で暮らす生活にそろそろ耐えられなくなってきたのだ。
私は、塔の窓から見渡せる城の中庭を歩く女性を指さした。日傘を差し、侍女を連れて歩く女性。見るからに貴族の令嬢という雰囲気だった。結われていない髪型から、彼女が未婚の若い令嬢であることも分かった。しかも、そばには伯爵家の紋章を背負った騎士の姿が見えた。私はその令嬢が伯爵家の血統を引いていることを確信した。だから、その女性を指さした。父は困るだろうと思ったから。侯爵家よりも位の高い、未婚の女性を、妻にするためではなく、遊び相手として、城の中に連れてくるのはどう考えても不可能だった。
私は勝った、と思った。父が、それだけはできないと言って私に頭を下げるのだ。そして、この幽閉生活から私は解放されるはずだった。
だが、父は手強かった。次の日、塔の中に、伯爵家の令嬢が侍女を連れて私に挨拶をしにきた。
私は父に敗北した。父は、この貴族の令嬢を、こんな塔の中に連れてくるためにいくら金を積んだのだろうか。この女性はいくらで、父である伯爵に売り払われたのだろうか。
私が完全な敗北を感じたのは、次のことに気づいた瞬間だった――私は誰とも話したことがない! この綺麗な女性にどうやって話しかけていいかすら分からない。妻などいらない、女と遊びたい、と父に豪語してみたものの、私は自分の名前すら恥ずかしくて名乗れない始末だった。
気まずい沈黙が流れた。おそらく何も分からず連れてこられたご令嬢は、困惑しているようだった。侍女の方は、こんな状況に巻き込まれたことに苛立っているようだった。
「あの……僕の名前はメスドラーマ。あ、あなたは……」
「私はセリシア。お嬢様はあなたよりずっと高貴なお方なのですよ。直接名前を聞くなどマナー違反にもほどがあります」
「まあ、まあ、セリシア。よいではないですか。私たちはこれから『お友達』になるのよ。堅苦しいことは抜きにしましょう」
部屋の絵画を眺めていたお嬢様がくるりと振り向いた。ブロンドの髪がふわりと宙を舞った。太陽のように美しい人だ。私は阿呆の子のように、口をあけて、その人に見とれた。そして安心した。「友達」にならなれるかもしれないと思ったからだ。
それが、父以外に私が初めて話した人間だ。その後、お嬢様は名前を名乗ったが、セリシアと名乗った侍女に言われたように、直接名前を呼ぶのは気が引けた。だから私は彼女のことをずっとレディと呼んだ。
こうして、私たち三人の奇妙な関係が始まった。
*灰色の記憶②
「この部屋はたくさんの絵がありますわね。若様は絵画がお好き?」
「うん、僕は絵がいちばん好きだ」
レディは約束通りに私の友達になった。毎日、城の塔の私の部屋にセリシアを連れてやったきた。私の部屋には畏国中から取り寄せた工芸品や絵画であふれかえっていたから、会話に困ることはなかった。
「私、絵の教養は全くないけれど、この絵がとても美しいのはよく分かるわ。ねえ、セリシア、あなたもそう思うでしょう」
「はい、お嬢様が美しいと思うものは全て美しいです」
セリシアが言うまでもなく、レディが美しいといったものは全て美しくなった。彼女は穏やかで、おっとりした物腰で、私の部屋にある調度品を一つ一つ褒めていった。それらは父が私を懐柔するために置いていったものたちだ。私はさして興味も持たなかったが、レディが美しいと言葉をかける度に、それらのものはまるで生命をもったかのように色鮮やかに輝いていった。彼女がいると、灰色の世界に色彩が戻るのだ。
「でも、あなたの髪もとてもきれいだわ。私、白銀の髪の方は初めてみましたわ」
レディが私の髪を見ていった。私は怖じ気付いた。この忌まわしい髪が、私から自由を奪った。父は不気味だとしか言わなかった。美しいなどと言われたことはなかった。
「レディ、君は僕の髪が恐ろしくはない?」
「いいえ、ちっとも。とってもきれい。いつかあなたは領主様になるでしょう。そしたらみんな、他の国の方に自慢するわ。このお城には白銀の貴公子様が暮らしているって」
「私もそう思います。だいたい、若様は自信がなさすぎですよ。未来の領主様がそんなに自信がなくてどうするのですか。人の上に立つためにはもっと勉強しないと」
「うん、なら僕はもっと勉強する。本もたくさん読む。財政のことも父から聞いておく。剣の練習だってするよ。レディ、僕が立派な領主になれたら、僕のことをほめてくれる?」
この頃になると、セリシアもよく笑うようになった。私は毎日が楽しかった。二人にずっと側にいて欲しかった。
「セリシア、レディはどんな宝石が好き? 流行の型のドレスは嫌いではない? どんな贈りものをあげたらいいだろう」
私はセリシアからレディの好みを聞き出しては、父の金を使ってありったけの宝飾を贈った。私が贈りものをすると、レディはいつもそれを身につけてくれた。彼女に喜んで欲しい。私に色彩あふれる世界を教えてくれた彼女に感謝の気持ちを伝えたかった。
ある日、いつものように城にやってきたレディは、いつもと違ってずっと窓の外を見ていた。セリシアは静かにたたずむレディの髪をすいて、きちんと編み直していた。
「レディ、どうしたの? 今日はお話はしてくれないの?」
「私は……今日は外の景色を見ていたわ」
レディは窓の外に手をのばした。
「あの山を越えた先に私の国があるわ」
私は普段と違うレディの雰囲気に、急に不安になった。
「レディ、セリシア、どうしたの。どうして今日は二人とも静かなの?」
「若様、お嬢様はしばらく里に戻ります。里のお屋敷で大事な用がありまして」
セリシアのその言葉を聞いて、私はひどく狼狽した。二人が城から去って、そのまま永遠に戻ってこない気がした。私の不安をいち早く察知したのはレディだった。
「大丈夫よ、お屋敷に戻ったら、里の絵師を呼んで私たちの絵を描かせるわ。そしてあなたの元に送ります。そうしたら、寂しくないでしょう?」
私は無邪気に喜んだ。レディの肖像画があれば、私は毎日、彼女に会える。彼女のことをずっと見ていられる。それに、私が絵が好きだと話したことを彼女が覚えてくれていたことが嬉しかった。
「ありがとう、僕は嬉しい。レディ、お礼に何が欲しい? ドレスがいい? それとも宝石の方がいい? この前、大陸から取り寄せた翡翠の首飾りがあるんだ。君がつけたらとても似合うと思う」
「若様、お気持ちだけで結構です。お嬢様はこれから里に帰る準備をしなくてはなりません。私たちの国までは長旅ですから、荷物が増えると大変ですし、宝石をたくさん持っていると盗賊におそわれる危険が増えますから」
「そう……」
そうし私は二人を見送った。
それからの日々は退屈と孤独との戦いだった。今まで、幽閉された生活に孤独を感じたことなどなかったのに、二人が去った後は、一人で暮らす毎日が退屈で、話相手もいない日々は孤独で気が狂いそうだった。自分の生活が、ひどく惨めで、不幸で、さびしいものだと気づいてしまったのだ。
暦を数えるのも諦めかけた頃、ようやく、セリシアが城に戻ってきた。だけど一人だった。黒い服を着ていた。喪服だった。
「レディは? 一緒じゃないの?」
「お嬢様は亡くなりました」
私は言葉を失った。レディが亡くなった? 嘘だ!
「……だって、だって、まだ若かったじゃないか……病気とは思えない。事故でもあったの?」
「若様は、何もお気づきにならないのですか……?」
「え……? 気づくって、何に……」
セリシアの表情がみるみる険しくなっていく。初めて会った時のようだ。
「お嬢様は心を病んで自ら命を絶ちました。若様の言う通り、お嬢様は若かった。まだ結婚もしていない――幼い頃に結婚の約束を交わした婚約者がいたのよ。私たちが城に召された日、お嬢様はたまたま、ランベリーの知り合いに会うために里のお屋敷を離れてこの城に来ていただけ。なのに、突然、お嬢様は若様の相手役に召されて、毎日お城に通う日々。あなた、想像したことがある? 婚約者のいる若い令嬢が、領主のお城の若息子の部屋に毎日毎日通う姿が。お嬢様は外では、あなたの愛人だってずっと陰口を言われていたのよ!」
「そ、そんなこと、僕は知らなかった……!」
「伯爵家のご令嬢が娼婦まがいことをして、男遊びに夢中になっている、お嬢様はそういう野卑な視線に耐え続けていたわ。お城をでる度に、お嬢様はずっと泣いていた。なのに、あなたは何も気づかず、ただ、お嬢様に綺麗な宝石を与えるだけ。あなたは自分の絵画を愛でるように、お嬢様にも綺麗なドレスを着せ、宝石で飾って愛でるだけ。城から出てくる度に、宝飾品を貢がれ、豪華な服を来て出てくるお嬢様を見て、城の使用人は笑ったわ。若様も娼婦と寝るようになった、無事に成人できた、とね」
「知らない……僕はそんなこと知らない! 僕はこの部屋から出ることを父から許されていない。城の噂なんて聞いたことがなかった。レディに宝石を贈ったのは、ただ、彼女に喜んでほしかっただけなんだ!」
誰とも会うことを許された私には、どうやって友達と話せばいいかなんて分からなかった。父は私にたくさんの宝飾品を与えることしかしなかった。だから私もそうするしかできなかったのだ。
「でも、お嬢様は死んだわ。噂が里のお屋敷まで広がり、お嬢様は婚約者に疑われ、どんな言葉を尽くしても疑いを晴らせず、泣きながらナイフで自ら命を捨てたわ――お嬢様は、ランベリーの若息子の娼婦だって言われたのよ!」
セリシアの目には、明らかに憎悪が宿っていた。私はどうしていいか分からず、立ったり、座ったり、部屋の中をうろうろと歩き回った。レディが亡くなったショックで気を失いそうだったのに、彼女が私のせいで辱められていたという事実に、私も死にそうになった。ああ!
「レディ、申し訳ないことをした……本当に……今更謝ってもどうにもならないけれど……僕がレディを城に呼んだばかりに。ああ、僕のせいだ。でも、婚約者がいたなら、最初から断ってくれればよかったのに。そうしたら、こんな悲劇はおきなかったのに。父は一体、君たちにいくら払ったんだ?」
最初から不思議だった。伯爵家の令嬢が、侯爵家の幽閉された異形の息子の相手に召されるなど、ありえない話だ。私の父は一体、どれほどの金額で、伯爵家を動かしたのだろうか。
セリシアはかっと目を見開いて私をにらみつけた。そして啖呵をきるように言い放った。
「お金、お金、お金! あなたはいつもお金のことばかり! お嬢様の潔白のために私は言いますが、お嬢様も伯爵様も、一切お金は受け取っておりません! まるでお嬢様が侯爵様のお金で身売りされたみたいな言い方はよしてください!」
「セ、セリシア、ごめん。そうだったなんて。君たちを傷つけるつもりはなかった。でも、父がお金を出さなかったというなら、どうして、僕のところに来てくれたんだ……?」
その時、レディの死のショックに打ちひしがれていた私の心に、わずかな希望がわき上がった。レディはお金のためにこの城へ通っていた訳ではなかった。つまり、もしかしたら、私のことを愛してくれていたのでは、と幼く純粋だった私は憶測を抱いた。だが、その儚い憶測もセリシアの次の言葉によって、あっけなく砕かれた。
「お嬢様は、若様のことを不憫に思っていたのです。領主の跡取りに生まれながら、異形の生まれだったために外界から閉ざされ、塔の奥に幽閉された若い少年にひどく心を痛め、同情されました。ですから、ここへ通って、少しでも若様のお気を紛らわせようと思っていらっしゃいました――お嬢様のそんな殊勝なお心にも、あなたは全く気づいていないようでしたが」
同情、ああ、そうだったのか。私はずっと不憫な少年として哀れみの視線を向けられていたのだ。私は、そのことに、ひどく落胆した。レディが死んだことより、憐憫の情を向けられていたことに、鈍感にも気づかなかった自分がどうしようもなく情けなかった。
「若様、お約束のものをお持ちいたしました。お嬢様からの贈り物です」
もう相手にもしたくないというとげとげしい雰囲気のセリシアから渡されたのは、布でくるまれた身の丈半分ほどの板――二人の肖像画だった。
『アデレードとセリシア。我らの幸福な時を祝福する』
絵に刻まれた二人の名前と、その後の言葉に私はぞくりとした。背筋が凍るようだった。この言葉はレディが望んで絵師に刻ませたのだろうか。
「さあ、若様、ご満足いただけましたか。これがお嬢様からあなたへの最期のお気持ちです。私はこれで役目を果たしましたから」
「幸福な時か……」
レディの死と、彼女から私に向けられた心の真相を知った今となっては、あの日々を幸福な時と感じることは、もはやできなかった。
「ああ、お嬢様にとっても、おつらい日々でした――お嬢様の涙にあなたは一度でも気づいたことがありましたか?」
「いや……」
私はうつむいた。知らなかった。何も知らなかった。悲しいことに、それが事実だった。
「それでも、それでもお嬢様は、せめてあなたが悲しまないようにと、この絵に『幸福な時を祝福する』と書かせたのです。お嬢様は、ほんとうに、お優しい方だった……だけど、あなたが殺した! お嬢様を死に追いやったのはあなたよ!」
セリシアは服にしのばせていたナイフを取り出すと、目にも留まらない早さで、ナイフを肖像画に叩きつけた。その素早い一撃はレディの胸を切り裂いた。まるで私に、レディが死んだことを見せつけるように。
「私は最初から、お嬢様がお城に通うことには反対だったのよ! あなたのせいで、お嬢様が……ああ、お嬢様が……あの方なしには私は生きていけないわ……!」
セリシアはヒステリックに叫び散らした。私は止めようとしたが、レディに対する激しい罪悪感に苛まれ、彼女にかける言葉も見つからなかった。やがて、パニック状態の極限に達した彼女は、塔の窓から身を乗り出し、私が「あ!」と叫んだ頃には宙に飛んでいた。すぐに、どしんと鈍く重い音が聞こえた。私は窓から地面を見下ろす勇気がなかった。そして、ただぼんやりと、部屋に残された、切り裂かれた二人の肖像画を見ていた。
私にも、レディにも、セリシアにも、誰にとっても苦痛の日々だった。私はセリシアが投げ捨てていったナイフを拾うと、彼女たちの名前を削り取った。もう二度と、彼女たちの名前を口にすることはないだろうと私は思った。
*涙の意味
「主様……先ほどは取り乱して、申し訳ございませんでした……」
私は、主の寝室の扉をそっと叩いて、中に入った。もう一人の私から、取り乱してしまったことを主にきちんと詫びてくるように叱られたからだ。
「主様?」
私は天蓋の下のベッドをそっとのぞき込んだ。シーツの上にきれいな銀髪が流れている。私はじっとみつめた。初めて見たときから、とても美しい髪色だと思っていた。
「誰だ、そこにいるのは」
「あ、あの……お休み中にお邪魔でしたらすみません。すぐに出て行きます」
「レディか、おまえなら別に気にしない」
私は主の好意に甘えて、ベッドのそばのスツールにすとんと腰をおろした。
「主様はとてもきれいな銀の髪をもっていらっしゃるのですね」
「ああ、これか……」
ベッドで寝ていた主は、半身を起こして、自分の髪を無造作にかきあげた。
「若い頃はいろいろ気味悪がられたのだが。悪魔の子だとか、ずいぶん言われた。この国では白子は珍しいからな――そういえば、私の髪を美しいと初めて褒めたのもレディだった」
「私……ではなくてアデレード様ですよね」
主が自ら、あの肖像画のレディ・アデレードについて語るのは初めてのことだった。私は肖像画の令嬢たちについて質問したいことが山のようにあった。だが、もう一人の私に、主の過去に関する人間たちのことには口を突っ込むなと散々叱られたばかりだったので、私は何も言わなかった。
少し休んだ後だったので、主は少し上機嫌になったようだ。主はベッドから出ると、サイドテーブルの上に置かれていた木片を私に手渡した。そこには、二人の女性の名前と「幸福な時を祝福する」という言葉が書かれていた。
「レディ・アデレード……高貴な女性だった。私は一度もその名前で呼んだことはないが」
「……だから私はずっとレディと呼ばれていたのですね……きっと主様の、いえ、メスドラーマ様の幸福な記憶なのでしょう。闇の眷属の私めがこの名前を口にしたら、きっとその幸福な記憶を壊してしまいます」
私は主にその板を返した。主は笑った。
「その必要はない。私が彼女たちを殺したのだから……幸福な日々ではなかった。その間逆だ。その女のうちの一人は私に憎悪の目を向けさえした」
「……っ!」
私は困惑した。肖像画の女性はもう亡くなっているのだろうとは思っていた。だが、主が殺し、主にとって忌まわしい記憶だったとは。
「では……その、ご自身で殺した女性と同じ姿をした私たちをそばに置いておくのは、おつらいのでは……どうして私に、その方の名前と姿を与えたのですか?」
「さあな。私でもよく分からない。もうどうでもよいことだ。彼女らも、私の魂もとうに故人だ。死んだ人間が死んだ人間の魂を喚びだし、昔の記憶と戯れているだけだ」
私は主の言葉を聞くと、静かに部屋を出た。よい夜を、とだけ声をかけた。
「レディ、主様にちゃんと謝れた?」
「お姉さま……」
私は主の部屋から出ると、外で待っていたもう一人の私の胸に飛び込み、こらえきれずに泣き出した。
「あらあら、また泣いているの。あなたは手間のかかる子ねえ」
「そう、私は泣いてる……でも、悲しいのは私じゃなくて、主様なの。主様のかわりに泣いているの……とても胸がしめつけられて、もう私、どうしたらいいのか分からないわ」
私は悪魔。闇の一族。私は人間の魂を喰らい、大いなる主のために血を集めるために生み出された存在。命の奪い方は知っていても、失われた魂のために嘆く人にかける言葉は知らない。
「レディ、泣かないで。私たちは私たちの役目を果たせばいいのよ」
「お姉さま……?」
「私たちは、主様のために魂を尽くして生きるのよ。主の悲しみは私たちの悲しみ。私たちの喜びは主の喜び。あなたが泣いていたら主様はますます悲しむわ。前を向きなさい。私たちは主様の手となり足となり、盾となり、剣となるのよ」
もう一人の私は私に、短剣を握らせた。
「殺しなさい」
「殺す……? 誰を?」
「レディ・アデレードはまだ生きている。殺すのよ」
「レディを殺す? え、だって、レディ・アデレードは主様が、自分の手で殺したって、さっき言ってたわ……それとも私を?」
もう一人の私は、何も言わずに、私の手にある短剣を指さして、うながした。
短剣を持ったまま、私はその場で立ちすくんだ。どうすればいいのだろうか。
*さしのべる手
――何度、この過ちを繰り返えすのだろうか。
私は、寝室の窓をあけ、城の東の尖塔をぼんやりと眺めた。そこが、領主の息子だったかつての私が幽閉されていた場所だ。そこで、レディの死を聞き、セリシアの死を見届けた。私の記憶の中のもっとも灰色の部分だ。
レディとセリシアの死の責任はずっと感じ続けていた。人知れず泣いていたレディの涙に気づけなかった責任は私にある。そのことをずっと責め続けていた。私はもう、メスドラーマ・エルムドアではないというのに。死んだあとでさえ、灰色の記憶がこの身体にこびりついていて、離れない。
なぜ、眷属たちに彼女らの名前を与えてしまったのか。自分でも分からない。彼女たちに側にいて欲しかったのか。今度こそ、自分を愛して欲しかったのか。それとも――罪の償いをしたかったのか……いや、私も、彼女たちも死んでいるというのに、どうやって贖罪をすればよいのか。
灰色の記憶が詰まった塔を眺めながら、私はぼんやりと夜の時間を過ごしていた。すると、部屋の外から、レディのすすり泣きが聞こえる。あまりにも過去の記憶に浸っていたから、レディの亡霊が私の耳元で泣いているのかと思ったが――いや、たしかにレディが泣いている。私の眷属のレディが。
「やれやれ、困った子だ」
悪魔なのに、と口に出しかけて私は硬直した。
レディの涙。私が気づけず無視し続けた涙。私にはその涙をふきはらう必要があったはずだ。今になって気づいた。レディ、私が失った魂。そして私が再び呼び戻した魂が泣いている。私がするべきことはただ一つ――その涙にこの手をさしのべるのだ。
「レディ!」
私は、窓から身を離し、扉をあけるために部屋を走った。
もう過ちは繰り返さない。泣いているレディは、私た殺したレディではない。今更、手を差し出したところで、私の偽善が満たされるだけかもしれない。だが、もう私は彼女の涙を無視するわけにはいかない。そのために彼女の魂を呼んだのだ――
「今、私がいくから――」
そして、扉をあけた私は想定外の光景に驚いた。そこにいるはずだった涙を流すレディはいなかった。かわりに、思い詰めた表情でナイフを握りしめてたたずんでいるレディの姿があった。
「レディ! 何をしている、そのナイフを捨てなさい!」
*新しい世界のために
「主様……」
私はナイフを握ったまま主を見つめた。
「私は闇に生きる暗殺者。お姉さまから、私が次に殺すべき標的を教えてもらいました――レディを殺せと」
握ったナイフで、私は自分のブロンドの髪をざっくりと切り落とした。肖像画の中の彼女は長い髪を垂らしていた。でも私は貴婦人じゃない。私は暗殺者。長い髪で飾る必要はない。それから、おもむろにドレスの裾を破いた。
「主様は私にレディ・アデレードとしての姿と名前を与えました。ですが、私はその名前と姿を捨てます。主様にいただいたものを捨てるわがままを、どうかお許しください」
そして、私は、持っている力の全てを使って姿を替えた。できるだけ貴族の姿から離れた衣装をまとい、闇に生きる暗殺者にふさわしい姿に――
「どうです、私の新しい姿、気に入ってくださいましたか? レディ・アデレードは私が闇に葬りました。これから先、私がドレスをまとうことも、あの高貴な方のお名前を口に出すことも二度とありません。私は名前を捨てました。私のことは、ただ『レディ』とお呼びください。レディ・アデレードを再び殺したのは、この私です。主様が気に病むことはございません」
主はにこやかに笑った。
「眷属に心配されるとは、私も主としての自覚が足りないようだな」
「そうですよ、ザルエラ様。あなたはもう侯爵ではなく、死を司る天使様なのですよ」
もう一人の私が姿を現した。もう一人の私も、ドレスを捨てて私と同じ闇の衣装をまとっている。
「主様、申し訳ございません。私もいただいた姿を捨ててしまいました。私のことは……そうですね、セリアとお呼びください。セリシア様はもう私が消してしまいましたから」
「ああ、そうだな、それがいい」
主は、くるりと向きを変えて、ベッドのそばのサイドテーブルに置かれた小さな木片を手に取った。そこには二人の名前が刻まれている――私たちが捨てた二人の女性の名前が。
「さらばだ、レディ・アデレード、セリシア――そしてメスドラーマよ……」
主は板をまっぷたつに折った。そうして、板の半分を窓の外に手放した。二人の名前は風に乗ってどこかへ流れていく。
「死者の記憶はしかるべき場所に還るがよい。私たちはなすべきことをしよう」
主は、残った板の半分を私に手渡してくれた。そこにはこう刻まれている。
『我らの幸福な時を祝福する』
私は声に出してその言葉を読み上げた。顔を上げると主と目があった。
「主様……」
私は嬉しかった。主が私を見ている。レディ・アデレードに向けられる視線ではない。私に向けられる視線だった。はじめて、主は私を見てくれた。
「私は主様のおそばにずっとおります。片時も離れず、あなたをお護りいたします」
主は私たち抱きしめてくれた。
「レディ、よかったわ。主様が私たちのことを祝福してくださったわ。死の天使様の加護をいただいたのよ」
「ええ、お姉さま。私は主様のために、たくさんの血を集めるわ――私たちの生きる新しい世界を作るために」
私はこれからレディになる。私は私になるのだ――私がレディだ。
2019.3.19