.
「おじちゃんはどうしていつも黒い服をきているの?」
黒い服のおじさんに、おそるおそる近づく小さな少女。ふわっと金髪が肩の上で跳ねる。少女は好奇心旺盛だ、普通の人なら近づかない怖いおじさんにも物怖じせずに近寄っていく。だからおじさんの方が怖じ気付いてしまう。黒い服のおじさんは畏国で一番恐れられた暗殺者だった。夜にとけ込む漆黒のマントで素性を隠し、彼の素顔を見たものは誰一人としていなかった――近づく前に彼に心臓に打ち抜かれてしまうのだ。おじさんは凄腕の狙撃手でもあった。
「嬢ちゃん、興味半分に俺に近づくなよ。火傷するぜ」
「だって……知らない人には近づいたら駄目ってパパが言うの。おじちゃん、騎士団のひとでしょ。パパの騎士団の人なのに、一緒にいたらパパに怒られるなんてわけがわからない」
この嬢ちゃんは、騎士団長の箱入り娘。メリアドール嬢ちゃん。大事に大事に甘やかされて育てられてる。
おじさん――バルクは思った。俺がもし父親だったら、俺みたいな輩には娘を近づかせないぜ。騎士団長も父親だな。
「ね、おじちゃん。パパは騎士団のみんなは家族だって言ってる。私もおじちゃんともっと仲良く――」
バルクは笑った。
「ごっこ遊びは別の兄ちゃんにやってもらいな。俺は向かねぇよ」
バルクはきびすを返してメリアドールに背を向ける。家族ごっこなんて冗談じゃない。ちびちゃんと遊ぶのは向いてない。俺は……
「バルク」
どこから現れたのか、背後から低い声で呼びかけられた。振り向かざるを得ない圧力を感じる。渋々、声の主を振り返る。げ、副団長じゃねえか。こいつは堅物だ。いつも不機嫌だ。説教が長い。融通が利かない。ともかく面倒だ。
「あんだよ」
「なぜ、メリアドール様のご要望を無視するのだ。メリアドール様はヴォルマルフ様のご息女。彼女の命令をすることは、すなわち団長に離反すること。たたき斬るぞ」
バルクはため息を一つついた。こう言われたら相手をするほかはない。バルクは少し居心地が悪くなった。嬢ちゃんのわがままにつきあうのが嫌なわけではない。
だたちょっと、過去を思い出して感傷に浸っているだけだ。
バルクは、胸の中に密かに隠している。銀のリングに手を当てた。昔の記憶はここにある。
――どうしておじちゃんはいつも黒い服を着ているの?
嬢ちゃん、俺はまだ夜の中に生きてるんだよ。
――俺あ、ゴーグに帰るぜ。
――どうしたんだよ、バルク。しけたこと言うなよ。一緒に王の首を狩りに行こうって誓った仲じゃねえかよ。この腐った国を変えられるのは俺しかいないって、おまえは何度も言った。途中で降りるなんて承知しねえぞ。おめえの頭、腐っちまったのか。
――ガキができたんだよ。帰って顔見せてやらねえと。一回くらい抱いておかないと親父の顔も覚えてくれねえだろう。顔みせたらすぐ戻ってくるよ。
――やめとけ、一度でも抱いたら情がうつる。そしたら二度と戻ってこれなくなる。
その言葉に嘘はなかった。ゴーグに帰って、女房に小言を言われ、かわいい赤子に対面するのだ。この日のために、ちょっとした銀細工を彫金してきた。そういや婚約指輪も作ってなかったしな。女房に待たせてごめんよと謝るつもりだった。
けれど、その日は永遠にこなかった。
女房が待つ家はなかった。瓦礫の下だった。夫の帰りを待っていた妻は腹ごと潰れていた。
バルクはそこで自分が何者かを思い出した。
畏国で最も恐れられるテロリスト。それが未来の国家を作るためだと信じて、壊し、奪い、崩してきた。たやすいことだった。破壊するのはあまりにも簡単だった。
――これが俺のしてきたことかよ。すまねぇ。
俺の子だった。抱き上げて名前を呼びたかった。女だったのかも男だったのかも分からず。名前をつける間もなく。世の光を見る間もなく瓦礫の下へ。
――抱いたら、二度と戻ってこれなくなる。
でも抱けなかった。因果だ。破壊者として生きてきた報いを受けたのだ。
なんでだよ。俺はガキらが虐げられない国を作るために、生きてきたんじゃないのかよ。幸福を願うと不幸がやってくる。それが世界なのかよ。世知辛えな。神なんてクソくらえ。
「黒い服のおじちゃん、私も騎士になるの。いつかパパの騎士団ので一番強い騎士になるわ! 私もおじちゃんと一緒の騎士よ! そうしたら……家族になれるよね?」
「嬢ちゃん……」
家族なんて言葉の意味はとうの昔に忘れてしまった。
――探したぞ、ブラックリスト一番手のテロリストよ。
――おい、取り込み中だ。話は後だ。
家族のために即席の墓を作った。妻と、まだ生まれてこなかった子供のために。バルクはいつもと変わらず素顔を隠す黒のマントで身を覆っていた。だが、これは暗殺者の衣じゃない。死を悼む喪服の色だ。
そこへやってきたローブの男。相手も黒色のローブをまとっている。黒。闇にとけ込む影の色。祈りの黒色。バルクにはその黒色の意味が分からない。こいつぁ、誰だ?
――てめえ、誰だよ。俺の首を狩りにきた野郎か? いいぜ、存分に戦ってやるぜ。俺の首は安くないからな。だが、今は駄目だ。俺は祈っているんだ。邪魔するな。5分待て。
――5分と言わず、いくらでも祈るがいい。私も祈ろう。それが私の仕事でもあるから。
バルクは首を傾げた。怪しい男だが敵対心は感じられない。
――申し遅れた。私は神殿騎士のヴォルマルフ・ティンジェル。今日は剣を持っていない。戦う準備はしてない。頼むから、私に銃を向けてくれるなよ。丸腰だからな。
変な野郎だ。騎士団長ともあろう人間が丸腰で、テロリストの隣に座って、墓石を見つめている。何を考えているのやら。
――家族を亡くし、寂しかろう。
――……あたりめえだ。
バルクは妻の墓石を撫でた。生きてるうちにできなかった愛撫。冷たい石を撫でるのがこんなに虚しいとは。あんたは寂しくない。子供と一緒に逝っちまったから。だから俺は寂しい。一人取り残された、我が身の、どうしようもない寂しさ。
――私も細君を亡くしてな……
この風変わりな騎士団長は唐突に語り出した。彼の妻のこと。妻がいかに美しく、きれいで、可愛らしかったか。自分がいかに妻を愛し、愛されていたか。もう亡き人だが……と、永久に終わらぬ愛の言葉にバルクは静かに耳を傾けた。いつもなら他人の惚気話なんてごめんだぜ、そう思うはずだった。でも、今は嫌じゃない。
「私のパパはね、とてもすごい騎士なの。ね、ローファルもそう思うでしょ? 私のいちばん憧れる人なの!」
「はい。お嬢様のおっしゃるとおりで」
嬢ちゃんの口から、パパがいかにすばらしい騎士か、次々に言葉があふれてくる。
ここの親父は愛されてるな。バルクは、嬢ちゃんの父親が妻をこよなく愛する良き夫だったことを知っている。まだこの騎士団に入る前に、長々と聞いたことがある……あの時、あの日、懐かしい。
記憶は過去から現在へ、現在から過去へ、ゆるやかに駆けめぐる。
――騎士団長さんよ、それで、俺に何の用だ。まさか俺のかみさんの墓参りにつきあってくれたわけじゃねえだろう。用件を話しな。くだらない用だったら俺は帰るぜ。
帰るといっても、もう家はなく。かつてのテロリスト仲間のもとへ帰る気もなく。どこへ行くのかさっぱり分からなかった。分からなくていい。俺は夜の生きる人間。行く宛なんて見当もつかない。
騎士団長は麻袋を取り出した。金だ。バルクにはその袋を持たずとも、音、大きさ、それだけで勘定がつけられる。
――俺を買おうって話か。全然足りねぇよ。俺の懸賞金いくらか知ってんのかよ。俺の首はそんなはした金じゃ売れん。
――あいにく、我が騎士団は清貧を誓っていてな……これ以上の金は出せない。だが、いい人材は惜しみなく私の騎士団に迎え入れよう。偉大なテロリストよ、今からおまえは騎士になるのだ。
――忠誠を誓って生きるなんて俺の性分には合わないね。帰れ。それかもっと金を出せ。俺を満足させろ。
――テロリストよ……いや、バルク。おまえはもう一人ではない。騎士団には同胞がいる。アジョラの血を分け合った仲間がいる。もう一人で孤独に戦う必要はない。
バルクは黙っていた。今し方家族を失った男の同情を惹こうと、この騎士は巧みに言葉を操っているのだろう。そこで、はい、喜んで、と答える男はそもそもテロリストにはならない。バルクもそうだ。無言で、険しい表情をする。
――俺は感情では動かない。騎士団に入ることで、それに見合う報酬が得られるのなら、考えてやってもいい。
――報酬? そうだな、私の娘を抱っこする権利を特別におまえにやろう。特別に1回だ。これは私と副団長にしか許されていない特別な権利だ……1回だけだからな!
――はあ?
バルクはあきれ顔で聞き返した。この男は何を言っているのだ。
――この上ない報酬だ。どうだ、好条件だろう。
でも、付いてきてしまった。他に行くところがなかったからだ。
そうしてテロリストは教会の騎士になった。
そして、今――噂のお嬢ちゃんに出会った。騎士団長の溺愛している、かわいいお嬢ちゃん。
「おじちゃん、パパよりずっと背が高いのね。ねえ、お肩をかして?」
人なつっこいお嬢ちゃんは、怖じ気付くこともなくバルクに絡んでくる。俺に抱っこして欲しいというのか? この俺に? 自分の子すら抱けなかったこの俺に?
バルクはおそるおそる、手をさしのべる。
「ちょっと」すかさず副団長が眉間に皺をよせて制止してきた。「団長の許可なくお嬢様を抱かないでください」
いつもは頷くしかない副団長の言葉だが、今日ばかりは、鼻高々に答えられる。
「はん、俺はな、団長の許可をもらってるぜ。嬢ちゃんを抱き上げてもいいってな――ほら、嬢、こいよ」
手をさしのべる。騎士団長からもらった1回だけの特別なチャンス。
メリアドールはバルクの手にぱっと飛びついた。バルクは軽く抱き上げる。嬢、軽いな。女の子はこんなもんか。肩にかつぐのも軽々だ。メリアドールはバルクの頬に顔をすりよせた。「すごいわ、お空が高く見える――おじちゃん、大好き」
ああ、いいな、こういうの。可愛い。すごく可愛い。
「バルク、頼むから、お嬢様を抱いたまま外へいかないように。誘拐犯がお嬢さまをさらったみたいに見える」
副団長のあからさまなため息。だがバルクもメリアドールを抱き上げるまでは同じことを考えていた。俺みたいなアウトローが嬢ちゃんに触れたら、釣り合わない、と。俺には父親なんてなれっこない、と。
「ローファル! おじちゃんは誘拐犯なんかじゃないわ。わるいひとじゃないでしょう?」
「あ、ああ……」バルクは答えに困った。俺は何者だろう。もうテロリストじゃない。騎士になった。でも相変わらず黒い衣を着たまま。影に身を隠す黒。いつまでも明けない喪の色。
――一度抱いたら、二度と戻ってこれなくなる。
ああ、その通りだ。俺はもう二度と戻れない。あの頃には。選んでしまったのだ。この仲間たちと生きることを。時は戻らない。瓦礫の下から妻が生き返ることもない。
「嬢、強くなりな。騎士になるんだろう。だったら自分の身は自分で守れるくらいに」
「うん。おじちゃんのことも守ってあげる」
「はは、それは頼もしいな」
夜明けは近い――長き喪がようやく明けるのだ。
016
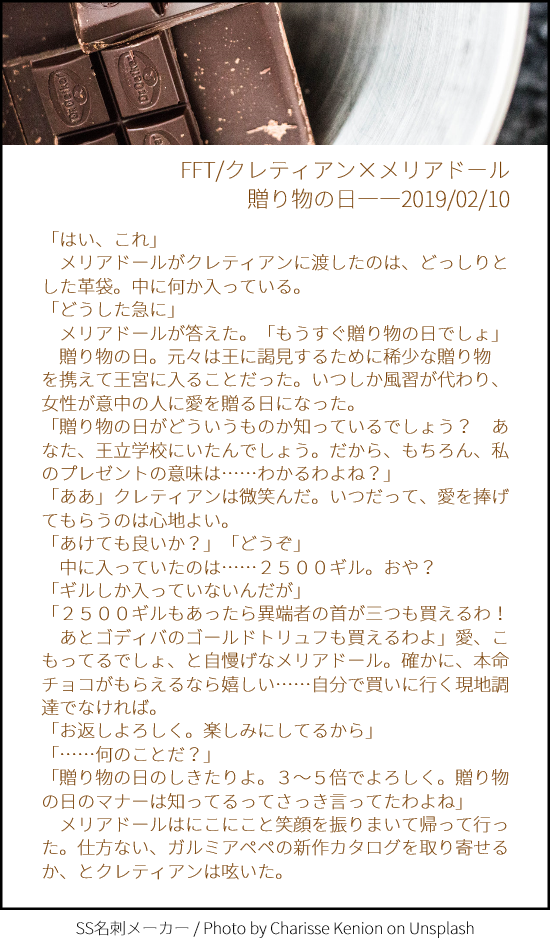
015
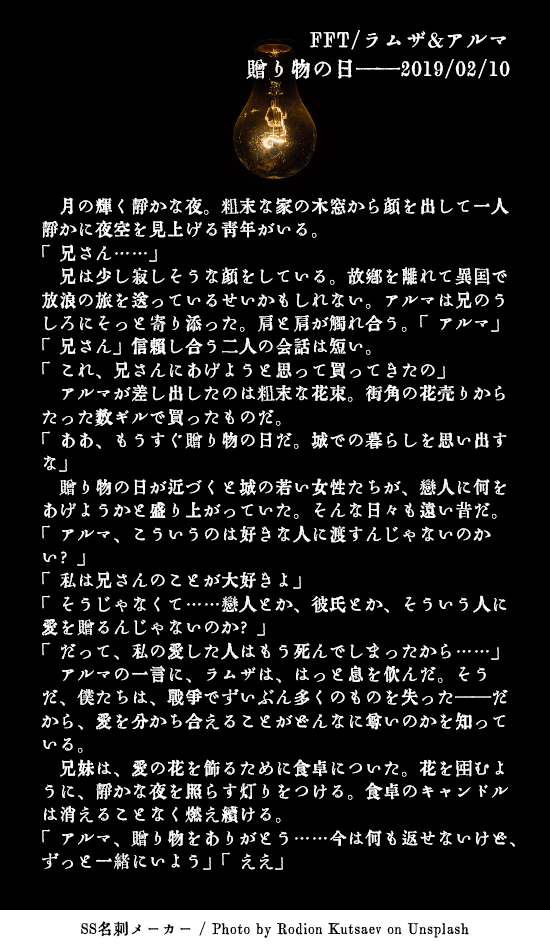
緋色の大地に見る夢は
.
*皇帝を倒す直前のラスウェルとアクスターのif会話です(※9章までのシナリオ設定で書いてます
緋色の大地に見る夢は
「アクスターさん、あなたの正体がわかりました……」
孤高の皇帝が築き上げた、次元の狭間の異空間。グランドールと呼ばれるクリスタルの宮殿でラスウェルは、かつて「師匠」と慕った剣の師に向かって話しかけた。
「その真実は墓場まで持って行くつもりだったのだが、よりによっておまえにばれてしまうとはな、ラスウェル」
「クリスタルの記憶があなたの記憶を見せてくれました。あなたの長い、孤独な旅を――アクスターさん……いや、レイン、話がある」
「話などない。何度も言っただろう。俺の身体はもう限界を超えていると。俺はおまえの師匠として消える。おまえを弟子にできてよかった。さらばだ、ラスウェル」
アクスターはそう言い残して、すっと闇に溶けるように姿を消した。ラスウェルは彼の本当の名前を何度も叫んだ。「レイン! 待ってくれ!」
皇帝を追わなければいけないのは分かっている。だが、どうしてもアクスターを追わなければならない。クリスタルの記憶で、彼の、レインの旅路をラスウェルは知ってしまった。何十年にもわたる仲間のいないたった一人きりの旅。正体を明かせない孤独な旅路。それはどんなに寂しく、苦しいものだっただろうか。
「レイン! おまえを一人でいかせるわけには――」
「待って。そんなに騒々しくしないでよ。レインはやっとの思いであなたたちをここまでつれてきたんだから。もう休ませてあげて」
焦燥にかられるラスウェルを制するように現れたのは、闇の花嫁の格好をした、もう一人のフィーナだった。神出鬼没で、何を考えているのかよく分からない魔性の女だ。
「大丈夫よ、レインには私がついているから――と言いたいところだけど、不満そうね」
「当たり前だ。やっとレインに会えたというのに、何も言わずに別れろというのか」
「こっちの世界には、今のレインがいるでしょう。今生の別れみたいに言わないで」
「ああ、そうだ。俺はレインと共に戦い、皇帝を倒す。だが、俺の師匠として生きてくれたレインは一人だけだ。あいつを一人にはできない。頼む、少しの間だけでもいいから話をさせてくれ」
フィーナはやれやれ、と肩をすくめた。
「まあ、気持ちは分かるわよ。ついていらっしゃい。レインもあなたも時間はないんだから、ほんの少しだけよ」
フィーナがラスウェルの手をつかんだ。身体が白い光で包まれる。ふわりとした感覚。転移魔法だ、とラスウェルは思った。目を閉じて、フィーナの導くままに身体をゆだねる。そして、目を開くと、そこは一面の緋色の世界だった。アルドールタワーを目の前に眺める緋色の高台――
間違いない、ここはアクスターと戦ったあの場所だ。
ラスウェルは迷うことなく、高台の開けた頂を目指して歩いた。アルドールタワーと、その麓――アクスターの仲間が眠っているというあの場所――を一度に見渡すことができる、その場所にレインがいると確信していた。
だが、ラスウェルが見つけたのは、ラスウェルの記憶の中のレインとは全く違っていた。くすんだ赤色の襤褸をまとい、背中を丸めてうずくまり、一人静かにアルドールタワーを見つめている男。ラスウェルやレーゲンよりもずっと年上の男。髪色だけがラスウェルの知っている金髪だった。
レイン、そう呼ぼうとしてラスウェルは一瞬とまどった。あまりにも彼の知っているレインとはかけ離れた風貌だったからだ。レインと呼ぶには老けすぎている。ラスウェルの知っているレインは、自分と幼なじみで、同じ夢を語ったグランシェルトの騎士だったから――
こんなに老け込ませるまで、彼を一人にしてしまった……。彼は自身の長い旅路について一言も語らなかった。最期の時を迎えようとしても、相変わらず、彼の背中は無言だった。
「レイン……」
ラスウェルはやっとのことで、彼の名前を呼んだ。
「ラスウェル、来るなといったのに。こんな姿、おまえには見せたくなかった。俺は皇帝に破れた。敗北の象徴だ。これから皇帝を倒しにいくおまえが見る必要などない」
隻眼、隻腕、隻足の男。失われた彼の半身が皇帝の尽きせぬ魔力の壮絶さを物語っている。
「いや……皇帝に負けたのはおまえのせいじゃない。俺のせいだった」
ラスウェルは覚えていた。かつて、彼の師アクスターが「己の慢心のせいで仲間と半身を失った」と語ったことを。だが、クリスタルの記憶によれば、皇帝に破れた責は自分にあるのだ……
「俺が優柔不断な戦いをしたせいで、おまえを何十年も孤独にさせた。俺があの時、うかつにも死んでしまったせいで……」
長かったよ、とだけレインは答えた。まなざしは揺らぐことなくアルドールタワーに向けられている――いや、もしかしたら、麓に眠っている仲間のもとに向けられているのかもしれない。
「俺にとって、アルドールタワーは忘れられない場所だ」レインは語った。「ザッハでどうしようもない挫折を味わい、無念の中でオーダーズになって皇帝に仕えた。ただ皇帝を倒すために選んだ道だと自分に毎日言い聞かせる苦しい日々だった――それでも、皇帝には勝てなかった。身体も、仲間も、全てを失い、どうして自分だけが無様に生き残ったのかと絶望の中をさまよった」
「レイン……皇帝に負けたのは俺のせいだと言っただろう……」
「ああ、そうだった。だから俺はおまえに非情さを教えるために過去に遡り、アクスターとして、ゼノとして再び皇帝に従う道を選んだ。しかも、隣には若かりし頃の自分がヒョウとして生きている。過去の人生を再びやり直しているようで複雑な気持ちだった。非情になどなりたくはないのに、非情になろうとした過去の自分に向き合い、そして、おまえに非情になれと言い続けた――」
「レイン! やめてくれ、俺はこれ以上おまえが苦しんでいる姿を見たくない……!」
「――ラスウェル、でも、おまえは教えてくれた。情の力は何よりも強いと、この場所で戦って証明してくれた。あの時、俺がどんなに嬉しかったか分かるか? 非情にならなくてもいいと、おまえが教えてくれたんだ――俺の人生を救ってくれた。ラスウェル……ありがとう、感謝している」
振り向かない背中が、何かを物語っている。ラスウェルの胸にあついものがこみ上げてきた。
「レイン、俺は……おまえに別れを言うためにフィーナにここにつれてきてもらったんじゃない。おまえを叱りにきたんだ」
「へえ?」
アルドールタワーを見つめたままのレインが振り向かずに声だけで笑った。それは師匠の声だった。けれどラスウェルは物怖じしなかった。目の前にいるのはもう師匠じゃない、レインだ。俺の相棒であり、仲間であり、友であるレインだ。
「まったく、おまえという奴は……俺より何十年も生きているというのに。剣の腕は上達しても、それ以外は何も変わってないな。レイン、おまえが一人でラピスのゲートを閉じにいった時に俺たちがどんなに心配したか分かるか? おまえが闘星としてオーダーズにいると知った時も、俺たちは心配で夜も眠れなかった。なのに――おまえはいつも一人でそうやって勝手に答えを出して、一人で生き急ごうとしている。情の力を信じられるようになったというなら、もう少し俺たちを頼れ、頼って、本音を話してくれ」
「ふっ……そう言われればな。パラデイアに来てからはずっと一人だったからな」
「だけど、もう一人じゃないだろ。レイン、顔を見せろ。俺はアクスターさんじゃなくて、おまえに会いたいんだ。俺はおまえが敗北の象徴だなんて一度も思ったことはない。俺がパラデイアにきたのはアルドールもヘスも関係ない。皇帝なんて知らなかった。ただ、おまえを探すためにこの星へ来たんだ。今も未来も関係ない。おまえに会いたかったからここまで来た」
ラスウェルの言葉に、レインがわずかに反応した。半分の肩をこわばらせ、それでも頑なに振り返ろうとしない。視線はアルドールタワーにある。
「俺を探しに……?」
「そうだ。おまえはかけがえのない仲間だ……レイン、ずっと一人にしてすまなかった……俺たちの仲間だというのに……」
ラスウェルは、レインの後ろから抱きついた。今すぐに、彼の身体に触れ、自分がここにいる証明をしなければいけないと感じたからだ。
「レイン、おまえとこの緋色の高原で戦った時、アルドールタワーが墓標だと言ったな。おまえの時代の俺たちは死んだかもしれない。だけど、俺は生きてる。絶対に死なない。皇帝を倒して再びこの星に帰ってくる。アルドールタワーは墓標じゃない。新しい時代を切り拓く希望の光にしてみせる……絶対に……だから俺たちの戦いを信じて、ここで待っていてくれ」
「ラスウェル……ああ、そうだな。俺はもうおまえの師匠じゃないし、アルドールの王になるのももう一人の俺だけど………おまえの仲間として、友として、検討を祈る――グランシェルトの騎士として」
友の口癖。久しぶりに聞いた気がする。相変わらずレインは顔を見せなかった。それでもラスウェルには伝わった。レインが、再び自分を信頼してくれていると。
触れた身体からぬくもりが伝わる。生きている。今もこれからも。アルドールタワーを墓標になんかさせるか――レイン、俺はおまえの思いに答えて見せる――
「アクスターとの挨拶はすんだのか?」
レイン――今の時代のレインに言われて、ラスウェルははっと我に返った。いつの間にか緋色の高台からグランドールに戻ってきている。そうだった、もう一人のフィーナは気まぐれな性格だった。何も言わずにラスウェルを元の場所に連れてきたのだ。
「ああ、師匠とはちゃんと話してきた。もう大丈夫だ」
「アクスターか……すごい奴だよな。ここに来る前にアルドールタワーで俺に魔法障壁を教えてくれたけど……あいつは何者なんだ? ラスウェルはずっとあいつと旅してきたんだろう?」
「ああ、師匠はすごい人だよ。俺は師匠のことを尊敬している。これからもずっと。師匠は……皇帝との戦いで仲間を失ったんだ。だから、俺たちのこともすごく心配してくれてるんだ。魔法障壁を教えてくれたのも、きっと師匠の思うところがあったんだろう」
「アクスターはラスウェルの師匠だったんだろ? だったら、ラスウェルにそのまま魔法障壁を教えればよかったんじゃないか。どうして俺に教えてくれたんだろう」
ああレイン、おまえは自分の手で仲間を守りたかったんだな。相変わらず、お前ってやつは、正義感が強くて、自分を犠牲にしてまで、誰かを守ろうとする。変わらないな。
「さあな。師匠は過去のことをあまり語らなかったし……」
「ラスウェル、いこうぜ、今度こそ皇帝を倒そう。俺は……今度こそ、アルドールタワーに希望の光を灯すんだ。俺たちの手で」
「ああ」
ラスウェルはうなずいた。レインはいつだって頼もしい。俺の信頼出来る相棒、頼れる仲間だ。
レインが親指を空に向かってぐっと立てた。幼なじみの口癖だ。
「グランシェルトの騎士として」
「違うだろう、レイン。俺たちはもう騎士じゃない。王だ」
「おっと。そうだった――アルドールの王として」
ラスウェルは友の言葉に返した。「ヘスの王として――血は違えど、目指す場所は同じだ」
迷い無く前に向かって進むレインの隣にラスウェルは並んだ。
「レイン、この戦いが終わったら、アクスターさんの仲間に会ってくれないか? アルドールタワーの麓に眠っているんだ。レインが来てくれたら師匠は喜ぶと思う――だから、皇帝を倒して、絶対に生きて帰ろう。背中は託した。頼むぜ、相棒」
「ああ、任しておけ」
二人の王が新しい時代に向かって歩いていった――自分たちの時代を切り拓くために。