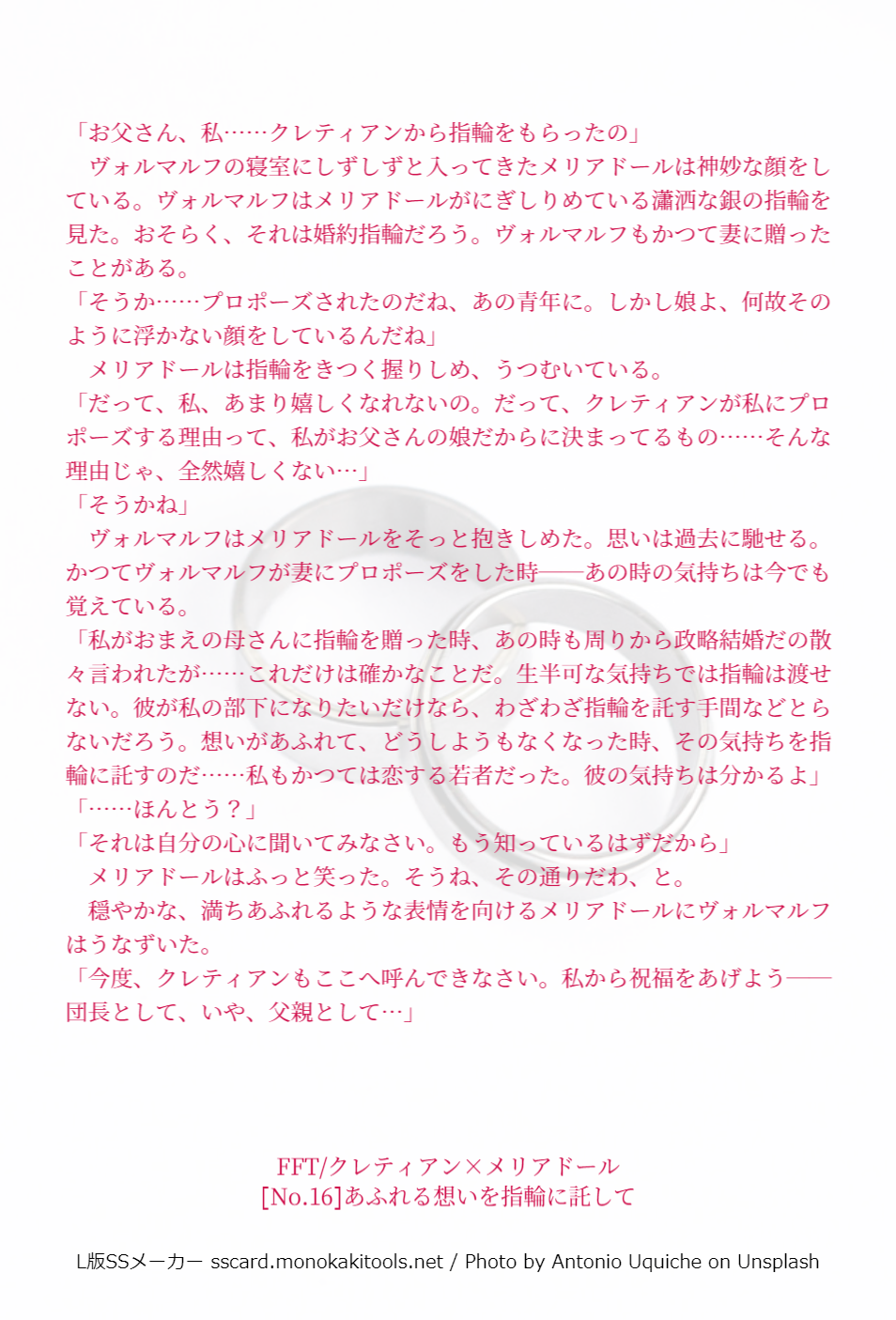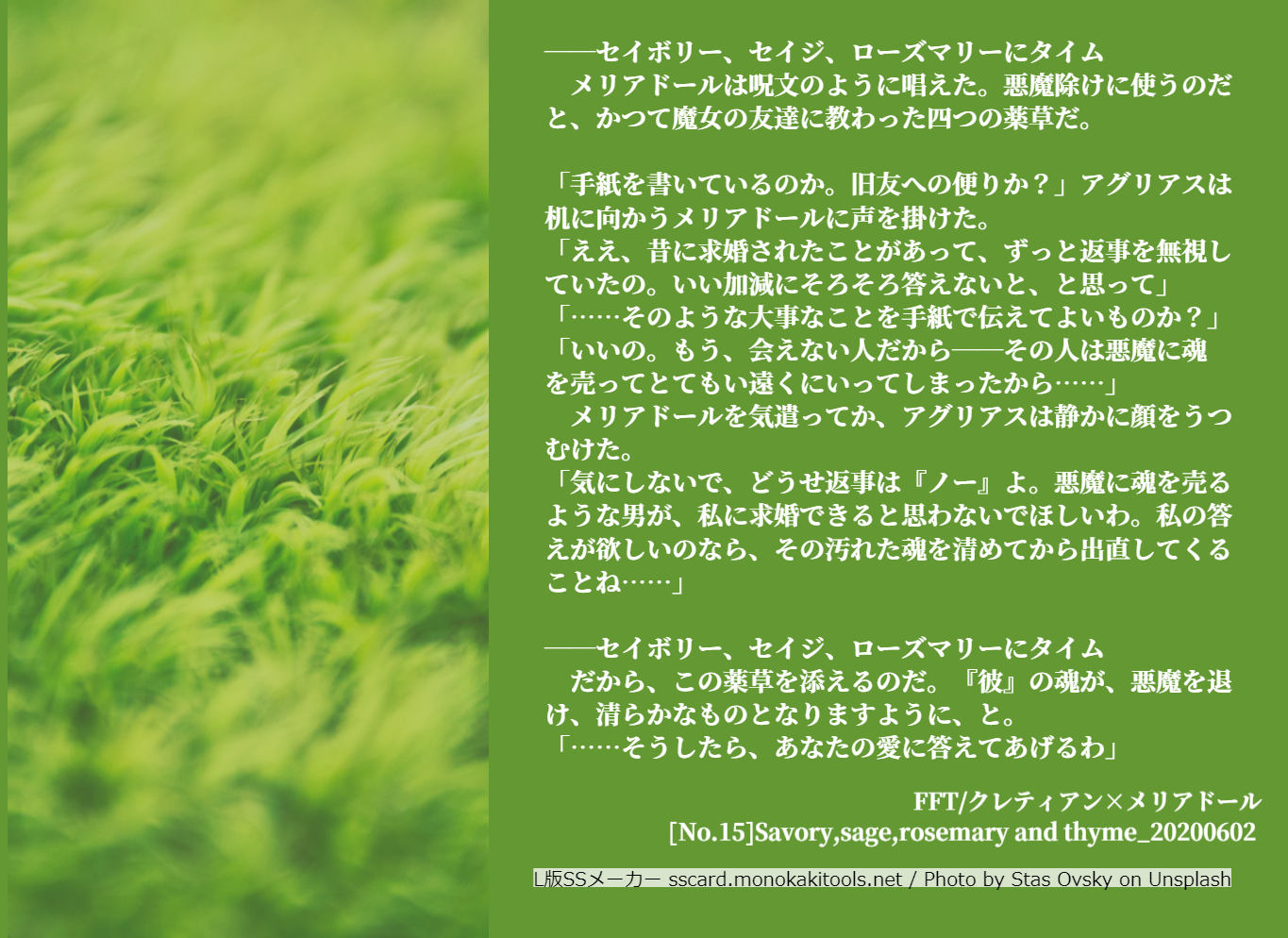.
・オーランが生きています。バルマウフラと結婚しています。バルマウフラは森の魔女です。
・「ヴァイゼフラウ・バルマウフラ」の続編のようなお話です。バルマウフラが「ヴァイゼフラウ(賢い女)」と呼ばれているのはそこからのオリジナル設定です。
妻の名前を呼ぶ日
長い夢を見ていた気がする。熱い、炎に、焼かれるような、息苦しい夢。目を閉じたら二度と起きることができないような深い夢。
「旦那、お目覚めかい」
オーランはふっと目を開けると、声の聞こえる方に顔をわずかに向けた。身体が思うように動かない。見知らぬ場所の見知らぬベッドの上に寝かされていて、ありったけの包帯と保護布で身体を覆われている。
「全身ひどい火傷だよ。焼けた家の下敷きにでもされたのかい?」
火傷。その言葉にでオーランのぼんやりとした意識は完全に覚醒した。
――そうだ、私は火刑に処されて死ぬはずだった。
杭に縛られ、足下に積み上げられてた薪に火がつけられ、有象無象の観衆から投げつけられる言葉を聞いているうちに息苦しくなってくる。白書を上梓し、後は森羅万象に身を委ねるつもりだった。しかし、いざ杭につけられ、我が身に迫る炎を見ると恐怖がせり上がってくる。この場においてみっともなくもがき苦しむよりは、と、オーランはそこで意識を手放した。いや、その前に「彼女」の姿を見た気がする。それが死ぬ前の幻覚が見せる夢だったのかどうか、彼には分からなかった。
そして、再び意識を取り戻し、見知らぬ場所に寝かされている。やや心配そうな顔で寝ているオーランをのぞき込む男の名前も、当然知らない。
「しかし旦那、いったいどうしてこんなひどい怪我を? 家に放火でもされたんですかい?」
「ああ、火をつけられてしまってね……うっかりしていたよ」
異端として火刑宣告されて我が身に火を放たれて、とは言えなかった。貴族ならばオーランの素性を知っており、処刑を生き延びたことを密告するかもしれない。この男がどこまで貴族と関係があるのか分からなかったが、オーランは念のため事情を伏せておいた
「あなたが私の治療を?」
オーランはベッドの上で、そっと自分の身体を触った。かなり炎に炙られていたと思われる下半身は殆ど感覚がない。だが、わずかに手を下腹部にずらあしていくと軟膏と包帯とで手厚保護されているのが分かる。腕のよい治療師が手当てをしてくれたのだろう。
「いや、俺じゃない。ヴァイゼが旦那をここへ連れてきた。大方の治療はヴァイゼがやった。俺は彼女に指示された世話をしてるだけさ」
「ヴァイゼ……?」
「ヴァイゼフラウ――魔女だよ。村のはずれのラナの森にひとりで住んでる」
村の男は木枠で覆われた窓をこんこんと叩いた。おそらく、叩かれたその方角に魔女の住まう森があるのだろう。
オーランは、ヴァイゼフラウと呼ばれる魔女の正体を知っていた。どうやら死ぬ前に「彼女」を見たのは夢ではなかったようだ。そして、「彼女」が彼を助け出してくれたようだ。
「『彼女』は今どこに?」
はやく会いたいな、とオーランは思った。
「ヴァイゼなら森へ帰ったさ。彼女はきっちり三日おきに村へやってくる。次にここ来るのは夜が三度来てからだ。それが魔女の流儀なのさ――ところで、旦那はいったい何者ですかい? あんたはヴァイゼが突然この村に連れてきた。怪我を追っているから看病をしてやってくれと。彼女といったいどういう関係だ?」
「私は彼女の夫です。彼女は私の妻です」
「旦那? ちいと煙を吸いすぎたのでは? 頭はしっかりしていますかい?」
村の男はオーランの言葉を笑って流した。オーランがまだ昏睡状態で夢まぼろしの言葉をしゃべっていると思っているらしい。
「いや、これは本当です。領地には正式な結婚証明書があります。私たちの間には息子だっています。証明書はここにはないけれど、結婚の誓いをあげた時に作った指輪が――あれ、ないな……」
オーランは自分の左手を見てがっかりした。処刑台にあがる前に、これだけはと司祭に懇願して最後まで身につけいていた結婚の指輪が見あたらない。
「旦那、無理は禁物ですさ。しっかり寝て起きれば、頭もしっかりしてきます」
「ああ、ありがとう……」
――せめて、あの指輪が見つかれば僕が「彼女」の夫だとこの人に伝えられるのに。
オーランはがっかりした。肩を落として、そのまま目を閉じた。この場所にいればいずれ「彼女」に会える。その安心感が彼を安らかな眠りへと誘った。
さっぱりした薬草の香りに目が覚めた。
「バルマウフラ……もう来てくれたのかい。村の人の話だと三日おきにしか顔を出さないとか」
「そうよ、私は三つの夜を数えてから森を出た。あなたがずっと眠っていただけよ」
バルマウフラはベッドの上に横たわるオーランにそっと覆い被さり、頬を、髪を、両手ではさんで優しく撫でた。
「ゆっくり休んで身体を回復させるのよ」
そう言いながら、バルマウフラはオーランの身体をベッドの上で転がしながら手際よく包帯の交換を行っていく。サイドテーブルにはオーランにも名前が分からない薬草の束がどっさりと積まれている。
「君は……ここではヴァイゼフラウと呼ばれているようだね」
「それは母の名前だ……森に住む賢い女は皆、ヴァイゼフラウと呼ばれる。母亡き後、私がヴァイゼフラウになったの。私の母は教会の騎士に異端の嫌疑をかけられ、その場で火炙りになって死んだ――だから、炎は、私は、きらい」
仰向けに寝かされているオーランからは、テーブルの薬草を包帯に練り込んでいるバルマウフラの表情は見えない。オーランは無性にバルマウフラのことを抱きたくなった。今はただ静かに抱いて、謝りたい。
――君が炎を恐れているのはずっと昔から知っていた……そして僕はまた君を怖がらせてしまった………
「あなたが炎に包まれた時……私は……」
バルマウフラが涙を飲む音が聞こえた気がした。
彼女を泣かせてしまった。どうしよう。抱きしめたいのに。今すぐ彼女の肩に手を添えて、大丈夫だよ、と言ってあげたいのに。動かない身体がもどかしい。
「バルマウフラ、心配をかけてすまな――い、痛ッ」
バルマウフラが、オーランの右足の包帯を締め上げた。
「――冗談じゃないわよ。次に炎の中に入るときがあったら、もう知らない。勝手に焼かれなさいよ」
手際よく、古い包帯をはがし、焼けた皮膚を削り落として薬草と軟膏を塗り込んで新しい包帯で締め上げていく。その手つきが少々荒いのは、妻に心配をかけた夫への罰だろうか。それならば甘んじて受け入れるしかない。オーランはベッドの上に四肢を投げだし、彼女のされるがままになっていた。
「――そういえば、ここの村の人は、君が独り身だと信じているようだ。僕が君の夫なんだと言っても鼻で笑われたよ。頭でも打って錯乱しているだけだとね」
バルマウフラは笑った。そしてベッドの側のスツールに腰をおろした。仰臥しているオーランと会話がしやすいように視線を落としてくれたのだ。
「そうね、都市には都市の法がある。そして森には森のしきたりがある。ここの村では教会で結婚をするというしきたりはないの。村の祭りで互いの名を呼び、村の人たちから認められればそれで夫婦になるの。だから、都市で作った結婚証明書を見せても、村の人はただの紙切れだと笑い飛ばすでしょうね」
「次の祭りはいつだい? もう一度君の名前を呼ぶよ」
「あら、二回目のプロポーズ? ふふ、嬉しいわね。でもそんなことをしなくてもよくてよ。私から村の人に事情を説明しておくわ――もちろん、あなたが火刑台にのぼって火傷を負ったことは伏せておくけれど」
はい、とバルマウフラはオーランの寝ているベッドの横に置かれた、軟膏やら薬草やらがどっさり積まれた小さな木机の上に、銀の指輪をおいた。
「煤で焼けてしまったから磨いておいわたわ。村でも指輪を贈り合う夫婦は多いから、これを見せたら私たちの関係について信じてもらえると思うわ。それと、最後まで……身につけていてくれて、ありがとう……」
オーランが探していた結婚指輪だ。服をはぎ取られ、罪人の服を着せられ、その麻服以外は何物も身につけることを許されなかった。それでも、この指輪だけは、と司祭にこいねがい、最後まで手放さなかったものだ。なくしたわけではなかったようだ。オーランは安心した。
「いや、でも僕は村のしきたりに従うよ。ここは君の大切な故郷だろう? 次の祭りはいつだい?」
最初にこの村で目覚めた時、村人はバルマウフラの住む森のことをラナの森よ呼んだ。彼女は故郷の名前をずっと名乗っていたのだ――母を殺され、教会にさらわれ、故郷に帰ることすらできず、そして、貴族の妻となりその名前さえ捨ててくれた。だから、せめて彼女の大切な故郷のしきたりに従って、もう一度プロポーズをしたいとオーランは思った。
「次の祝祭はラマスね。収穫祭よ。だけど、間に合わないわ」
「どういうこと?」
「私は領地――あなたの領地よ――に帰るから。息子の世話をしないと。考えてみて。異端として殺された父親と、素性あやしく魔女と噂される両親の間に生まれた子が、周囲から干渉されずにまっとうに生きれると思う? 私たちの子を守ってあげないと……」
オーランは歯がゆかった。白書を世に出すこと、それが自分の使命だと信じて疑わなかった。けれど、その使命のために、どれだけのものが犠牲になったのだろうか。
「バルマウフラ、君ひとりでは行かせられない。僕の息子だ。僕も一緒に――」
「何を言っているの? 寝言かしら? あなたは処刑された死んだ。私は夫を亡くした未亡人。これが事実なのよ。死んだ人が帰ってきたらお屋敷は大混乱して、死者の霊を祓う専属司祭を雇うことになるでしょうね」
「ああ……はい……ここでおとなしく寝ています……でも、僕がしでかしたこんな状況の中で、息子をひとりで育てるのは大変だろう。君ばかりに負担をかけたくない」
バルマウフラは誇らしげに笑った。
「私は今まで誰と仕事をしてきたか知っている? 私の仕事仲間は今はこの国の王よ。息子には最高の処世術を伝授できるわ」
オーランはむすっとした。国王――あの男――ディリータのことはどうも好きになれない。これはオーランの個人的な感情だ。妻が奴のことを誇らしげに語る時、オーランは不機嫌になる。オーランはベッドに積み上げられた毛布を顔まで引き上げた。
「あらあら、嫉妬?」
「……放っておいてくれ」
「オーラン、あなたは、つらく苦しい試練に耐えた。それはあなた自身が選んだ道。私もあなたの夫になり、貴族の妻になるという道を選んだ。だから私の使命を果たさせて。幼い我が子には庇護が必要……でも、彼が成人して、私たちがそうしたように、彼もまた自分の道を選択したのを見届けたら……そうしたら、またこの森に帰ってくる。その時には、また私の名前を呼んでね……その日をずっと楽しみにしているから……」
「旦那、旦那は本当にヴァイゼの旦那様だったんですな。ヴァイゼが指輪を見せてくれたんです」
バルマウフラはオーランが寝ているうちに静かに旅立っていった。けれど、旅に立つ前にオーランとの関係をちゃんと説明してくれたようだ。おかげで村人がオーランに物珍しげな視線を投げかけてくるようになった。どこの都市でも村でも、男女の恋愛は話の種だ。きっと彼らは、オーランがどういう経緯で森の魔女の夫になったのか知りたくてしょうがないのだろう。
「いやぁ本当にびっくりしましたよ。まさか、あのヴァイゼが――森を出る時はあんなに小さな少女だったのに――十年ぶりに森に帰ってきたかと思えば夫を連れてくるとは……しかし、ヴァイゼはまた気まぐれに森を出て行ってしまった。旦那も後を追うんです?」
「いや、私はしばらくここで世話になるよ。まだ傷も当分治らないだろうし」
「夫婦なのに、離れて暮らすんですか?」
「ああ……それが私たちの選んだ道だからね。それに、私はまだここでは彼女の夫ではない。ここでは祝祭の時に互いの名を呼んで夫婦になるそうだね。その日まで、私は彼女の夫ではなく、ただの……」
オーランはそこで言葉を詰まらせた。今や、自分は何者だろうか。貴族としての命は失ってしまった。魂をかけて書き上げた白書も、世に出した。貴族でもない、学者でもない、彼女の夫でもない……だとすると……
「旦那、いったい旦那は何者ですかい? 森の魔女は代々、私ら村の人間に知識を与えてくれた。そして、そのお礼に、私らは彼女らにパンや薪やらを渡し、生活を支えてきた。代々のヴァイゼフラウは時々珍しいものを持ってくることもあったが、人間の男をもってきたのは初めでね」
「ああ、そうだね、その通りだ。私は彼女の『知識』だ。占星術士――星を読む人間だ」
「ほう、それは珍しい。村に初めての『知識』だ」
男は目を丸くした。天上の星の世界にも知識があるのかと驚いている様子だ。
「それで……旦那にはどんな対価をお支払いしましょう。ヴァイゼが留守にしているので今は旦那に対価をお渡ししましょう。けど、俺ら村人には、その、星の知識に対してどんなお礼を渡せばいいのかさっぱりでして……」
オーランは答えた。
「多くは望みません。怪我が癒えるまでの手当てと、ここで生計を立てるまでの間の食べ物をください。あとは、いつか私が妻の名前を呼ぶ日に、あなたがたの祝福をください――それだけで十分です」
彼女はいつ帰ってくるのだろうか。彼女の名前を呼べるまで、いったいどれだけの日を待つのだろうか。
しかし、これで良いのだ。想う時間が長ければ長いほど、想いはあふれるのだから――