.
「おじちゃんはどうしていつも黒い服をきているの?」
黒い服のおじさんに、おそるおそる近づく小さな少女。ふわっと金髪が肩の上で跳ねる。少女は好奇心旺盛だ、普通の人なら近づかない怖いおじさんにも物怖じせずに近寄っていく。だからおじさんの方が怖じ気付いてしまう。黒い服のおじさんは畏国で一番恐れられた暗殺者だった。夜にとけ込む漆黒のマントで素性を隠し、彼の素顔を見たものは誰一人としていなかった――近づく前に彼に心臓に打ち抜かれてしまうのだ。おじさんは凄腕の狙撃手でもあった。
「嬢ちゃん、興味半分に俺に近づくなよ。火傷するぜ」
「だって……知らない人には近づいたら駄目ってパパが言うの。おじちゃん、騎士団のひとでしょ。パパの騎士団の人なのに、一緒にいたらパパに怒られるなんてわけがわからない」
この嬢ちゃんは、騎士団長の箱入り娘。メリアドール嬢ちゃん。大事に大事に甘やかされて育てられてる。
おじさん――バルクは思った。俺がもし父親だったら、俺みたいな輩には娘を近づかせないぜ。騎士団長も父親だな。
「ね、おじちゃん。パパは騎士団のみんなは家族だって言ってる。私もおじちゃんともっと仲良く――」
バルクは笑った。
「ごっこ遊びは別の兄ちゃんにやってもらいな。俺は向かねぇよ」
バルクはきびすを返してメリアドールに背を向ける。家族ごっこなんて冗談じゃない。ちびちゃんと遊ぶのは向いてない。俺は……
「バルク」
どこから現れたのか、背後から低い声で呼びかけられた。振り向かざるを得ない圧力を感じる。渋々、声の主を振り返る。げ、副団長じゃねえか。こいつは堅物だ。いつも不機嫌だ。説教が長い。融通が利かない。ともかく面倒だ。
「あんだよ」
「なぜ、メリアドール様のご要望を無視するのだ。メリアドール様はヴォルマルフ様のご息女。彼女の命令をすることは、すなわち団長に離反すること。たたき斬るぞ」
バルクはため息を一つついた。こう言われたら相手をするほかはない。バルクは少し居心地が悪くなった。嬢ちゃんのわがままにつきあうのが嫌なわけではない。
だたちょっと、過去を思い出して感傷に浸っているだけだ。
バルクは、胸の中に密かに隠している。銀のリングに手を当てた。昔の記憶はここにある。
――どうしておじちゃんはいつも黒い服を着ているの?
嬢ちゃん、俺はまだ夜の中に生きてるんだよ。
――俺あ、ゴーグに帰るぜ。
――どうしたんだよ、バルク。しけたこと言うなよ。一緒に王の首を狩りに行こうって誓った仲じゃねえかよ。この腐った国を変えられるのは俺しかいないって、おまえは何度も言った。途中で降りるなんて承知しねえぞ。おめえの頭、腐っちまったのか。
――ガキができたんだよ。帰って顔見せてやらねえと。一回くらい抱いておかないと親父の顔も覚えてくれねえだろう。顔みせたらすぐ戻ってくるよ。
――やめとけ、一度でも抱いたら情がうつる。そしたら二度と戻ってこれなくなる。
その言葉に嘘はなかった。ゴーグに帰って、女房に小言を言われ、かわいい赤子に対面するのだ。この日のために、ちょっとした銀細工を彫金してきた。そういや婚約指輪も作ってなかったしな。女房に待たせてごめんよと謝るつもりだった。
けれど、その日は永遠にこなかった。
女房が待つ家はなかった。瓦礫の下だった。夫の帰りを待っていた妻は腹ごと潰れていた。
バルクはそこで自分が何者かを思い出した。
畏国で最も恐れられるテロリスト。それが未来の国家を作るためだと信じて、壊し、奪い、崩してきた。たやすいことだった。破壊するのはあまりにも簡単だった。
――これが俺のしてきたことかよ。すまねぇ。
俺の子だった。抱き上げて名前を呼びたかった。女だったのかも男だったのかも分からず。名前をつける間もなく。世の光を見る間もなく瓦礫の下へ。
――抱いたら、二度と戻ってこれなくなる。
でも抱けなかった。因果だ。破壊者として生きてきた報いを受けたのだ。
なんでだよ。俺はガキらが虐げられない国を作るために、生きてきたんじゃないのかよ。幸福を願うと不幸がやってくる。それが世界なのかよ。世知辛えな。神なんてクソくらえ。
「黒い服のおじちゃん、私も騎士になるの。いつかパパの騎士団ので一番強い騎士になるわ! 私もおじちゃんと一緒の騎士よ! そうしたら……家族になれるよね?」
「嬢ちゃん……」
家族なんて言葉の意味はとうの昔に忘れてしまった。
――探したぞ、ブラックリスト一番手のテロリストよ。
――おい、取り込み中だ。話は後だ。
家族のために即席の墓を作った。妻と、まだ生まれてこなかった子供のために。バルクはいつもと変わらず素顔を隠す黒のマントで身を覆っていた。だが、これは暗殺者の衣じゃない。死を悼む喪服の色だ。
そこへやってきたローブの男。相手も黒色のローブをまとっている。黒。闇にとけ込む影の色。祈りの黒色。バルクにはその黒色の意味が分からない。こいつぁ、誰だ?
――てめえ、誰だよ。俺の首を狩りにきた野郎か? いいぜ、存分に戦ってやるぜ。俺の首は安くないからな。だが、今は駄目だ。俺は祈っているんだ。邪魔するな。5分待て。
――5分と言わず、いくらでも祈るがいい。私も祈ろう。それが私の仕事でもあるから。
バルクは首を傾げた。怪しい男だが敵対心は感じられない。
――申し遅れた。私は神殿騎士のヴォルマルフ・ティンジェル。今日は剣を持っていない。戦う準備はしてない。頼むから、私に銃を向けてくれるなよ。丸腰だからな。
変な野郎だ。騎士団長ともあろう人間が丸腰で、テロリストの隣に座って、墓石を見つめている。何を考えているのやら。
――家族を亡くし、寂しかろう。
――……あたりめえだ。
バルクは妻の墓石を撫でた。生きてるうちにできなかった愛撫。冷たい石を撫でるのがこんなに虚しいとは。あんたは寂しくない。子供と一緒に逝っちまったから。だから俺は寂しい。一人取り残された、我が身の、どうしようもない寂しさ。
――私も細君を亡くしてな……
この風変わりな騎士団長は唐突に語り出した。彼の妻のこと。妻がいかに美しく、きれいで、可愛らしかったか。自分がいかに妻を愛し、愛されていたか。もう亡き人だが……と、永久に終わらぬ愛の言葉にバルクは静かに耳を傾けた。いつもなら他人の惚気話なんてごめんだぜ、そう思うはずだった。でも、今は嫌じゃない。
「私のパパはね、とてもすごい騎士なの。ね、ローファルもそう思うでしょ? 私のいちばん憧れる人なの!」
「はい。お嬢様のおっしゃるとおりで」
嬢ちゃんの口から、パパがいかにすばらしい騎士か、次々に言葉があふれてくる。
ここの親父は愛されてるな。バルクは、嬢ちゃんの父親が妻をこよなく愛する良き夫だったことを知っている。まだこの騎士団に入る前に、長々と聞いたことがある……あの時、あの日、懐かしい。
記憶は過去から現在へ、現在から過去へ、ゆるやかに駆けめぐる。
――騎士団長さんよ、それで、俺に何の用だ。まさか俺のかみさんの墓参りにつきあってくれたわけじゃねえだろう。用件を話しな。くだらない用だったら俺は帰るぜ。
帰るといっても、もう家はなく。かつてのテロリスト仲間のもとへ帰る気もなく。どこへ行くのかさっぱり分からなかった。分からなくていい。俺は夜の生きる人間。行く宛なんて見当もつかない。
騎士団長は麻袋を取り出した。金だ。バルクにはその袋を持たずとも、音、大きさ、それだけで勘定がつけられる。
――俺を買おうって話か。全然足りねぇよ。俺の懸賞金いくらか知ってんのかよ。俺の首はそんなはした金じゃ売れん。
――あいにく、我が騎士団は清貧を誓っていてな……これ以上の金は出せない。だが、いい人材は惜しみなく私の騎士団に迎え入れよう。偉大なテロリストよ、今からおまえは騎士になるのだ。
――忠誠を誓って生きるなんて俺の性分には合わないね。帰れ。それかもっと金を出せ。俺を満足させろ。
――テロリストよ……いや、バルク。おまえはもう一人ではない。騎士団には同胞がいる。アジョラの血を分け合った仲間がいる。もう一人で孤独に戦う必要はない。
バルクは黙っていた。今し方家族を失った男の同情を惹こうと、この騎士は巧みに言葉を操っているのだろう。そこで、はい、喜んで、と答える男はそもそもテロリストにはならない。バルクもそうだ。無言で、険しい表情をする。
――俺は感情では動かない。騎士団に入ることで、それに見合う報酬が得られるのなら、考えてやってもいい。
――報酬? そうだな、私の娘を抱っこする権利を特別におまえにやろう。特別に1回だ。これは私と副団長にしか許されていない特別な権利だ……1回だけだからな!
――はあ?
バルクはあきれ顔で聞き返した。この男は何を言っているのだ。
――この上ない報酬だ。どうだ、好条件だろう。
でも、付いてきてしまった。他に行くところがなかったからだ。
そうしてテロリストは教会の騎士になった。
そして、今――噂のお嬢ちゃんに出会った。騎士団長の溺愛している、かわいいお嬢ちゃん。
「おじちゃん、パパよりずっと背が高いのね。ねえ、お肩をかして?」
人なつっこいお嬢ちゃんは、怖じ気付くこともなくバルクに絡んでくる。俺に抱っこして欲しいというのか? この俺に? 自分の子すら抱けなかったこの俺に?
バルクはおそるおそる、手をさしのべる。
「ちょっと」すかさず副団長が眉間に皺をよせて制止してきた。「団長の許可なくお嬢様を抱かないでください」
いつもは頷くしかない副団長の言葉だが、今日ばかりは、鼻高々に答えられる。
「はん、俺はな、団長の許可をもらってるぜ。嬢ちゃんを抱き上げてもいいってな――ほら、嬢、こいよ」
手をさしのべる。騎士団長からもらった1回だけの特別なチャンス。
メリアドールはバルクの手にぱっと飛びついた。バルクは軽く抱き上げる。嬢、軽いな。女の子はこんなもんか。肩にかつぐのも軽々だ。メリアドールはバルクの頬に顔をすりよせた。「すごいわ、お空が高く見える――おじちゃん、大好き」
ああ、いいな、こういうの。可愛い。すごく可愛い。
「バルク、頼むから、お嬢様を抱いたまま外へいかないように。誘拐犯がお嬢さまをさらったみたいに見える」
副団長のあからさまなため息。だがバルクもメリアドールを抱き上げるまでは同じことを考えていた。俺みたいなアウトローが嬢ちゃんに触れたら、釣り合わない、と。俺には父親なんてなれっこない、と。
「ローファル! おじちゃんは誘拐犯なんかじゃないわ。わるいひとじゃないでしょう?」
「あ、ああ……」バルクは答えに困った。俺は何者だろう。もうテロリストじゃない。騎士になった。でも相変わらず黒い衣を着たまま。影に身を隠す黒。いつまでも明けない喪の色。
――一度抱いたら、二度と戻ってこれなくなる。
ああ、その通りだ。俺はもう二度と戻れない。あの頃には。選んでしまったのだ。この仲間たちと生きることを。時は戻らない。瓦礫の下から妻が生き返ることもない。
「嬢、強くなりな。騎士になるんだろう。だったら自分の身は自分で守れるくらいに」
「うん。おじちゃんのことも守ってあげる」
「はは、それは頼もしいな」
夜明けは近い――長き喪がようやく明けるのだ。
Return to my Home
.
・バルクさんお誕生日お祝い小説
・妻子持ちバルクさんがどうしようもないヘタレ父親です
・オリキャラ出てくるのでご注意
Return to my Home
彼はいつも首から銀のリングを下げている。漆黒の衣に鈍く輝く銀のきらめき。
「バルク隊長、アウトローだった時からそれ、大事にしてますよね」
ふと気になって尋ねたのは、長いあいだバルクと一緒に戦場を駆けめぐってきた、アイテム士のジェレミー。
「ああ? お守りみたいなもんだよ。気休めさ。持ってると気が安らぐのさ」
「見てもいいですか?」
ほらよ、とバルクは旧友にリングを放り投げた。ジェレミーは落とさないように大事に受けとると、その銀細工をしげしげと見つめた。
「中に文字が彫ってあるんですね」
「俺が彫金したんだ」
そういえば、隊長は昔ゴーグで機工士をしていたらしい。ジェレミーが出会った時はすでに貴族から恐れられる荒くれ者だったから、ゴーグで暮らしていたという昔のことは知らない。バルクも語ろうとしなかった。
「隊長、誘拐犯みたいな見た目だけど、意外と手先が器用ですよね。銃とかも自分で手入れしてますよね。職人みたいだ」
「ああ、職人だったんだよ。昔はな」
「ところで、これ、何て書いてあるんですか? 畏国の言葉じゃないみたいだ」
「ロマンダにいた頃に作ったからな。ここの言葉じゃねえや」
「へえ! 隊長、ロマンダ語もしゃべれるんですか? すごいや、読んでみてくださいよ」
バルクはかたく首を振った。「だめだ。それはかみさんへのプロポーズの言葉だ。アイツ以外に言うつもりはねぇ」
あ、とジェレミーは声を漏らした。妻への愛の言葉を胸元で大事に守る男。その意味を察してしまったのだ。これは形見の品に違いない。興味本位で軽々しくたずねてしまったことをジェレミーは後悔した。
「すみません。私としたことが……奥様の思い出、どうが大事にお持ちください」
ジェレミーは銀のリングを隊長にそっと返した。だが、当のバルクは怪訝そうな顔をしている。
「なんでえ、そんなしけた顔しやがって」
「だって、奥様がとの、悲しい別れを思い出して、さぞおつらいでしょう……」
「女房? ゴーグでピンピンしてるぜ。ガキもそろそろいい年になってるだろうよ」
「……え、えぇえ? なんですって?」
ジェレミーは思わず、真顔で聞き返した。「奥様はまだ健在? しかも子供までいる?」
「ああ。娘だか息子だか分からんが。15年以上帰ってねえし」
「で、なんであなたはここにいるんですか? 奥さんほったらかして。子供の面倒もみずに! あなたは男として、人間として最低だ」
「それがアウトローとして生きるさだめだ。俺は修羅の道で生きてきた。女房もそれは分かってる。俺はアウトローとして生きると決めた時、女房に言った。俺は死んだものと思えってな」
「隊長、ではどうして、奥様へのプロポーズの言葉が刻まれたリングを隊長が持ってるのですか。あ、ペアリングですか?」
「い、いや一品物……タイミングを逃して渡しそびれた……」
「はぁ~~隊長、想像以上にどうしようもない人ですね。そんなんっだったら、もうフェニ尾あげませんから」
「待て! それは困る! 俺はお前がいないと生きていけない! 頼む!」
バルクはあわててジェレミーにすがった。この有能なアイテム士は、どんな障害物をもかわしてバルクにフェニ尾を投げつけてくる凄腕の戦友なのだ。
「だったら、奥様にちゃんとプロポーズしてきてください。私は腑抜けと一緒に戦う気はありませんからね。私、団長に隊長の休暇願いを申し立ててきます」
さっさと踵を返して立ち去るジェレミーをバルクは呼び止めた。だが、もう時すでに遅し。ジェレミーはすでにその場を去っていった。
「おいおい、今更求婚なんてこっぱずかしいことできるかよ。だいたい団長がそんなふざけた休暇願いを聞き入れるはずがねぇだろうよ……」
「団長OKです」
「話がはえーよ」
ジェレミーが鉄砲玉のように飛び出していってから5分も経たず、風呂敷包みを持って現れた副団長。
「我が神殿騎士団は礼節を重んじる騎士団。団員のご家族に挨拶をさしあげるのも長の仕事……といいたいところですが団長はご多忙の身ゆえ、私がともに参ろう。あ、これは手土産のミュロンド饅頭と銘菓あじょら餅」
「いらん世話は焼かないでいいっての」
バルクは風呂敷包みをひったくった。よりにもよってこいつと一緒に里帰りかよ。いつもフードを目深にかぶり、素性を隠し通す仏頂面の副団長。
「おい、もうちょっとマシな顔はできねぇのか。俺のかみさんはな、生まれたゴーグの町から一歩も外に出たことがない女なんだ。暗黒司祭みてえな奴が家に上がってきたら気絶するわ」
「大丈夫ですよ。ご婦人へのマナーはわきまえておりますから」
そういってローファルは、さっとフードを下ろした。トンスラの金髪が風になびく。顔には穏やかな僧侶の微笑みをたたえている。営業用スマイルだ。こいつも黙ってこうして立ってれば可愛い奴なのにな。
「バルク、あの子は連れて行かないのですか? あなたのことを随分と慕っているようですが」
「ジェイミーか? あいつは留守番だ。アウトロー時代を知ってる奴に、家庭のことは見せたくねえんだ……気まずいだけだろ」
バルクはため息をついた。ローファル、おまえもだ。できればこいつも置いていきたい。言外の意味をこめてローファルをじっとにらむ。だが帰ってきたのは副団長の圧だった。しかたねぇな。
「あ、おじちゃん、ゴーグに帰るってほんと?」
「嬢、どした」
ゴーグ行きの船に乗るため、まとめた荷物を持ち上げようとしたら、荷物のすきまに嬢ちゃんがすかさず滑り込んできた。バルクはじゃれついてくるメリアドールを引き剥がし、ローファルに押し付けた。子供の扱い方はどうも難しい。
「待って、おじちゃん!」ローファルの背の影からメリアドールはバルクに呼びかけた。「お・み・や・げ」
「はいはい」
しかたねぇな。何か買ってきてやるよ。
「あんたァ、この20年どこほっつき歩いてたんだね」
「ルツ……」
覚悟はしていた。扉を開けたら、不審者が入ってきたと鍋で撃退されるかもしれない。20年も家に帰らなかった男はもう死んだも同然だ。新しい夫が、女房の隣に座っているかもしれない。俺の女に手をを出すなと狙撃されるかもしれない。そんな心配が家に帰る間中ずっと頭を離れなかった。
杞憂だった。女房は健在だった。思ったよりずっと老けていたが。俺だって老けた。もうおじさんだ。
「覚えているかい、この俺のことを……」
「なんだい、その情けない顔は。あたしは、あんたの子を20年も育ててきたんだ。どうして忘れるんだい」
よかった。扉を開けて鍋でぶっ叩かれたのでは隣にいる副団長に永久に失笑される。それだけは避けたかった。
「ご挨拶が遅れてすみません」ローファルが一歩前に進みでる。「わたくしは神殿騎士団副長のローファル・ウォドリングと申すもの。ご主人を長らくお借りしており申し訳ございません、マダム・フェンゾル」
「あたしはマダムなんてたいそうなものじゃ……」
威勢のいいゴーグの職人街で育ったマダム・ルツ・フェンゾルは神殿騎士の挨拶にぎょっとした。ここでは彼女のことをマダムなんて呼ぶ者はいないのだから。ルツよ、こいつは俺以上に腹の黒い坊主だぜ。口に出しては言わなかったが。
ルツはバルクに小声でささやいた。「この坊さんは誰だい。あんたがさらってきたのかい? あんたはまだ誘拐犯みたいなことをやってるのかい? うちには教会のお偉いさんに払う金なんてないよ」
「俺の仲間だよ。俺は教会の騎士になったんだ」
「冗談はおよし!」
ルツはバルクの背中をバンバンと叩いた。「信じられない!」と豪快に笑っている。
ああ、俺も信じられない。俺が騎士だって。死んだ親父も驚いて墓から出てくるだろうよ。だが、事実なんだ。
「彼の言っていることは本当ですよ。マダム。彼の身元は私が保証します。私たちは教皇の勅命を受けて、この国の未来を作るために戦っているのです。彼は私たちに随分と尽くしてくださいます。彼の働きには、とても感謝しているのです」
では、私はこのあたりで。あとは夫婦水入らずでどうぞ、と気を使って退出する。ルツはまだ目を丸くしている。バルクはどうやって話をまとめればよいのか分からない。あ、そういや土産を持ってきてたな……「ほらよ、ミュロンド銘菓あじょら餅。食おうぜ」
「へぇ、神殿騎士団ね。国を壊してくるぜ、って息巻いて郷を出てったあんたが教会の騎士ねぇ……」
「国家に縛られたくないとアウトローになった俺が今や教会の犬だ。笑えるだろう。なあ」
「いや、あたしは難しいことはわかんないよ。あんたが生きててくれただけで嬉しいさあ。……だけど、ゴーグの隣で暮らしてんならもうちっと早めにけえってきて欲しかったさね。子育ても終わっちまった後に戻ってくるたあ、どんな父親だい」
「はい、ごもっともで……めんもくもない……」
あじょら餅の包みを広げて満足そうにほうばる女房の前バルクは静かになっていた。何も言い返せない。使いこまれたぼろぼろの食卓に座る、少し気まずい雰囲気の夫婦。バルクの右手には銀細工が握られている。いまだ、渡そう、いやまだだ、渡せない。気持ちが逡巡する。
「ルツ……」
「なんだい」
「いや、なんでもない……」
「ちょっと! はっきりしなさいよ!」
言えなかったプロポーズを。やっぱり郷を出る前に言っておけばよかった。畜生、失敗したな。
ルツとはゴーグの幼馴染だった。いつも一緒にいるのが当然だったから、プロポーズなんてこともなく夫婦の契りを交わし、連れ添うように一緒に暮らしはじめた。バルクにとって、己の命より大事な妻だった。だから、ゴーグを出てアウトローとして生きる決意をしたときは妻を巻き込むまいと、心に決めていた。彼女はゴーグの職人街でそだった善良な街娘。法を飛び越えて夜を渡り歩くアウトローの生き方を押し付けるつもりはさらさらなかった。
だからこう言ったのだ。
――俺は死んだものと思え。
テロリストの妻なんて肩書きを与えたくなかった。俺のことなんか忘れて幸せになれよ。そう言ったつもりだった。だが、妻は帰らぬ夫のことを待っていた。子供まで育てて。
俺、くそ野郎じゃねえか。新妻にプロポーズもせず、死亡宣告だけして家出同然に失踪して、20年も戻らなかった。夫のいない家で一人、子供を育てる妻がどんなに寂しかっただろうか……畜生、畜生。俺は父親になれなかった男だ。夫にすらなれなかった。
ゴーグを出てロマンダに渡ってすぐにガキが生まれた、という手紙はもらった。その時は郷に帰ろうと思った。だが、その時は戦争中で、必死に密航したロマンダからゴーグに飛んで帰るのは至難の業だった。だから、旅先でかき集めた金で、記念にちょっと洒落た銀のリングを作って、戻ったらちゃんと渡そうと思っていた。だが、アウトローの人生は波乱に満ちていた。3年、5年、10年、と時間が過ぎ、郷に帰るタイミングをずるずると失った。
怖くて帰れなかったのだ。妻に見捨てられていそうで。
「あんたは昔から怖いもの知らずの荒くれだったからね。ちゃんと、その、教会の騎士ってやつはうまくいくのかい。教皇さまと一緒に暮らしてるんだろ?」
怖いもの知らず? いや、俺はただの臆病者だ。20年も郷に帰れなかった小心者。
「まあな。騎士団には俺よりやばい連中がうじゃうじゃいるさ」
騎士団。嬢のことを思い出した。ゴーグ土産、何にすっかな。ああ、そうだ。嬢といえば、俺のガキはどこだ。
「ルツ、あの、その……おまえの子はどこだ?」
「腰が低いねぇ、あんたの子って言えばいいのに」
マイスターのギルドで徒弟修業中だよ、会いに行くかい、とルツに言われた。バルクはうなづいた。ああ、もちろん。だが怖い。やっぱり怖い。女房はともかく、一度も会ったことのないちびに何面で会えばいいのか。父親ではないな。通りがかりのおじさん顔をしておこう。
案内されたのはゴーグで一番広い工房。機工士として少年時代を過ごしたバルクはこの建物が誰のギルドなのかすぐにわかる。マイスター・ベスロディオ・ブナンザ。
「ほら」建物の窓越しにルツが指差す。
「おお、俺の子にしては随分イケメンじゃないか。人のよさそうな顔をしている」
「ちょっと! どこを見てるんだい。あれはマイスターの坊ちゃんだよ。いつフェンゾルの家に金髪がまじったんだい。うちの子はあっち」
ルツの渾身の突っ込みで背中をバシバシと叩かれた。「わかってるって、冗談だよ」
工房の隅で、粘土板に製図器を使って図面を書いている。小さな粘土板に描かれたのは一部分だが、バルクにはその機械がすぐに分かった。飛空艇だ。間違いない、あいつは機工士になる。間違ってもテロリストとして逃亡生活を送る人間にはならない。ほっとした。これは父親心だろうか。
「坊主」
バルクは窓から身を乗り出して石壁をトントンと叩いた。黒髪の少年が振り向く。ルツにそっくりだ。人相の悪い俺に似なくてよかったな。
「おじさん、誰」
「おじさんは通りすがりの騎士だ」
少年はあからさまに興味なさそうな顔をした。自分の図面に戻って没頭したいという雰囲気をかもし出している。
「坊主、機工士になるんだろ」
「うん。マイスターみたいになりたい」
「頑張れよ」
「うん」
数秒で終わってしまった会話。少しものさびしいが、まあ、失踪してた父親がいきなり出てきたと説明するのも難儀だし。マイスターのギルドにいるのなら、まっとうな機工士になるだろう。それでいいさ。
「あんた……もうちっと顔をみてったら」
「いいよ。怖い顔のおじさんに見つめられても不気味なだけだろう――さ、ちびの顔も見たし、俺はミュロンドに帰るよ。副団長を待たせてるのも悪いし」
今だ。去り際にかっこよく。「これ」銀の指輪を渡すのだ。「結婚の記念に渡そうと思ってた」待たせてごめんな。「ロマンダで作ったんだ」ちょっとかっこつけたかった。渡し忘れたせいで台無しになったが。
「あら、あんたにそんな気遣いができるとはね。愛の言葉でもくれるのかい」
バルクは苦笑した。
「あいにく、俺はそういうの得意じゃないんだ。だからかわりに指輪に書いておいた」
「あたしは目も悪いし、字もよめねえんだ。かわりに言っておくれ」
バルクは戸惑った。言うのか。愛の言葉を。俺に言う資格があるのか。言えるのか。
「……誰にも言うなよ、これは妻にしか言わないって決めてるからな」
やっと言うのだ。妻に20年越しのプロポーズを。
「へたくそ」
ミュロンドへ戻る船の上でローファルがぼそりとつぶやいた。
「あんだよ。夫婦水入らずで、とか言ってつけてんじゃねえよ」
「失礼な。私は護衛していただけです。あなたは自分の立場をわきまえた方がいい。どうして国家指名手配犯のあなたが、この数時間で誰にも狙撃されずに街中を歩けたと思います?」
ローファルは黒の僧服の袖口からするりとこぶりの長剣を取り出した。
「今日だけで何人始末したとお思いですか」
「ふん……いらん世話は焼くなって言ったろ……」
相変わらず物騒なやつだ。涼しい顔して、プロのアサシン顔負けの始末術を持っている。
「しかしあなたははどうしようもない父親ですね。息子の名前さえ聞かなかった。奥様はさぞがっかりしているでしょう」
「……聞いたら、情が移るだろうが。これでいいんだよ。騎士になったっていっても俺は影の住人だ。中途半端に父親面したくねぇんだよ」
「あなたは臆病者だ。ただ逃げているだけ。生きている家族が目の前にいるというのに、あなたは逃げ出した。あなたはいつか後悔する。生きているその手を自ら手放したことを」
「説教はよせよ。俺は自分で決めたことに後悔はしない」
「いいえ、あなたは後悔する。ヴォルマルフ様や私がそうであったように……」
ああ、団長も細君と死別してたんだっけな。副団長もか。ん、副団長? こいつもか?
「ローファル、あんたもか? あんた修道士だろ。結婚してないよな……?」
ローファルはふいと顔を背けた。そしてぼそりとつぶやいた。「私は孤児だった。父の名もしらず、誰に抱かれた記憶もない」
めったに心を開かない副団長がはじめて自分の過去を語っている。「そうか、あんたは寂しかったんだな……そうだ、なら俺がパパになって抱いてやるよ。今からでも遅くない。ほら、膝の上、あいてるぜ――痛ぇ!」
すばやい平手うち。さすが始末人。目にも留まらぬ右手の動き。しかも、おまえ、服の下に鎖帷子着てるだろう。痛ぇンだよ。
「わ、わたしのことではない。おまえの子の心配をしているのだ!」
「あーはいはい、どうせ俺は父親失格の人間だ。今更父親なんて無理だっての……まあ、練習したらいいパパになれるかもな。帰ったら嬢を借りるぜ。まずは抱っこの練習から――」
「隊長! 戻ってきたんですね。あれ、夫婦喧嘩でもしましたか?」
港で出迎えてくれたのは相棒ジェレミー。こいつとは勝手知ったる仲なので、挨拶代わりにポーションを投げつけてくる。ありがてぇ。副団長にはたかれた痕に寸分の狂いもなく塗り薬が炸裂する。
「いや、これは同士討ちだ。副団長の機嫌が悪かった。乱闘になった」
「どうせ隊長が失礼なこと言ったからでしょう。バルク隊長、空気よめないから……」
「うるせぇな」
アイテム袋をごそごそとあさりながらジェレミーが言った。
「奥様にちゃんとプロポーズしてきましたか?」
「ああ」指輪は渡したし。
「お子様にもちゃんと会ってきましたか?」
「ああ」窓越しに。通りすがりのおじさんとして。
「なら、今回の里帰りは大成功ですね! よかった。私、心配してたんですよ。20年も帰らなかった夫を見て妻が逆上して死闘になるんじゃないかって。ほら、フェニ尾、こんなに買って準備してたんですよ」
「ありがとよ。でも俺のかみさんは優しいから必要ねぇよ」
「そうですね、隊長よく死にかけてますよね。でも大丈夫ですよ、ストックが99本ありますから」
バルクはジェレミーをこづいた。「バーロー、俺は不死身だ。フェニ尾なんて捨てちまえ。妻子を残してそう簡単に死ねないからな」
014

013
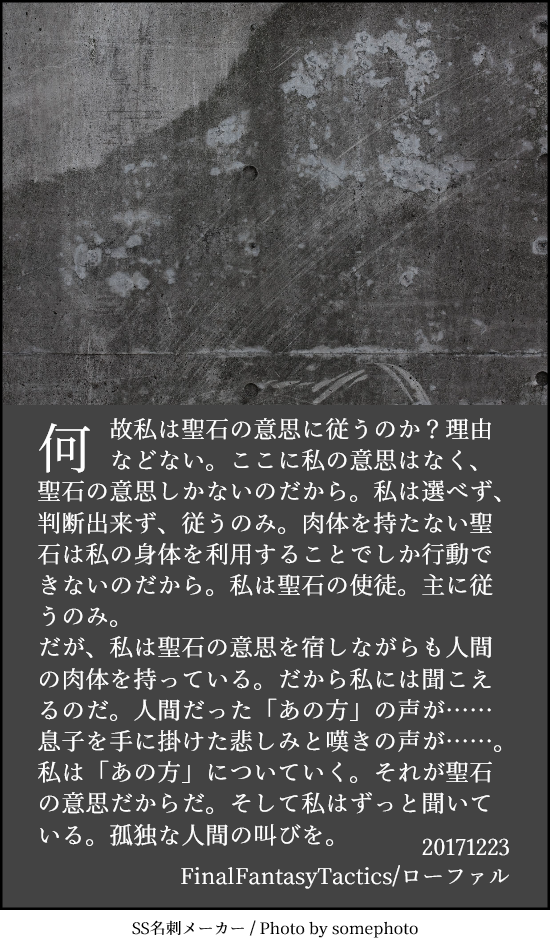
おひざでおひるね
.
・メリアドール(十代前半)、クレティアン(十代後半)、ローファル(永遠の年齢不詳∞)
・イズルードが登場させられなかったのですが、行外で元気に飛び跳ねているということで……
おひざでおひるね
今日はとても暖かい日だわ。
メリアドールは城館の裏口に座って午餐の後の穏やかな時間を満喫していた。伐り出された薪に肩を預けて城館で働く使用人や騎士団の人たちが忙しなく働いている様子をぼんやり眺めていた。こうしていると時々、騎士団の若い男たちがかまってくれることがある。
「お嬢さん、お暇でしたら私が相手をいたしましょうか」
メリアドールは声の主をちらりと見た。騎士団の制服を着た栗毛色の髪の青年。一日の大半を一緒に過ごしているためか、騎士団の人間の名前はたいてい覚えている。
「ええ、とっても暇。イズルードは裏の果樹園に行っていて、今日は誰も私の相手をしてくれないの。でもクレティアン、あなたは仕事中ではなくて?」
クレティアンは両手に本の束を抱えていた。見るからに重そうだった。
「副団長様の命令で書庫でさがし物をしていたんです。ですが急ぎの用事というわけでもないので、少しくらいなら……」
メリアドールが砂埃を払って隣のスペースを作ると、クレティアンはそこに腰をおろした。「一緒に本でも読みましょうか」そう言って持ってきた荷物に手を伸ばした。
まずい。そんなことになったら途中で寝てしまう。
メリアドールはあわてて首を振った。「わ、私はいいわ……あなたが隣で読んでくれるのならそれで結構」
本を読んだり歌を歌ったりするのはメリアドールにとって退屈極まりないことだった。それよりもメリアドールは身体を動かしている方が好きだった。木に登ったり森を駆け回ったりする方が性に合っている。でもこの人はそういう野遊びにはつきあってくれない。彼は騎士団にいる有象無象の山猿たちとは違って、由緒正しき士官学校を卒業してきた貴族の青年だった。
メリアドールはしばらくの間クレティアンの声に聞き入っていた。メリアドールのことを見もせずに隣で黙々と本を読み上げている。この人は、副団長が読むような本を私が楽しめると本当に思っているのだろうか。あたまのいい人の考えることはよく分からない。本の内容もさっぱり分からない。でもきれいな声。低くていい声をしてるわ。ずっとこうして隣に座っていたくなる。魔法を使う人はみんなこんなに穏やかなしゃべり方をするのだろうか……ちょうどいい心地よさにメリアドールはだんだんと眠くなってきた。
「あら、二人してかわいい」
通りすがりの使用人の声にはっとしてメリアドールは顔をあげた。暖かい日差しの中でつい船をこいでしまっていたらしい。
それにしても昼寝に最適なあたたかさだった。そう思って膝の上を見ると、いつの間にか寝落ちしていたらしいクレティアンが小さな寝息を立てている。気がついたらメリアドールが膝枕する形になっていた。どうりでぬくもりが気持ちいいと思ったわ。
「どうやら若騎士さまはお疲れのようだな」メリアドールは背後に人の気配を感じた。そして膝の上の若騎士を起こさないように、そっと聞き返した。
「ローファル? どうしたの?」
「その若いのを回収にきた。仕事の途中だ」
「あら、だめよ、お昼寝の途中で起こしたらかわいそうだわ」
メリアドールはローファルに向かって人差し指を立てた。もう片方の手で寝ているクレティアンの髪をそっと撫でた。穏やかな寝顔を見ていると無理に起こしてしまうのが忍びなかった。
「私、この前うっかり寝ているイズルードを踏んじゃったんだけど、そうしたらすごく機嫌が悪かったの」
「その男はイズルードより五歳以上も年上なのだから、その心配は無用だ。今すぐにたたき起こせ。午睡の時間はとっくに過ぎている」
「そう?」
だがメリアドールが声をかけるまでもなくクレティアンが気配を察したらしく飛び起きた。ローファルの無言の圧力を感じ取ったというべきか。
「クレティアン、さぞや良い目覚めだろうな」
「ウォドリング様――わ、私は決して惰眠をむさぼっていたわけでは……」
「そうか、レディに添い寝するのが騎士の流儀とでも言うのか。貴殿は士官学校で一体何を学んできたのだ?」
「い、いえ……」
クレティアンがその場から身体を引いてたじろいだ。
「そんなにいじめたらかわいそうよ、ローファル。それに私はレディじゃないから何も問題はないわ」
「……お嬢さん」クレティアンは気まずそうな雰囲気だ。「お膝を失礼いたしました。ですが、途中で起こしてくださってもよかったのですよ? 重くて邪魔だったでしょう……」
「別に? ちょっと重たい布団だと思ったくらいよ。それに、あたたかくて気持ちよかったわ」
「そうですか……布団ですか。あなたの布団になれたのなら光栄です――ですが、お父様にはどうかご内密に」
クレティアンはローファルの顔色をちらちらと伺いながらメリアドールに話しかけていたが、最後に一言念を押していくのを忘れなかった。
「で、では私は先に下がらせたいただきますので……」そう言って荷物をまとめるとその場から逃げるようそそくさと城館の中へと戻っていった。
「メリアドール。あなたには騎士団長の息女として身につけるべき礼儀作法がある」
「何?」
「もし今度若い騎士に膝の上を占領されることがあったら即刻蹴り落とすこと」
「そうなの。知らなかったわ。じゃあ次からはそうするわ」
メリアドールは満足げにうなずき、仕事場に戻っていくローファルを見送った。外はそろそろ日差しが傾いて来る頃で、メリアドールも何か手伝いに行こうとすぐに後を追った。
十十
日月 え の日(10/10)の記念SSです。
O daughter, never more bemoan
.
O daughter, never more bemoan
――眠れぬ夜に
『最近、眠るのが怖いの。そのまま起きれそうもない気がして』
部屋の入り口に女性が立っていた。寝間着姿のままで。
「メリアドール。こんな時間にどうしたんだ」
「一人で寝るのが怖くて」
ローファルはやれやれ、と言ってメリアドールを部屋に招き入れた。
メリアドールはこうして時々、ローファルの部屋を訪ねた。誰にも知られずこっそりと――といっても真夜中の逢瀬といった艶めかしいものではない。
これは父親に甘えたがる娘のようなものだ。ローファルはそう思った。実の父親が厳格すぎるせいか、いつしかメリアドールはローファルに甘えてくるようになった。ローファルにとってもメリアドールのことは家族同然に愛していたので、こうした関係を疑問に思うことはなかった。それどころか、年頃の女性になった今でも、昔と変わらずあどけない少女のような感情をローファルに向けてくれるメリアドールのことを愛していた。
「一緒に寝てもいい?」
メリアドールはローファルに聞くと、すかさず彼のベッドに潜り込んだ。彼女はここが最も安全で、心安らぐ場所だと心得ていた。
ローファルは毛布を引き上げ、横になったメリアドールの身体を優しく包んだ。メリアドールはローファルの服の裾を引っ張った。仕方ないな、というそぶりでローファルはメリアドールの隣にすべり込んだ。
「悪夢にうなされるの」
「どんな?」
「弟が……異形の怪物に殺される夢」
「それはただの夢だよ」
“そう、それはただの夢であってほしい”
「でも、弟は死んだわ。それは夢じゃない」
「そうだね、夢ではない」
“そう、それは夢ではない”
ローファルは寒さと底知れぬ恐怖に震えるメリアドールの手を握った。今だけは、このぬくもりが伝わるように――
ノックもせずに誰かが入ってきた。ローファルはすぐに分かった。長年の騎士修行のおかげで、人の気配だけでその動き察することができるようになった。ローファルはメリアドールを起こさないようにそっとベッドから這い出ると、部屋の片隅に置いていた剣を手に取った。そして、いつでも抜けるように身構えた。
「娘を探しにきた」
騎士団長の声だった。
「娘がいないと思って探しにきてみれば……」
ヴォルマルフは途中で言葉を切ると、ちらりと部屋の様子を見た。メリアドールは毛布にくるまってベッドの上で丸くなっている。ヴォルマルフの視線をローファルは感じ取った。
「神殿騎士として、お互い何もやましいことはしていませんよ」
ローファルはきっぱりと答えた。手に剣を持ったままで。
「誰の娘だと思っている――私の娘だ。勝手に連れ出さないでもらおうか」
「<誰の>娘ですと?」
「私が父親だ。そこをどけ」
「父親は死んだ。あなたは父親ではない」
ローファルは迷わず剣をヴォルマルフに向けた。
「息子に剣を向けられ、娘に逃げられ……おまえも私を拒むのか」
「これが、イズルードを殺した報いですよ」
それを聞いてヴォルマルフは鼻で笑った。
「器にならぬ人間を殺して何が悪いのだ? あいつの肉体は――」
ヴォルマルフが言うより先にローファルが剣を振り下ろした。その切っ先はヴォルマルフの顔をかすめて壁をしたたか叩いた。乾いた金属音にメリアドールがかすかに身じろぎした。ローファルはその気配をすかさず感じとった。
「誰であろうと――たとえ騎士団長であろうと、死者の名誉を汚すことは許されない。彼は正しい理想に殉じた――<私たち>には到底、為し得ないような偉業を果たしたのだ」
剣を握る拳に力が入った。
「ふっ……おまえがそう思いたいのならせいぜい勝手に想像しておくんだな。だが忘れるなよ。おまえは私の眷属であることを」
「ですがその前に、私は誓いを立てた騎士なのです」
ヴォルマルフはローファルの手にしていた剣に一瞥をくれるとそのまま部屋を出て行った。
「騎士か……騎士なら戦え。その剣で血を得よ。それがおまえの役目だ」
ローファルは剣を床に投げ捨てると、ベッドの縁に身体をあずけてその場に力なく座り込んだ。そして膝に顔を埋めた。騎士の誓いを立てたのが大昔のことのように思える。どんな文言を唱えたのかすら記憶にあやしい。
とはいえ、目を閉じれば思い浮かぶのは色あせた昔の記憶ではない。つい最近のことだ。色鮮やかな――鮮血の記憶だ。
“彼は死んだのだ”
“いいや、殺されたのだ”
“誰に?”
“父親<だった>男に殺されたのだ”
若い騎士の姿が思い浮かんだ。栗毛色の髪をしたあどけなさの残る少年だ。彼がどうやって最期を迎えたかは、同じ城に居合わせたブロンドの少女から伝え聞いた。
『彼は勇敢に戦って亡くなりました』
ああ、イズルード。おまえは年は若いが立派な騎士だった。メリアドールがその死を悲しんだように、ローファルもまた悲しんでいた。人知れず流した涙を誰も知ることはなかったが。
「しかし……さすがに父親に剣を向けるのはしのびなかったか……」
『それでも彼は最期まで手放そうとしませんでした』
彼がどんな気持ちで剣を握っていたのか……想像するだけで胸が潰れそうだった。
『そして、彼は私に彼の聖石を託してくれたのです』
彼は騎士だった。守るべきもののために戦った。その行為は報われるべきだ。たとえそれが、不幸で惨めな『死』で終わったとしても。そこに栄誉を認めることが彼への弔いになる――もはやそれ以外に為す術はないのだから。
“それでは私の剣は何のためにあるのか”
ふわりとした感触が肩を覆った。
「そこで何をしているの?」
メリアドールがベッドの上から不安そうな顔を見せていた。
「寒くて凍えているの? 震えているわ」
メリアドールはさっきまで自分がくるまっていたあたたかい毛布をローファルの背中に羽織らせた。
ローファルはメリアドールの温もりを肌で感じた。
「起こしてすまなかった」
「誰か来たの?」
床に落ちた剣をメリアドールは見つめていた。ローファルは首を振った。「いいや、誰も来ていない」そう言うと、ベッドの上で身を起こしているメリアドールを毛布でくるみなおした。
「心配ないよ、さあ、寝て」
「……だめ、怖くて眠れないの」
「何が怖いんだい」
「……」
メリアドールはうつむいた。
「ほら、おじさんに言ってごらん」
暗がりの中でメリアドールがふふっと笑うのが聞こえた。しかし、声は悲哀の色を含んでいる。
「……もう剣は持ちたくないの。ごめんなさい……私、もう戦えないわ……」
「イズルードのことか」
メリアドールは答える代わりにローファルの服をきゅっと握りしめた。声にならないすすり泣きが聞こえてきた。
ローファルはたまらず、メリアドールを抱きしめた。深く、優しく、そっと。
“この光景を団長が見たら怒るだろうか”
“いや、かまうものか。彼女を守る家族はもはやいないのだから――”
“私が父親だ”
父親が娘に願うことはただ一つ。その身の幸せ。限りない幸福。
「でも、私……弟の仇を討たなきゃって思うの。なのに、どうしてだか、身体が動かないのよ……」
“メリアドール。剣を持ちたくないというのなら持たなくていい”
“君が復讐の血でその手を汚す必要はないんだ”
“父親ならそう思って当然だろう?”
「ローファル、誰が弟を殺したか分かる?」
ローファルはこの質問をおそれていた。なぜなら、答えることによって、メリアドールを血の復讐に巻き込むことになってしまうからだ。まして、父親の身体に宿る悪魔が弟を殺したと、どうやって説明すれば良いのだろうか。
“私は彼女がこの悪夢から解放されることを望んでいる”
“悪夢から解放するすべただ一つ――私が彼女を手放すことだ”
「ローファル? どうしても私は弟の仇を討たなければならないの。お願い、知っているなら教えて」
ローファルは答える代わりに、メリアドールに尋ねた。
「どうして、そこまで復讐にこだわるんだ? 剣を持つのが怖いというのなら、無理に戦いに挑む必要はあるまい……」
「だって、イズルードは私の家族だもの。弟の死が無駄ではなかったと、価値あるものだったと私は証明したいの」
「そうか……しかし私は何も言えない」
「なら、一つだけ教えて。再び剣を持つ勇気をどうやったら思い出せる?」
「自らの道を信じることだ――その剣を持って行くといい」
ローファルはさっきまで自分が持っていた剣――ヴォルマルフに突きつけた――を指し示した。青白く光る刀身を持つ、特別な騎士剣だった。<守護>の銘が刻まれている。そう、騎士の誓いが刻まれているのだった。
“もはや、私には必要のない剣だ”
“彼女が持つに相応しい”
ローファル・ウォドリングはかつて偉大な騎士だった。時は無慈悲に流れようと、かつての騎士の誇りが完全に消えてはいなかった。
“剣よ、同伴かなわぬ騎士に代わって彼女に尽きせぬ守護を与えよ”
メリアドールは夜明けに旅立っていった。
「私の娘はどこへ行ったのだ」
ヴォルマルフはメリアドールが行方をくらましたことにすぐ気づいたようだった。
「行方を知っているのだろう。ローファルよ」
「さあ。彼女は弟の仇を討ちに行くとだけ言っていましたが」
「その言葉の意味を分かっているのだろうな」
「ええ。遅かれ早かれ、彼女は事の真相に気づくでしょう。そうしたら――あなたを殺しに戻ってくる」
ヴォルマルフは馬鹿げた話だ、とだけ言った。
「出来るはずがなかろう。愚かな姉弟だ。共に血の海に沈めてやろう」
「あなたは父親ではない。娘と呼ぶ権利はない」
「ほう……? それがどうした。些細なことではないか」
“そう。これは些細なことだ”
“騎士団長の身体に、父親ならざる異形の者が住み着いているとは誰も気づいていない”
“メリアドールはいずれ弟の仇を討ったとき、父親を殺すことになったと嘆くのだろう”
“だが、その復讐が死んだ父親の魂の無念を晴らすことになるのだ”
それは決して『些細なこと』ではないとローファルは知っていた。
――娘よ、嘆くことなかれ。たとえその手が復讐の血で汚れようとも。
――その両手は無辜の死者らが流した涙によって清められるのだから。
ボスは愛娘を手放さない
.
ボスは愛娘を手放さない
◆1
年頃の娘を持つ父親として、いつか言われるであろう台詞を覚悟してた。“娘さんを私にください”というあれだ。
もちろん、絶対にくれてやる気はない。
「団長、参謀から申し上げたいことが……」
「クレティアンか。なんだ、言いたまえ」
「二十歳の娘の父親はそろそろ子離れする時期かと」
「貴様……次元の狭間に葬られたいのか?」
だいたい、求婚するにしてももっと言い方があるだろう。私はそんな礼儀も知らない男に娘を渡すわけにはいかない。
「私の娘はそのことを知っているのか」
「いえ、でも承知の上かと。それに父親に先に話をしておくのがマナーかと思いまして」
まるで娘と結婚できるのが当然だと思いこんでいるこの求婚者の態度が私は気に入らなかった。私の優秀な部下であるのに、私の許可なくいつの間にか“そういう仲”になっていたらしい。腹立たしい。
「ローファル、例の本を持ってくるのだ」
私は騎士団長として様々な権限を持っている。気に入らない娘の求婚者を消し去るのはたやすいことなのだと、この恐れ知らずな参謀に思い知らせてやろうと思った……が、副団長は私の命令が聞こえなかったのか聞こえて無視しているのか、何食わぬ顔をしてそっぽを向いている。
副団長はどうやら中立を決め込んだようだ。
こいつはどっちの味方だ? 大事な娘の将来がかかっているというのに。
そういう訳で、私は一人でこの問題に話をつける必要があった。
「おまえは私の娘を手に入れられると思っているようだが、それは間違いだ」
「何故です? 私はお嬢様の愛を得るにふさわしい人物だと思っていますが。恥じるべき行為は何一つしていません」
悪びれる風もなく、涼しげな声で私に口答えをする。私に物怖じせず言ってくるのは後にも先にもこいつと副団長くらいだった。「団長が参謀の助言を無視するのはいかがなものですか」とまで言ってくる。これで無能な部下であればすぐにでも娘の手の届かない場所に左遷してやるのだが……。
「そんなに娘に惚れ込んでいるのなら教えてやろう……我が娘は家出中だ」
さすがにこの言葉は居丈高な若き参謀にも多大なショックを与えたようだった。当たり前だ。私も娘の家出で言葉を失ったのだから。
「お、お嬢様は今どこに……?」
「分からない。私が知りたいくらいだ」
さて、どうしてものかと私が考えあぐねていると、副団長がそっと私に助言をしてきた。彼の助言は参謀の戯れ言よりも結構役に立つのだ。
「良い青年ですよ」
「なんだね、ローファル。おまえまであいつの肩を持つのか」
「参謀が傍にいれば誰も手出しできません。最適な虫よけではありませんか」
「そ、そうか……そうなのか?」
「それに、彼は誰よりメリアドールさまに惚れ込んでいますよ。結婚許可を出せば、彼は確実にメリアドールさまをつれて帰ってくるでしょう」
娘が帰ってくる。その言葉に私は心を動かされた。激しく癪に障るが、それならばこの参謀に頼んでもいいかもしれない。だが、娘の相手に選んでも良いかということとは全く別問題だ。
「さあ、クレティアンよ。娘をつれてこい。団長の命令だ。話はそれからだ」
「当然です。お嬢様の身に何かあってからでは遅いのですから。団長の命令があろうとなかろと私は迎えに行きます」
そう言い残してさっさと部屋を出て行った。
「可愛げのない奴め……」
ああ、娘よ、あんな男のどこが良いのだ……。
私は頭を抱えた。これは深刻な問題だ。
◆2
「メリアドール……さっきから僕たち付けられてないか? 人の気配を感じるんだ」
「あら、だってここは貿易都市だもの。たくさん人がいるわ」
「いや、もっと執念深い気配を感じるんだけど……ストーカーみたいな」
「ああ、あの人なら大丈夫よ。無害な人だから放っておけばいいのよ。ただの父の部下だから」
「お嬢様! そこまで気づいているのなら私を無視しないでくださいますか?!」
ああもう、うんざりだわ。せっかく家を出たっていうのに、父の部下が探しにきたなんて私の面目が立たないじゃないの。ああ、ほら、ラムザが怪訝そうな顔をして私を見ている。
「それで、一体何をしにきたの。ドロワさん?」
はやく家に帰ってこいというお小言を父に代わって言われるのだと思った。
「あなたを愛しています。心から愛しています」
私は全く予想していなかった言葉に度肝を抜かれた。
「私はあなたのお父上と話をしてきたのです。なのにお嬢様が家出中では話になりません。ですから、早くお父様と和解してください。そして家に帰ってきてください」
「そ、そういう話は……私が家を出る決断をする前にしてほしかったです……」
タイミングが悪すぎるのよ。
「ええ。そのつもりでしたが、気づいたらお嬢様が相談もなしに家を飛び出してしまっていて……」
当たり前じゃない。家出するのに相談するわけないじゃない。それに――
「――父に言う前に私に先にプロポーズをすべきではありませんこと?」
「では、ここでお嬢様に正式に求婚します。指輪の銘はお嬢様の好みを聞いてから作らせようと思ってましたが……では、『我が唯一の望み』と『我が心は永久に』のどちらが良いですか――」
「ちょ、ちょっと、お待ちなさい! こんな街中でのプロポーズなんて私認めませんからね!」
あまりに恥ずかしさに顔が赤くなるのが分かった。このやりとりを隣で聞いているラムザは何を思っているやら……。
「僕は席をはずしますから、あとは二人でどうぞ」
あ、よかった。紳士だわ。
そうしてドーターの街角を二人で歩いていた。クレティアンは私をちゃんとエスコートしてくれたけれど、時々心配そうに後ろを振り返った
「お嬢様が迷子になっていないか不安で……」
この人は私を何だと思っているんだろう。私はもう二十歳なのに、まるで手の掛かるお嬢様だとでも言わんばかりの態度だった。
「ラムザにどう思われているか心配だわ。私の実家がとんでもないところだって思われてないかしら。ああ、それにきっと、私は世間知らずのお嬢様だって思われてるに違いないわ……」
「お嬢様が世間知らずなのは事実でしょう」
この失礼極まる発言は聞かなかったことにしてあげた。彼は方々を訪ねて周り私のことを探してやっと見つけてくれたのだから、多少はその苦労に報いてあげようと私は思った。それに、年上の騎士に愛を捧げてもらう喜びが分からないわけでもなかった。
「あの方はベオルブ家のご子息様でしょう? あとで挨拶に行かないと――お嬢様が失礼なことを言っていないと良いのですが。まさか出会い頭に喧嘩を売ったりしていないでしょうね」
「で、でも、ちゃんと、和解したわ」
ああ、もう本当に、にくたらしい人ね。……悔しいけど、全くその通りなのよね。
「思いこみで行動してはだめだとあれほど言っているのに……あなたという人は……」
余計なお小言よ。
「あなたは、私に求婚しにきたのではなくって? それとも御託を並べにいらしたわけ?」
「そんな……分かりきったことをわざわざ聞かないでください、お嬢様。それで、私ははるばる求婚しに来て、快い返事の一つももらえずに帰るのですか?」
「同じことばをそのままお返ししますわ。ドロワさん――私が快くない返事をするはずはありませんもの」
◆3
お嬢様はどうやら父親と和解したらしい。そもそもの喧嘩の発端は定かでないが、あの気むずかしいお嬢様をなだめて連れ帰ってくるのは大騒動だった。
「……ヴォルマルフ団長。私の働きには報いてくださらないのですか」
彼女は私がつれてきたのだ。私が迎えにいかなければ、今頃彼女はベオルブの御曹司と一緒に鴎国観光を満喫していたことだろう。それに団長とはまだ話の続きがある。お嬢様の家出騒動の前にしていた話が。
「何のことだね。言いたまえ」
知っているくせに。しらを切るつもりだろうか。
団長はご機嫌だ。なぜなら、大事な箱入り娘が帰ってきたのだから。繰り返すが私が迎えにいったのだ。お嬢様もご機嫌よろしく父親にくっついて「お父様、ごめんね」と言っている。団長も「よしよし、メリア。仕方ないなぁ」などと甘やかしすぎである。副団長もそんな様子をにこやかに見守っている。
そんな穏やかな団らんの中で私にこんな台詞を言わせるのだから、我が団長はさすがとしか言いようがない。この娘にしてこの父親、というものだ。
「……娘さんを私にください。お嬢様の許可はいただいています」
団長は驚いたようにお嬢様を見た。私の言葉はひとまず無視するようだった。
「そうなのか、メリア」
「うん」
「どうしてそういう大事なことを先に父さんに話さないんだ」
「だって、大好きなお父様ならゆるしてくれると思ったから」
「そうか……そんなにこの男のことが好きなのか? 嘘じゃないのか? 本当なのか? 本気なのか?」
「うん。ちゃんとプロポーズしてくれたのよ」
団長は難しい表情をしている。何を考えているのかは想像に難くないが……
「クレティアン」
「はい」
「どうやら娘はおまえのことを認めているようだ――だが私は断る。私が娘を手放すつもりはない」
「まあ、そうですよね……」
「もう、お父様ったら。あ、でもそれって私はお父様とずっと一緒に暮らせるってこと?」
お嬢様は嬉しそうだった。メリアドール、そこは喜ぶところじゃないぞ、私は言いたかった。これでは子離れができていないのか、親離れができていないのか、どっちだか分からなくなってくるじゃないか。
私の内心を悟ってくれたらしく、お嬢様がそっと助け船を出してくれた。
「でも、ドロワさんはお父様のためなら命を捨ててくれるって。立派な騎士だと思わない?」
「うむ、それはそれで心配だな……父親としてはまずは娘に命を捧げてほしいものだが……いや、おまえの献身は分からなくもないが、それは団長として嬉しいのだが、それと娘のことは別なのだよ」
「まあ、もういいですよ……」
ここは私が折れるところなのだろう。結局、私が騎士である限り、団長には頭があがらないのだから。そうしてその団長の娘を愛してしまったのだから。
◆4
「メリアドール、こっちへおいで」
「ローファル?」
父とクレティアンに聞こえないように私を近くに呼び寄せた。
「あとでクレティアンの部屋へ行ってなぐさめておあげ」
「何を?」
「今日のことを。クレティアンはヴォルマルフ様にちゃんとプロポーズしたかったんだよ」
「だって私は彼の求婚にはちゃんと答えたわ」
「それとはまた別のことなんだ。男はプライドが高い生き物だから、好きな人の父親の前ではいい格好をしたいと思うんだよ」
そういうものなのかしら。でも、ローファルはクレティアンとは長いつきあいがある友人だし……彼の言うことなら間違いないのだろう。
「でも、ドロワさんは私より父に忠義を尽くしてくれているんじゃないかと思うの……」
「多分彼も同じことを思っているよ」
「え?」
「お嬢様は一番愛しているのは父上ではないかと胃を痛めていた。有り体に言えばとても嫉妬している」
「だって……お父様のことは愛しているけど……それは家族だもの。当然でしょう? なんで父親に嫉妬するわけ?」
「男というものはそういう生き物なんだ。いつまでたっても娘を手放さない父親と殴り合いの一つや二つはするものだ――相手が騎士団長でなければね」
「ドロワさんがお父様に喧嘩売りにいく姿が見てみたいわ。お願いしたらやってくれるかしら」
「おそらくね。そうやって頼んで彼を困らせておいで」
ローファルはどこか嬉しそうだ。私はどうしてそんな顔をするのかと尋ねた。
「何故かって? 大事なお嬢様をそう簡単には手放したくないんだ。お嬢様への求婚者はこうやって少し困らせてやるくらいがちょうど良いのさ」
ローファルがこの二人(クレメリ)の仲人をしてくれるのは、「大事なお嬢様であるメリアドールの思い人だから」であって、クレティアンには「お嬢様に求愛するなら少しくらい覚悟しとけよ」という気持ちです。ローファルはメリアドールの第二のお父さん(?)です。みんなメリアドールのことが大好きなんです。末永く仲良くしてね!
星空の彼方
.
星空の彼方
むかしのことを思い出した。
母が亡くなって間もない頃、まだ人が死んだらどうなるのか分からなかった頃。いつまで経っても戻ってきてくれない母の帰りをずっと待っていた。
「かあさまはどこへ行ったの?」
その言葉に父は答えてはくれなかった。わたしに背中を向け、「遠いところへ行ったんだよ」
「どうして?」
繰り返すわたしに答えをくれたのはローファルだった。たくさんの魔道書。古の伝承歌。教会の教え。剣の持ち方。ローファルは、わたしの知らないことをなんでも教えてくれた。
蔵書室の傍らに腰掛けて、昔の英雄達の最後を語ってくれた。あれこれと、とても真面目に、<死後の世界>について教えてくれた。それでも首をかしげるわたしに、ローファルはとうとう諦めて、外へと連れて行ってくれた。
夜の帳の静かに落ちた後、空は満天の星が輝いていた。一つ、二つ、と星の数を数えていたら、
「母君はあの星の向こうへ逝ってしまった。こうなることは決まっていたんだ。イヴァリースに住む者は皆、星々の運行の下に生きているんだ。誰もそれを止めることは出来ないのさ……」
母がわたし達を置いて本当に遠いところへ行ってしまったのだと分かった。丸い天の下、たった一人取り残されてしまったような気がしてとても怖かった。悲しかった。そしてとてつもなく寂しかった。隣に座っていたローファルにぎゅうぎゅうと抱きしめた。この手で掴んでいないと、みんな遠くへ去ってしまうような気がした。
「メリア、そんなに抱きつかなくても、私はちゃんとここにいるよ。寂しくなったらいつでもおいで」
悲しいのか嬉しいのか自分でも分からなかったけれど、涙がぽろぽろと頬を伝った。
わたしを呼びに来た弟が不思議そうに見ていた。「ねえさん、どうして泣いてるの?」
「かあさまが遠くにいってしまったからよ」
弟はまだ母の死を知ることが出来なかった。死という残酷な響きを理解するにはあまりに幼すぎた。
「もうすこし大きくなったらわかることよ」
母が亡くなった時は悲しかった。弟が亡くなった時はもっと悲しかった。
「期待のゾディアックブレイブだったのに…」
あちこちでそうささやく声が聞こえた。ゾディアックブレイブの証の聖石はとうとう戻らなかった。折れた剣がひとふり、わたし達の許へ帰ってきた。それだけだった。
騎士として立派につとめを果たしました。ぼろぼろの剣はそう語っていた。けれど、わたしの心はそんな言葉で慰められることはなく。抑えられない悲しさにおぼれそうになっていた。
相変わらず父はわたしの前に顔すら見せなかった。もう家族がばらばらに引き裂かれてしまったように思った。それでも、その頃は、わたしも騎士として相応の分別を持ち合わせていたから、取り乱したりすることはなく、ローファルの許をそっと訪ねた。
「一体リオファネス城で何があったのですか?」
「……異端者と打ち合ったと聞く」
「そう……ならば、弟はミュロンドの騎士として死んだのですね。これも星宿の巡り合わせというものなのでしょうか」
答えはなかった。しばらくの沈黙が続いた。そして、ローファルはぼそりと、「違う、そうじゃなかった」と答えた。わたしは再び、「リオファネスで何があったのですか」と繰り返した。けれど、無言のままに扉を閉められた。内側から嗚咽が漏れた。「可哀想に」
可哀想に。真相も分からず夭折した弟も、たった一人残されたわたしも。
「寂しいときはいつでも来い、って約束してくれたじゃない――」
わたしは、密かに下された異端者抹殺の命を全うすべく、夜の闇の中を歩く他なかった。
――それも今はもう昔の話。あれから刻々と時は流れ、あの当時は想像もしなかった環境にいる。決して共に歩むことなどないと思った人と今は一緒にいるのだから。
「メリアドール? そんなところに居たら風邪ひくわよ?」
「あらアルマ。そうね、ちょっと夜風に当たりたくて。星を眺めているといろいろなことを思い出すの」
昔の事を思い出す。かつて共に過ごした人たちも今はもういなくなってしまった。寂しい。だのに、それを慰めてくれる人はいない。――寂しくなったらいつでもおいで。
「そう、約束してくれたじゃないの」
「何の約束?」
「ううん、昔の事よ。何でもない」
夜風が頬をさらっていく。さらさらと、静かに吹いている。やむことなく、さらさらと。
「わたしもね、こうして星空を見ているとあの時の事を思い出すわ。オーボンヌからさらわれたあの日のことを」
「その節は、どうもうちの弟が随分と迷惑を掛けたみたいね。ごめんなさいね。普段はあんな乱暴な子じゃないのよ」
「いきなり殴って気絶させられるなんて、初めての体験だったわ。あれはもう御免。でもいいの。別に恨んでないし、本当はわたし、誰かにここから連れ出してもらうのを心の底では待ってたの……」
「兄さんたちはみんな自分の道を自分で決めて、歩んで、すごくうらやましかった。なのにわたしは修道院と、学校との往復。そのうちお嫁にいって、跡継ぎを作る。そんな道しかなかったから。いつかこんな狭い世界からわたしをさらってくれるような騎士様を待ち望んでたの。本の読み過ぎかしら。――でも、本当に来てくれた」
アルマは静かに語っていた。夜の暗さから、表情は見えない。
「イズルードと二人で、チョコボに載って、満天の星空の下を走ってた。行き先も教えてくれないかったから、わたしはこれからどうなるのかも分からなくて、でも全然怖くはなかった。あんな真夜中に、森の中を走ってるんだから、今思い返すと不思議なことね。」
「でもさすがに、ラムザ兄さんと引き離されて、その時のわたしはとても機嫌が悪かったから、わたしは不満ばかり言ってて、困ったイズルードがこう言ったの」
――オレがあの天の星を一つもいできてやる。だから機嫌を直せ。
アルマは静かに語る。声は柔らかく、暖かかった。
「あらやだ、イズったらそんな恥ずかしいことを」
「ふふ、わたしがあんまり怒っていたから困ったんでしょうね。一生懸命、わたしをなだめようとしてくれたもの」
「あの子は、女の子の機嫌を取る方法なんて知らないから……」
「わたしはその時思ったの、この人と一緒に行ってもいいかな、って。安心したの。でも、もういないのね。とてもさみしい、わ。」
昔の事は今でも手に取るように思い出せる。思い出せるのに、今はもういないなんて。
寂しい。隣にアルマがいるはずなのに、まるでたった一人夜に取り残されてしまったようで、誰かにぎゅっと抱きしめてもらいたかった。あの頃のように、「ここにいるよ」と言ってもらいたかった。
その時、アルマが寄りかかってきた。ふわり、と柔らかな髪が背の上でゆらめいた。
「でもね、イズルードはちゃんと約束を守ってくれたのよ。ほら、ちゃんとわたしに天上の星をもってきてくれたのよ」
アルマが聖石を取り出した。愛おしそうに撫で、唇をそっと持っていった。
「聖石は天からの授かり物、ね。そんなことをゾディアックブレイブに任命された時云われたわね」
「どんな星より綺麗な石の中の石。天から持ってきてくれたみたい。わたしの宝物。……本当に、星を取って、天から切り離せたらよかったのに。そうしたら運命だって止められたのに。でも、わたしは幸せよ。ああして、ほんの一瞬だけでも一緒に過ごせたのだから。ひとときでも心通わせた大切な人なの」
アルマの小さな身体が触れた。暖かかった。とても幸せそうだった。ちらりと見えた横顔には幸福の表情があった。その顔は、恋する乙女そのもの。
誰も知らない、二人だけの秘密。それはそれは密やかな、ささやかな恋。そう、あれは私の初めての恋だったのだ。
そう、イズルード、恋をしていたのね。わたしの知らないうちに、随分と大きくなったのね。
見上げた夜空には、粛々と星が輝いている。あと数刻もすれば夜が明けるだろう。目を閉じて、草むらに横になった。
星空の彼方、上のほうから「ここにいるよ」と声が聞こえたような気がした。