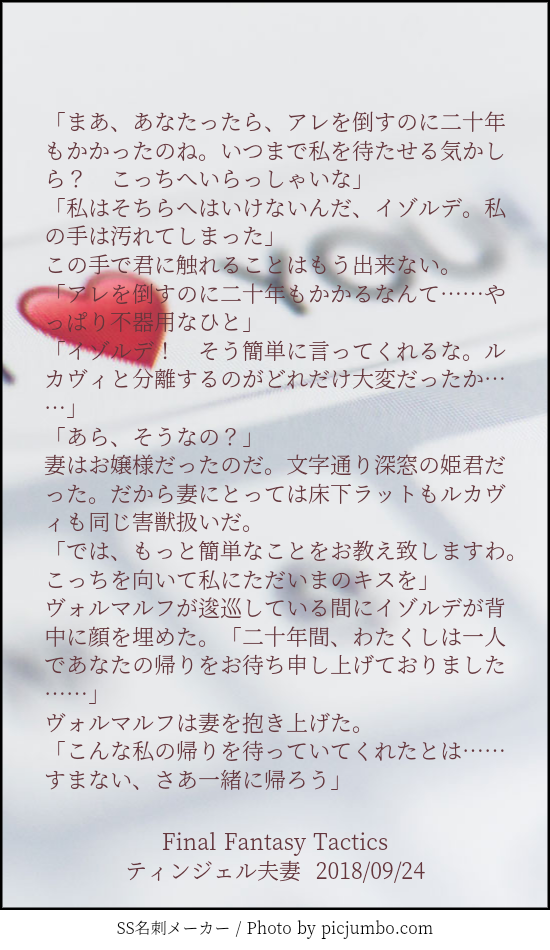.
輝く日を仰いで
メリアドールは私の娘だった。もちろん、私は彼女の父親ではない。
父親は死んだのだ。
娘と息子二人を残して。幼い子供らを庇護できるのは私しかいなかった。否、私にしかできないと思った。
「ウォドリングおじさん」
彼女ははじめ、私のことをそう呼んだ。だが、いつしか時は流れ、私のことを名前で呼んでくれるようになった。屈託のない笑顔と一緒に。
私は父親。彼女は誰より大切な私の娘。
その日は突然にやってきた。
「こんど騎士団に来る人、アカデミーの首席だった人なんですって。ローファル知ってる?」
メリアドールはルザリアから来る士官に興味津々な様子だった。私が何と答えたかは記憶にない。
都会から来る士官学生がろくな奴であった試しはない、のだが――鳶色の髪のすらりとした背格好の青年が年頃の娘の気を引かない訳がない。
私は心配だった。愛する娘が、野心あふれる若者にもてあそばれるのではないかと気に病んでいた。だが、彼女の口から「クレティアン、クレティアン」と若き士官の名前がこぼれるのを聞いて、私は諦めた。
私は父親であり彼女は娘だった。そこに彼が加わっただけのこと。家族が二人から三人になっただけのことだ。
「私はメリアドールには手を出すなと何度も言った。なのにおまえは私の話を全く無視したな、クレティアン」
「手は出していない……ああ、信じてないって顔だな。だが誓ってもいい。私は誠実であり、彼女は気高く清純だ。騎士の誓いを破ったことは一度もない」
「そうか……おまえがそう言うのなら、そうなのだろうな」
「それにしてもひどいな。なぜ私がメリアドールに手を出すなどと思ったのだ」
「野心ある若者がよくやることだ」
「私をそのような下卑な連中と一緒にしないでくれ。私が彼女の手を借りなければ出世できないような俗人に見えるか」
「ああ、そうだったな」
5年、10年と一緒に暮らして過ごせば相手の性格は分かるようになるものだ。今や私は副団長。彼は参謀。良きパートナーであった。
「しかしローファル。はっきり言うぞ。おまえのメリアドールへの執着は異常だ。なぜ父親でもないおまえが、彼女をそこまで庇うのだ」
「私が父親なんだ」
「ほう。私の頭がいかれてなければ、彼女の父である騎士団長殿は存命だ」
「死んだんだよ。おまえがミュロンドに来るよりずっと前にな。そう……あれは不幸な事故だった。ヴォルマルフ様は魂を悪魔に喰われて死んだ。だから私は誓った。幼い子供たちを死んだ父親に代わって守り抜くと」
「――そうだったのか」
「信じるのか? こんな荒唐無稽な話を。私が狂っているとは思わないのか」
「おまえがそう言うのなら、それが真実なのだろう。私はおまえを信じるよ、ローファル」
普通ではない。これは普通の家族ではない。本当は家族でもない。分かっていたことだ。いつか彼女が真相を知った時、この家族ははかなく消え去ってしまうことを。
輝かしい思い出だけを残して。
団長が死都に向かうと言った。私は何も言わずについて行った。メリアドールはとうに私の手を離れていた。私の役目は終えたのだ。あとは見届けるだけだった。
しかしこれだけは予想もしていなかった。まさかメリアドールが自らの手で終焉をもたらすとは。
その剣を振り下ろすまでに、彼女はいったいどれほど涙を流したのだろうか。私には決して分からない。分かってあげられない。それがどれほど悔しいのかも、彼女に分かってもらえない。
「……クレティアン、待っていてくれたんだな……」
身体中の力が抜けていくのが分かる。身も心もぼろぼろだった。修道院の深淵の、暗い、暗い、廃墟の街。こんなところで自分を待っていてくれる人がいるとは。
「ローファル、おまえが来るのを待っていたんだ。だって、もうおまえしかいないじゃないか……あの日々のことを覚えているのは」
そうだった。あの懐かしい日々。彼女と過ごしたあの日々。もう決して戻ってこないあの輝かしい日々。
「……ローファル、一つ言っておくことがある。私は約束を果たしたぞ……彼女には指一本触れなかった。彼女は尊く清らかだ。実のところ、私は彼女に感謝しているのだ。こんな状況になっても、な……。彼女を思えばこそ、こんな汚れた地獄の世界のまっただ中でも正気を失わずに生きてこられた。この想いを、ローファル、おまえに、伝えておきたかった……」
息も途切れ途切れに、それはほとんど愛の告白だった。
「なぜ私に?」
「いつか言っただろう、おまえが彼女の父親だったと」
「ああ……」
そうだ。私が父親だったなら、愛する娘に向けられたこの上ない讃辞を涙なしには聞けなかっただろう。私が父親だったなら……
「その言葉、たしかに受け取ったぞ。だが、真にその言葉を受け取るべき人は私じゃない」
私の返事を聞くことなく彼は力尽きたようだった。そっと彼の身体を抱き寄せた。
「よく頑張ったな……おまえに会わせたい人がいる。さあ、これから一緒に会いに行こう――」
――ヴォルマルフ様、あなたの誇り高い魂に誓って、彼女をこの命に代えても守り抜くと誓います。
はるか彼方。遠い昔の誓いの言葉。
この誓いは果たされた。私は為すべきことを為した。
家族は遠く離れてしまった。子供たちはもう二度と私の元へ戻ってはこないだろう。私のこの血に汚れた手で抱きあげることもかなわないだろう。
息子よ、娘よ。
彼らは死んだ父親に何を言うのだろうか。せめて叱責してくれようものなら赦しを請うこともできるのだが。
「ヴォルマルフ様」
聞き慣れた二人の男の声。振り返らずとも誰に呼ばれているのか分かる。私の忠実な部下たち。
「おまえたちか」
やはり来てくれたのか、と安堵する。しかし、やはり来てしまったのか、とも思う。ここまで忠義を尽くす必要もなかっただろうに。<統制者>である私に。
「ヴォルマルフ様……やっと……お会いできました。私はあなたに、<統制者>に代わって死んだ<本当の>あなたに会える日を楽しみに、ここまで生きてきたのです」とローファル。
後ろを振り返ると、そこにはクレティアンに寄り添ったローファルの姿があった。そうだ、この二人はいつも一緒だった。互いに支え合う二人の姿。そんな日常が毎日だった昔に戻ったようで微笑ましい。
ここまで来て、やっとあなたに会えました、と震える声を絞り出すローファル。私はそんなにも慕われていたのか。
「ローファル。さぞ憎かったことだろう、私を殺した<統制者>のことが。剣を向けてもよかったのだぞ。私の娘がそうしたように」
「いいえ……それだけはできませんでした。たとえ魂は離れようと、その身体はあなたのもの。私が剣を向けることなどできませぬ」
「そうか、そうか。ならば私はその忠節に応えてやらねばならないな……だが、私はもはや何もかもを失った身。家族にすら見放された私に何ができようか」
私は息子に手をかけた。その報いを娘の手により受けた。愛する家族にすら何もしてやれなかったのだ。
「ヴォルマルフ様、私たちは何も望みません。騎士団の仲間と過ごしたあの日々は、楽しく、輝かしいものでした。その思い出だけで私たちは十分なのです」
「ローファル、クレティアン。おまえたちは特に娘の面倒をよく見てくれていたな」
「ええ、それはとても」
と、二人そろって笑い合った。その談笑の輪に私は入れない。私は娘に父と呼んでもらえない。私はあの子たちと家族になれなかった。だが、私の部下たちが――私の忠実な部下たちがあの子たちの家族となってくれた。
それだけで十分ではないか。
「ヴォルマルフ様。だから私たちは戻ってきたのです」
「……どういう意味だ?」
「私たちは、お嬢様とこの上なく楽しい日々を過ごしました。この、お嬢様との思い出を、父であるあなたに知ってもらいたいのです。だから、こうしてお返しにきました――あの輝かしい日々を」
「語り合いましょう、三人で。尽きせぬ時間があるのですから」
私、神殿騎士団団長のヴォルマルフ・ティンジェルは良き部下に恵まれた。心からそう思った。
輝ける日々
それは家族の記憶
私がいるはずだった家族の記憶
戻らぬ時を経て、懐かしき思い出は今や私の手の中に
いかなる喜びぞ