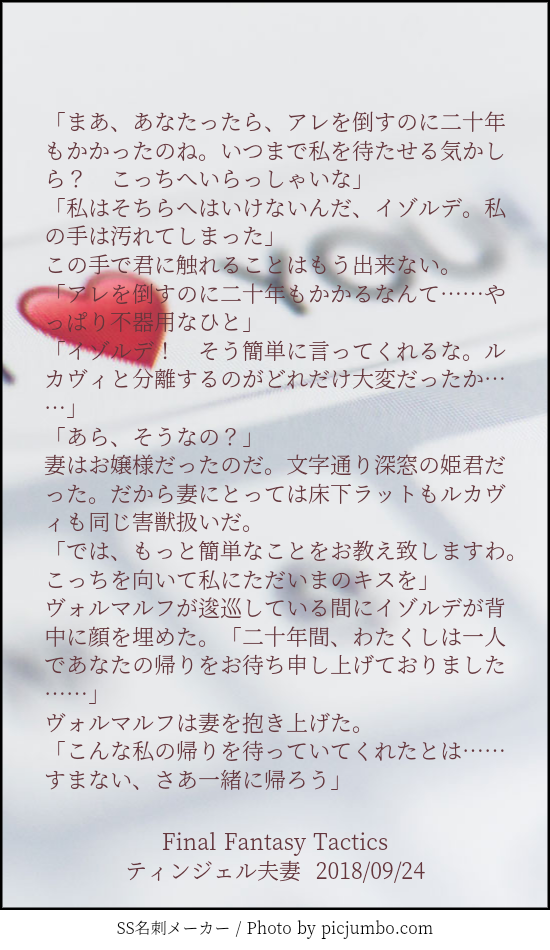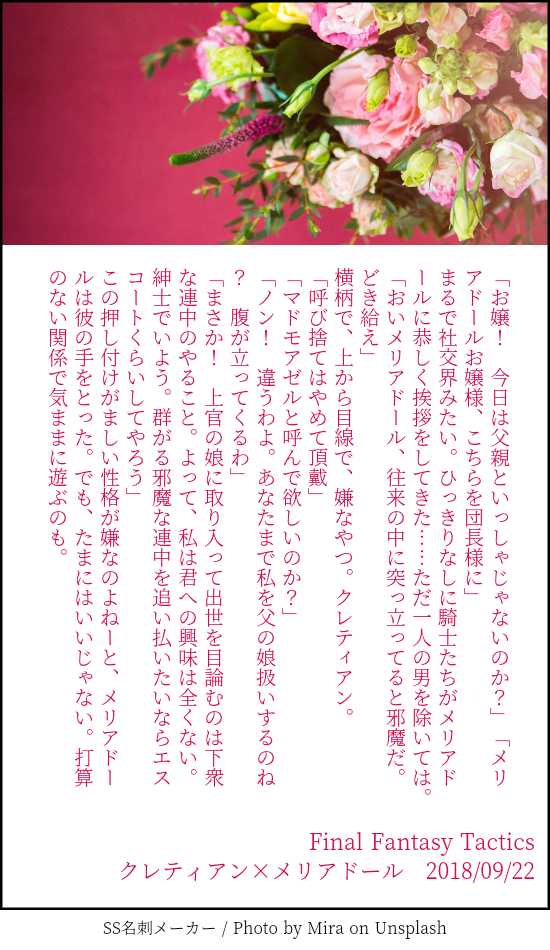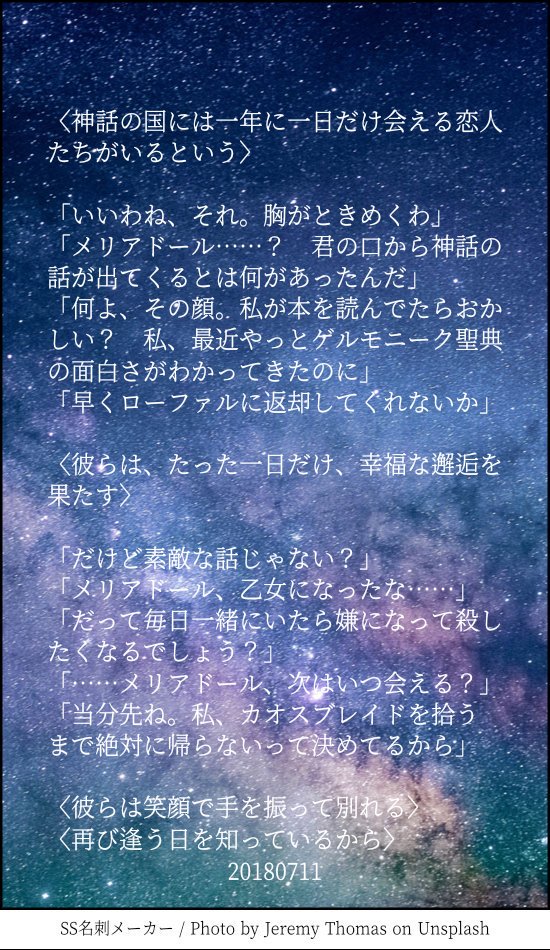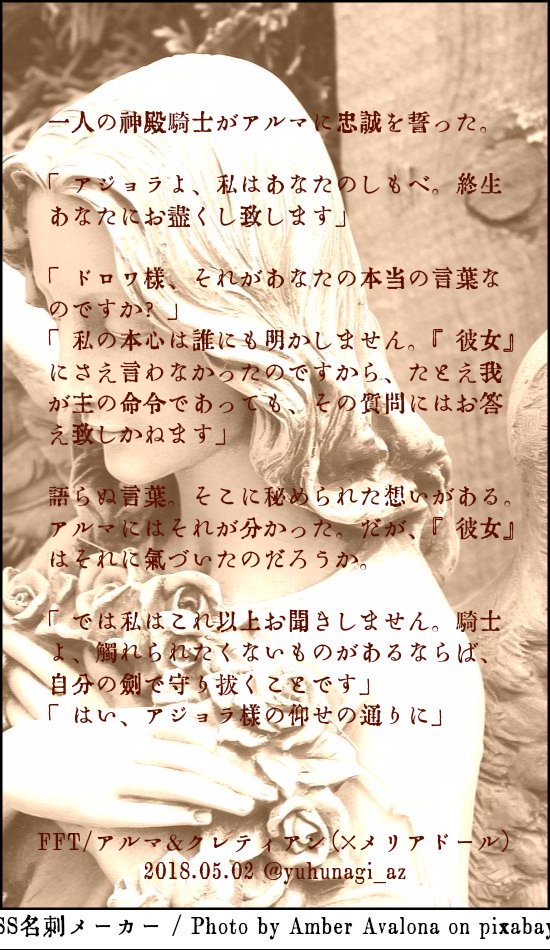.
・バルクさんお誕生日お祝い小説
・妻子持ちバルクさんがどうしようもないヘタレ父親です
・オリキャラ出てくるのでご注意
Return to my Home
彼はいつも首から銀のリングを下げている。漆黒の衣に鈍く輝く銀のきらめき。
「バルク隊長、アウトローだった時からそれ、大事にしてますよね」
ふと気になって尋ねたのは、長いあいだバルクと一緒に戦場を駆けめぐってきた、アイテム士のジェレミー。
「ああ? お守りみたいなもんだよ。気休めさ。持ってると気が安らぐのさ」
「見てもいいですか?」
ほらよ、とバルクは旧友にリングを放り投げた。ジェレミーは落とさないように大事に受けとると、その銀細工をしげしげと見つめた。
「中に文字が彫ってあるんですね」
「俺が彫金したんだ」
そういえば、隊長は昔ゴーグで機工士をしていたらしい。ジェレミーが出会った時はすでに貴族から恐れられる荒くれ者だったから、ゴーグで暮らしていたという昔のことは知らない。バルクも語ろうとしなかった。
「隊長、誘拐犯みたいな見た目だけど、意外と手先が器用ですよね。銃とかも自分で手入れしてますよね。職人みたいだ」
「ああ、職人だったんだよ。昔はな」
「ところで、これ、何て書いてあるんですか? 畏国の言葉じゃないみたいだ」
「ロマンダにいた頃に作ったからな。ここの言葉じゃねえや」
「へえ! 隊長、ロマンダ語もしゃべれるんですか? すごいや、読んでみてくださいよ」
バルクはかたく首を振った。「だめだ。それはかみさんへのプロポーズの言葉だ。アイツ以外に言うつもりはねぇ」
あ、とジェレミーは声を漏らした。妻への愛の言葉を胸元で大事に守る男。その意味を察してしまったのだ。これは形見の品に違いない。興味本位で軽々しくたずねてしまったことをジェレミーは後悔した。
「すみません。私としたことが……奥様の思い出、どうが大事にお持ちください」
ジェレミーは銀のリングを隊長にそっと返した。だが、当のバルクは怪訝そうな顔をしている。
「なんでえ、そんなしけた顔しやがって」
「だって、奥様がとの、悲しい別れを思い出して、さぞおつらいでしょう……」
「女房? ゴーグでピンピンしてるぜ。ガキもそろそろいい年になってるだろうよ」
「……え、えぇえ? なんですって?」
ジェレミーは思わず、真顔で聞き返した。「奥様はまだ健在? しかも子供までいる?」
「ああ。娘だか息子だか分からんが。15年以上帰ってねえし」
「で、なんであなたはここにいるんですか? 奥さんほったらかして。子供の面倒もみずに! あなたは男として、人間として最低だ」
「それがアウトローとして生きるさだめだ。俺は修羅の道で生きてきた。女房もそれは分かってる。俺はアウトローとして生きると決めた時、女房に言った。俺は死んだものと思えってな」
「隊長、ではどうして、奥様へのプロポーズの言葉が刻まれたリングを隊長が持ってるのですか。あ、ペアリングですか?」
「い、いや一品物……タイミングを逃して渡しそびれた……」
「はぁ~~隊長、想像以上にどうしようもない人ですね。そんなんっだったら、もうフェニ尾あげませんから」
「待て! それは困る! 俺はお前がいないと生きていけない! 頼む!」
バルクはあわててジェレミーにすがった。この有能なアイテム士は、どんな障害物をもかわしてバルクにフェニ尾を投げつけてくる凄腕の戦友なのだ。
「だったら、奥様にちゃんとプロポーズしてきてください。私は腑抜けと一緒に戦う気はありませんからね。私、団長に隊長の休暇願いを申し立ててきます」
さっさと踵を返して立ち去るジェレミーをバルクは呼び止めた。だが、もう時すでに遅し。ジェレミーはすでにその場を去っていった。
「おいおい、今更求婚なんてこっぱずかしいことできるかよ。だいたい団長がそんなふざけた休暇願いを聞き入れるはずがねぇだろうよ……」
「団長OKです」
「話がはえーよ」
ジェレミーが鉄砲玉のように飛び出していってから5分も経たず、風呂敷包みを持って現れた副団長。
「我が神殿騎士団は礼節を重んじる騎士団。団員のご家族に挨拶をさしあげるのも長の仕事……といいたいところですが団長はご多忙の身ゆえ、私がともに参ろう。あ、これは手土産のミュロンド饅頭と銘菓あじょら餅」
「いらん世話は焼かないでいいっての」
バルクは風呂敷包みをひったくった。よりにもよってこいつと一緒に里帰りかよ。いつもフードを目深にかぶり、素性を隠し通す仏頂面の副団長。
「おい、もうちょっとマシな顔はできねぇのか。俺のかみさんはな、生まれたゴーグの町から一歩も外に出たことがない女なんだ。暗黒司祭みてえな奴が家に上がってきたら気絶するわ」
「大丈夫ですよ。ご婦人へのマナーはわきまえておりますから」
そういってローファルは、さっとフードを下ろした。トンスラの金髪が風になびく。顔には穏やかな僧侶の微笑みをたたえている。営業用スマイルだ。こいつも黙ってこうして立ってれば可愛い奴なのにな。
「バルク、あの子は連れて行かないのですか? あなたのことを随分と慕っているようですが」
「ジェイミーか? あいつは留守番だ。アウトロー時代を知ってる奴に、家庭のことは見せたくねえんだ……気まずいだけだろ」
バルクはため息をついた。ローファル、おまえもだ。できればこいつも置いていきたい。言外の意味をこめてローファルをじっとにらむ。だが帰ってきたのは副団長の圧だった。しかたねぇな。
「あ、おじちゃん、ゴーグに帰るってほんと?」
「嬢、どした」
ゴーグ行きの船に乗るため、まとめた荷物を持ち上げようとしたら、荷物のすきまに嬢ちゃんがすかさず滑り込んできた。バルクはじゃれついてくるメリアドールを引き剥がし、ローファルに押し付けた。子供の扱い方はどうも難しい。
「待って、おじちゃん!」ローファルの背の影からメリアドールはバルクに呼びかけた。「お・み・や・げ」
「はいはい」
しかたねぇな。何か買ってきてやるよ。
「あんたァ、この20年どこほっつき歩いてたんだね」
「ルツ……」
覚悟はしていた。扉を開けたら、不審者が入ってきたと鍋で撃退されるかもしれない。20年も家に帰らなかった男はもう死んだも同然だ。新しい夫が、女房の隣に座っているかもしれない。俺の女に手をを出すなと狙撃されるかもしれない。そんな心配が家に帰る間中ずっと頭を離れなかった。
杞憂だった。女房は健在だった。思ったよりずっと老けていたが。俺だって老けた。もうおじさんだ。
「覚えているかい、この俺のことを……」
「なんだい、その情けない顔は。あたしは、あんたの子を20年も育ててきたんだ。どうして忘れるんだい」
よかった。扉を開けて鍋でぶっ叩かれたのでは隣にいる副団長に永久に失笑される。それだけは避けたかった。
「ご挨拶が遅れてすみません」ローファルが一歩前に進みでる。「わたくしは神殿騎士団副長のローファル・ウォドリングと申すもの。ご主人を長らくお借りしており申し訳ございません、マダム・フェンゾル」
「あたしはマダムなんてたいそうなものじゃ……」
威勢のいいゴーグの職人街で育ったマダム・ルツ・フェンゾルは神殿騎士の挨拶にぎょっとした。ここでは彼女のことをマダムなんて呼ぶ者はいないのだから。ルツよ、こいつは俺以上に腹の黒い坊主だぜ。口に出しては言わなかったが。
ルツはバルクに小声でささやいた。「この坊さんは誰だい。あんたがさらってきたのかい? あんたはまだ誘拐犯みたいなことをやってるのかい? うちには教会のお偉いさんに払う金なんてないよ」
「俺の仲間だよ。俺は教会の騎士になったんだ」
「冗談はおよし!」
ルツはバルクの背中をバンバンと叩いた。「信じられない!」と豪快に笑っている。
ああ、俺も信じられない。俺が騎士だって。死んだ親父も驚いて墓から出てくるだろうよ。だが、事実なんだ。
「彼の言っていることは本当ですよ。マダム。彼の身元は私が保証します。私たちは教皇の勅命を受けて、この国の未来を作るために戦っているのです。彼は私たちに随分と尽くしてくださいます。彼の働きには、とても感謝しているのです」
では、私はこのあたりで。あとは夫婦水入らずでどうぞ、と気を使って退出する。ルツはまだ目を丸くしている。バルクはどうやって話をまとめればよいのか分からない。あ、そういや土産を持ってきてたな……「ほらよ、ミュロンド銘菓あじょら餅。食おうぜ」
「へぇ、神殿騎士団ね。国を壊してくるぜ、って息巻いて郷を出てったあんたが教会の騎士ねぇ……」
「国家に縛られたくないとアウトローになった俺が今や教会の犬だ。笑えるだろう。なあ」
「いや、あたしは難しいことはわかんないよ。あんたが生きててくれただけで嬉しいさあ。……だけど、ゴーグの隣で暮らしてんならもうちっと早めにけえってきて欲しかったさね。子育ても終わっちまった後に戻ってくるたあ、どんな父親だい」
「はい、ごもっともで……めんもくもない……」
あじょら餅の包みを広げて満足そうにほうばる女房の前バルクは静かになっていた。何も言い返せない。使いこまれたぼろぼろの食卓に座る、少し気まずい雰囲気の夫婦。バルクの右手には銀細工が握られている。いまだ、渡そう、いやまだだ、渡せない。気持ちが逡巡する。
「ルツ……」
「なんだい」
「いや、なんでもない……」
「ちょっと! はっきりしなさいよ!」
言えなかったプロポーズを。やっぱり郷を出る前に言っておけばよかった。畜生、失敗したな。
ルツとはゴーグの幼馴染だった。いつも一緒にいるのが当然だったから、プロポーズなんてこともなく夫婦の契りを交わし、連れ添うように一緒に暮らしはじめた。バルクにとって、己の命より大事な妻だった。だから、ゴーグを出てアウトローとして生きる決意をしたときは妻を巻き込むまいと、心に決めていた。彼女はゴーグの職人街でそだった善良な街娘。法を飛び越えて夜を渡り歩くアウトローの生き方を押し付けるつもりはさらさらなかった。
だからこう言ったのだ。
――俺は死んだものと思え。
テロリストの妻なんて肩書きを与えたくなかった。俺のことなんか忘れて幸せになれよ。そう言ったつもりだった。だが、妻は帰らぬ夫のことを待っていた。子供まで育てて。
俺、くそ野郎じゃねえか。新妻にプロポーズもせず、死亡宣告だけして家出同然に失踪して、20年も戻らなかった。夫のいない家で一人、子供を育てる妻がどんなに寂しかっただろうか……畜生、畜生。俺は父親になれなかった男だ。夫にすらなれなかった。
ゴーグを出てロマンダに渡ってすぐにガキが生まれた、という手紙はもらった。その時は郷に帰ろうと思った。だが、その時は戦争中で、必死に密航したロマンダからゴーグに飛んで帰るのは至難の業だった。だから、旅先でかき集めた金で、記念にちょっと洒落た銀のリングを作って、戻ったらちゃんと渡そうと思っていた。だが、アウトローの人生は波乱に満ちていた。3年、5年、10年、と時間が過ぎ、郷に帰るタイミングをずるずると失った。
怖くて帰れなかったのだ。妻に見捨てられていそうで。
「あんたは昔から怖いもの知らずの荒くれだったからね。ちゃんと、その、教会の騎士ってやつはうまくいくのかい。教皇さまと一緒に暮らしてるんだろ?」
怖いもの知らず? いや、俺はただの臆病者だ。20年も郷に帰れなかった小心者。
「まあな。騎士団には俺よりやばい連中がうじゃうじゃいるさ」
騎士団。嬢のことを思い出した。ゴーグ土産、何にすっかな。ああ、そうだ。嬢といえば、俺のガキはどこだ。
「ルツ、あの、その……おまえの子はどこだ?」
「腰が低いねぇ、あんたの子って言えばいいのに」
マイスターのギルドで徒弟修業中だよ、会いに行くかい、とルツに言われた。バルクはうなづいた。ああ、もちろん。だが怖い。やっぱり怖い。女房はともかく、一度も会ったことのないちびに何面で会えばいいのか。父親ではないな。通りがかりのおじさん顔をしておこう。
案内されたのはゴーグで一番広い工房。機工士として少年時代を過ごしたバルクはこの建物が誰のギルドなのかすぐにわかる。マイスター・ベスロディオ・ブナンザ。
「ほら」建物の窓越しにルツが指差す。
「おお、俺の子にしては随分イケメンじゃないか。人のよさそうな顔をしている」
「ちょっと! どこを見てるんだい。あれはマイスターの坊ちゃんだよ。いつフェンゾルの家に金髪がまじったんだい。うちの子はあっち」
ルツの渾身の突っ込みで背中をバシバシと叩かれた。「わかってるって、冗談だよ」
工房の隅で、粘土板に製図器を使って図面を書いている。小さな粘土板に描かれたのは一部分だが、バルクにはその機械がすぐに分かった。飛空艇だ。間違いない、あいつは機工士になる。間違ってもテロリストとして逃亡生活を送る人間にはならない。ほっとした。これは父親心だろうか。
「坊主」
バルクは窓から身を乗り出して石壁をトントンと叩いた。黒髪の少年が振り向く。ルツにそっくりだ。人相の悪い俺に似なくてよかったな。
「おじさん、誰」
「おじさんは通りすがりの騎士だ」
少年はあからさまに興味なさそうな顔をした。自分の図面に戻って没頭したいという雰囲気をかもし出している。
「坊主、機工士になるんだろ」
「うん。マイスターみたいになりたい」
「頑張れよ」
「うん」
数秒で終わってしまった会話。少しものさびしいが、まあ、失踪してた父親がいきなり出てきたと説明するのも難儀だし。マイスターのギルドにいるのなら、まっとうな機工士になるだろう。それでいいさ。
「あんた……もうちっと顔をみてったら」
「いいよ。怖い顔のおじさんに見つめられても不気味なだけだろう――さ、ちびの顔も見たし、俺はミュロンドに帰るよ。副団長を待たせてるのも悪いし」
今だ。去り際にかっこよく。「これ」銀の指輪を渡すのだ。「結婚の記念に渡そうと思ってた」待たせてごめんな。「ロマンダで作ったんだ」ちょっとかっこつけたかった。渡し忘れたせいで台無しになったが。
「あら、あんたにそんな気遣いができるとはね。愛の言葉でもくれるのかい」
バルクは苦笑した。
「あいにく、俺はそういうの得意じゃないんだ。だからかわりに指輪に書いておいた」
「あたしは目も悪いし、字もよめねえんだ。かわりに言っておくれ」
バルクは戸惑った。言うのか。愛の言葉を。俺に言う資格があるのか。言えるのか。
「……誰にも言うなよ、これは妻にしか言わないって決めてるからな」
やっと言うのだ。妻に20年越しのプロポーズを。
「へたくそ」
ミュロンドへ戻る船の上でローファルがぼそりとつぶやいた。
「あんだよ。夫婦水入らずで、とか言ってつけてんじゃねえよ」
「失礼な。私は護衛していただけです。あなたは自分の立場をわきまえた方がいい。どうして国家指名手配犯のあなたが、この数時間で誰にも狙撃されずに街中を歩けたと思います?」
ローファルは黒の僧服の袖口からするりとこぶりの長剣を取り出した。
「今日だけで何人始末したとお思いですか」
「ふん……いらん世話は焼くなって言ったろ……」
相変わらず物騒なやつだ。涼しい顔して、プロのアサシン顔負けの始末術を持っている。
「しかしあなたははどうしようもない父親ですね。息子の名前さえ聞かなかった。奥様はさぞがっかりしているでしょう」
「……聞いたら、情が移るだろうが。これでいいんだよ。騎士になったっていっても俺は影の住人だ。中途半端に父親面したくねぇんだよ」
「あなたは臆病者だ。ただ逃げているだけ。生きている家族が目の前にいるというのに、あなたは逃げ出した。あなたはいつか後悔する。生きているその手を自ら手放したことを」
「説教はよせよ。俺は自分で決めたことに後悔はしない」
「いいえ、あなたは後悔する。ヴォルマルフ様や私がそうであったように……」
ああ、団長も細君と死別してたんだっけな。副団長もか。ん、副団長? こいつもか?
「ローファル、あんたもか? あんた修道士だろ。結婚してないよな……?」
ローファルはふいと顔を背けた。そしてぼそりとつぶやいた。「私は孤児だった。父の名もしらず、誰に抱かれた記憶もない」
めったに心を開かない副団長がはじめて自分の過去を語っている。「そうか、あんたは寂しかったんだな……そうだ、なら俺がパパになって抱いてやるよ。今からでも遅くない。ほら、膝の上、あいてるぜ――痛ぇ!」
すばやい平手うち。さすが始末人。目にも留まらぬ右手の動き。しかも、おまえ、服の下に鎖帷子着てるだろう。痛ぇンだよ。
「わ、わたしのことではない。おまえの子の心配をしているのだ!」
「あーはいはい、どうせ俺は父親失格の人間だ。今更父親なんて無理だっての……まあ、練習したらいいパパになれるかもな。帰ったら嬢を借りるぜ。まずは抱っこの練習から――」
「隊長! 戻ってきたんですね。あれ、夫婦喧嘩でもしましたか?」
港で出迎えてくれたのは相棒ジェレミー。こいつとは勝手知ったる仲なので、挨拶代わりにポーションを投げつけてくる。ありがてぇ。副団長にはたかれた痕に寸分の狂いもなく塗り薬が炸裂する。
「いや、これは同士討ちだ。副団長の機嫌が悪かった。乱闘になった」
「どうせ隊長が失礼なこと言ったからでしょう。バルク隊長、空気よめないから……」
「うるせぇな」
アイテム袋をごそごそとあさりながらジェレミーが言った。
「奥様にちゃんとプロポーズしてきましたか?」
「ああ」指輪は渡したし。
「お子様にもちゃんと会ってきましたか?」
「ああ」窓越しに。通りすがりのおじさんとして。
「なら、今回の里帰りは大成功ですね! よかった。私、心配してたんですよ。20年も帰らなかった夫を見て妻が逆上して死闘になるんじゃないかって。ほら、フェニ尾、こんなに買って準備してたんですよ」
「ありがとよ。でも俺のかみさんは優しいから必要ねぇよ」
「そうですね、隊長よく死にかけてますよね。でも大丈夫ですよ、ストックが99本ありますから」
バルクはジェレミーをこづいた。「バーロー、俺は不死身だ。フェニ尾なんて捨てちまえ。妻子を残してそう簡単に死ねないからな」