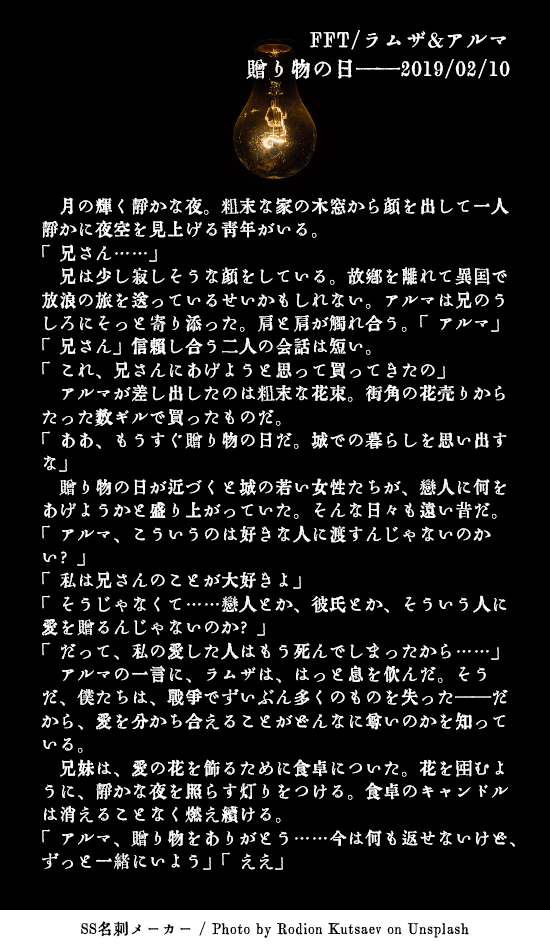.
誇りを失った騎士
第二幕
第一場 オーボンヌ修道院。僧房。
修道院院長の生活する一室。机と書架があり、部屋の片隅には祭壇も設けられている。部屋に飾りはないが、本が散乱している。修道院は神殿騎士の襲撃を受けており、外は騒然としている。叫び声、剣戟の音など。扉の向こうから、院長を呼ぶ声が上がる。シモン、それには答えず、部屋に留まる。
シモン (独白)修道院で血を流すとはなんという狼藉! 神殿騎士団! とうとう飼い主への礼儀を忘れたか! わきまえ知らぬ犬どもめ! おまえたちが剣を持っているのは何のためだ! 誰のために剣を持っている! 教会の騎士が、修道院の信徒を襲うとは、なんという過ぎたことを! おまえたちを騎士に叙して、その贅沢な暮らしを支えているのはこの教会だというのに! この報いは心してうけるがよい、世を知らぬ若き騎士どもよ――
(扉の外から、シモンを呼ぶ声)
シモン (答えて)ああ、分かっている。私は大丈夫だ。だから落ち着いて行動するよう皆に伝えなさいだ。何!? 地下書庫への扉が破られたと! ――ああ、なんということだ! あの書庫が――とうとう私の手を離れて、あの横柄を捌く犬どもに踏み荒らされるとは! (泣き崩れる)――あそこには私の全ての生涯が詰まっている。私はあらゆる手を使って――たとえ信仰を棄てようとも――あの書庫を守り抜いてきた。あの書庫はそれだけの、命を捧げる価値があったのだ。私は己の信仰と良心を犠牲にした。そうして私はあの幻の聖典を我が手にしたのだ! 若き騎士らよ、おまえたちにその価値が分かるか!? ――到底、分かるまいな! 何に価値があるかも分からず、知ろうともせず、ただ命令に従うことしか出来ない哀れな盲目の騎士たちよ! だからいつまで経っても教会の犬と揶揄され続け、信頼を回復出来ぬのだ。犬畜生め! とっとと書庫から出て行け! 誰がおまえ達にこのような野蛮な命令を下した? あの貪欲卑賤なあの王[教皇]か? いいや、それとも、こう卑劣な襲撃を考えるのはむしろあのミュロンドの騎士団長のやりかねんこと――たしか名前は――
(扉の外から、再びシモンを呼ぶ声)
シモン (答えて)大丈夫。ここはまだ安全だから――何、彼らは聖石を欲していると? (胸をなで下ろして)そうか、聖典を狙っているのではないのか、それは安心した――(慌てて否定して)ならん! 処女宮のクリスタルは王家から信頼の証として預かり申しているもの。そう簡単に手放す訳にはいくまい。聖石は渡せぬと、彼らにたしかに伝えなさい! ――そうだ、思い出したぞ。あの騎士団長の名前はヴォルマルフ! なかなかのやり手と聞いたが、たしかにそうだ。あの腐りきった神殿騎士団を、新生ゾディアックブレイブと呼ばせるまでに、信頼を勝ち得たのだから、相当な手腕だ。まごう事なき獅子だ。私も異端審問官だった頃はなかなかに名を馳せていたが、あの熟練の老騎士にはかなわぬな――それにしても、聖典でなく、ゾディアックストーンを欲するとは――それもそうか、あのクリスタルは、神の奇跡を起こす神器、いや、悪魔の依り代――いやいや、私にはそんなことは、どちらでも良い。どちらにせよ、一個の聖石は一個の騎士団に相当する戦力。子飼いの騎士らに真っ先に聖石を盗ませるのは、手っ取り早い、堅実な戦略だな。だが聖石の真価は――(間)――
(シモン、その場で腕を組んで考え込む)
シモン (続けて)――聖石の真価は、何もその秘められた力にだけあるのではない。誰も気付いていないだろうが――況んやあの若き騎士らは――クリスタルの価値はその知の集積にこそ宿るもの。あれが神器と呼ばれるのは、そこに死者の魂が宿るから。魂を宿した器なのだ。代々の魂が積み重ねられたものだ。すなわちそれは歴史そのもの! (吟じて)戦士は剣を取り胸に一つの石を抱く、消えゆく記憶をその剣に刻み、鍛えた技をその石に託す。物語は剣より語られ、石に継がれる――古えの言い伝えの通りだ。クリスタルは歴史を物語る。人の世は短く、人の言葉は少ない。歴史を記す書物はいつ燃やされ、葬られるか分からぬ。為政者に都合良く書き換えられ、真実は何も残らない。だが、クリスタルに宿る技は偽りを語らぬ。その魂は受け継がれるべきもの。石に刻まれた名前は永遠不滅。私は、歴史の真実を追究するために――この生涯を、この地下書庫に託してきた――書庫! ああ私の魂!
(シモン、立ち上がり、扉を開けて部屋を出ようとする。数人の修道僧が留まるよう説得するが、振り切って出て行く。外では悲鳴と怒声が響く)
第二場 オーボンヌ修道院。地下書庫入り口。
夜。修道院附属の来歴ある書庫の入口。石造りの堅牢な建物。天井はなだらかなヴォールトで組まれている。部屋の内部は書架で複雑に仕切られている。奥に地下へ続く階段があるが、舞台からは見ることが出来ない。若い兄妹が暗闇の中を手探りで進む。 ラムザ、アルマ、シモン。
アルマ 兄さん。
ラムザ (返事をしない)
アルマ 兄さん、真っ暗で姿が見えないわ。どこにいるの。
ラムザ (返事をせずに、アルマの手を取る)
アルマ 兄さん――いいかげん返事をしてちょうだい! さては私に怒っているのね!(兄の手をふりほどく)
ラムザ 当然じゃないか! こんな危険な場所にわざわざ大事な妹を連れて来るのは馬鹿だけだ!
アルマ 兄さんは馬鹿じゃないわ。もっと馬鹿なだけね。まず、私がいなかったら異端者の兄さんは修道院に入れなかったわ。そんなことも忘れているのかしら。
ラムザ いいや、僕一人だって、どうにかして入れたはずだ。僕は今までもっとひどい戦地だって見てきたんだ。こんな場所に入るのはわけないさ。
アルマ つまり無理矢理侵入するつもりだったのね! それじゃあ、修道院の扉を壊して押し入った神殿騎士たちと大差ないわよ!
ラムザ アルマ! 僕は兄ろして心配しているんだ! 奴らは、修道院に何の躊躇もなく夜襲をかけるような卑怯者だ! もしも、アルマ、君が奴らに見つかったらと思うと――
アルマ 大丈夫よ。私だって、自分の身は自分で守れるわ。私は回復魔法だって使えるのよ。
ラムザ 奴らは、替え玉を使って、王女誘拐にだって介入しているくらい、小賢しい連中だ。どんな手を使ってくるか想像も出来ない。気を付けた方が良い。――アルマ、ところで、ここは一体どこなんだ。どうしてこうも道が複雑になっているんだ! ちっとも前に進めないじゃないか!
アルマ 修道院の書庫よ。もうずっと、何世紀も前からある立派な書庫。イヴァリースの歴史と哲学がここに収められているの。いつもここで写字生の人たちが本を作っているのよ。それはそれはたくさんの本があるんだから! ――そうね、道がこんなに入り組んでいるのは、きっと私達みたいな乱入者から書物を守るためね。
ラムザ あの神殿騎士たちからもだ!
アルマ いつもシモン先生はこの書庫に籠もっていらっしゃるの。先生は神学者としても素晴らしいなのよ。あまり人前には出てこない方だから、知らない人も多いだろうけれど。もっと公の場に出てきても良いと思うんだけれど、先生は謙虚なお方だから、ご自分の研究を誇ったりなさらいのよ。先生は今日もきっとこの書庫にいらっしゃるはずだわ。(呼びかけて)先生! シモン先生!
シモン ――アルマ様!
(シモン、書架にもたれて倒れている。兄妹、その声を聞きつけて駆け寄る)
ラムザ シモン殿!
アルマ 先生、しっかり! 今、人を呼んできますわ。
シモン いいや、結構。お嬢様のお手を煩わせる訳には――私は、書庫を守れなかった――彼らは階下へ行ってしまいました。アルマ様、彼らが戻ってくる前にお逃げ下さい。私は――守れなかった――だがしかし、この書庫で果てるのもまた本懐というもの。どうかこのまま逝かせてください――
ラムザ 奴らは既に地下へ行ったか! しかし、何故突然オーボンヌ修道院を――
シモン 彼らが欲しているのは、この修道院の宝である処女宮のクリスタルです。彼らは、何としてでもその聖石を奪っていくことでしょう。
ラムザ やはり! 神殿騎士団はあの悪魔の力を欲しているというのか! もし聖石が奴らの手に渡ってしまったら恐ろしいことになる! 何としてでも阻止しなければ――アルマ、シモン殿を頼んだ。僕は地下へ行く。
アルマ そんなことをしては駄目よ!
ラムザ (アルマに聖石を手渡す)もしもの時のために、この二つの聖石を預けておく。もし僕が戻ってこなければ必ずバグロスの海に捨てるんだ。いいな?
アルマ (聖石を受け取り、頷く)
シモン なんということを! ――聖石を――海に投げ捨てるとは――いけません!
アルマ 先生、もうしゃべらないで!
シモン それは数百年の叡智が詰まった宝玉。一度失われては、もう二度と――どうかそのようなことは――そして、あの、その偉大なる聖石を持ちながら、何も知らない哀れな若者たちに――どうか分からせてやってほしいのです――
ラムザ (アルマに)おまえはここに残れ。僕は奴らを追ってくる。(立ち去る)
アルマ 兄さん! こんな時に何もできないなんて――私も兄さんみたいに男に生まれたかった。そうしたら、私も兄さんと一緒に戦えるのに。兄さんを助けられるのに。
シモン どうか――
アルマ 先生! しっかり!
第三場 前場に同じ
シモン、その場に倒れている。瀕死。しばらくして修道服を纏ったローファルが現れる。
シモン (気配を感じて)誰だ、そこにいるのは――
(ローファル、静かに歩み寄る)
シモン (見上げて)おお、その格好は――見慣れぬ顔だが、ここの僧か。
ローファル いいえ、私はミュロンドの神殿騎士。
シモン この狼藉者め――私にとどめを刺しに来たか。
ローファル いいえ。そうではありません。けれど、私の兄弟たちが多大な騒乱を起こした模様。その非礼は詫びましょう。
シモン おまえたちが引き起こした騒動ではないか――僧侶を殺める罪の重さを認めなさい――
ローファル 私は、貴殿がかつて異端審問官として名を馳せていた事を存じております。たとえ手は下さずとも、あなたの命令によって数多の罪なき者どもが――もちろん、真正の魔女もいたはずですが――露と消えていったことでしょう。その数は、決して私どもが手を掛けてきた数と大差はないはず。むしろ、罪なき無垢の者を死に至らせることの方が罪は重いのですよ?
シモン この修道院の僧侶は罪を背負った者どもだと申すか。まあ良い。私が審問官だったのは事実だ。私が罪なき者を殺めてきたのも事実だ。だが、私がその罪によって地獄で焼かれるのは事実ではない――
ローファル それは存分なことで。傲慢と不敬も神の御前で裁かれる罪となりましょう。
シモン 神の断罪も地獄の業火も何するものぞ。信じるに値せぬものをどうして怖れることができようか。
ローファル ほう、オーボンヌ修道院長として、神学者としても名高いシモン・ペン・ラキシュ殿が無神論者だったとは意外な事実。いやはや、これはまったく驚きました。
シモン 今更、詮無きこと。
ローファル 斯様な立場の貴方が神を棄てるにいたったとは、これは深遠なる事情があるのでしょう。私も、礼儀を重んじる騎士ですから、その道程はあえて尋ねませぬ。
シモン いや、何、この立場だからこそ、信仰を見失ったのだ。(咳き込む)――私はもう長くない。何をしに参ったか見当も付かぬが、そこのミュロンドの騎士よ、この老いぼれにいつまでも付き合うことはない――早く――
ローファル 私は貴方に会いに来たのです。シモン先生。
シモン これは奇妙なことを――残念だが私に神殿騎士の知り合いはいない。疾く帰りもうせ。
ローファル 勿論、貴方は私のことを知らないでしょうが、私は貴方のことをよく存じ上げています。もう二十年も前になりますが、ここの修道院で働いていたのです。――この書庫で。
シモン (その言葉に反応し、わずかに顔を上げる)ほう――?
ローファル (地下の階段を見つめながら)下に行った者たちはどうせしばらくは上がってこないでしょうから、せっかくなので私の身の上話でもしましょう。私は、今こそ神殿騎士としてミュロンドに生活を見いだしていますが、元々はここの修道院の荘園の生まれ。家は農家でしたよ。耕せども耕せども、とても裕福とはいえず、両親は修道院へ納める租税にも苦労する始末。そして、税を免除してもらう代わりに末の息子を――私を――修道院に置いていったのです。
シモン 親兄弟に見捨てられた恨みか? それとも重税をしぼっていた修道院への当てつけか? だがそれは先代の修道院長に陳状すべき事柄。私のあずかり知ることではない――
ローファル いいえ、そのようなことは申しておりません。私は修道院に恨みを抱くどころか、感謝すらしているのです。何故なら、ここには食べる物と、寝る場所と、そして仕事がありましたから。私は、ここで天職に恵まれました。ここで、この書庫で、私は書物の書き写しをしていました。私はオーボンヌ修道院の写字生として、長いこと働いていたのです。そこで先生――貴方が長いことこの書庫に籠もって研究に打ち込んでいる様子も見てきました。あれは、随分と骨の掛かる研究だったようですね? 一体何をそんなに熱心に調べていらっしゃったんです?
シモン その真価は誰にも分かるまい。(再び咳き込む)いや、分かってたまるか――若造に――
ローファル (無視して)私はここで仕事をしている頃、ある噂を聞きました。この書庫は地下三階まで広がる広大な書庫。十二世紀にも及ぶイヴァリースの歴史と学問の蓄積が保存されているのだと。しかし、それだけの長い年月を経た書庫には曰くはつきもの。年若き筆写職人たちはこぞって噂話に高じていました。中には何世紀にもわたって秘匿されてきた禁書がこの書庫には隠されているとか、地下の最下層にはには広大な虚無の空間が広がっているとか、まあ、様々でしたね。書物は歴史を語る代物ですから、その歴史を受け継いできたこの書庫は幾代もの王が欲し、その度にここは陰謀に巻き込まれてきたと聞きます。
シモン おぬし、なかなか物分かりが良いようだな――
ローファル ええ、権謀術数の渦中とも言うべき――その意味はご判断に任せますが――ミュロンドで騎士団を率いて生き残る為には、物分かりが良くないといけませんから。馬鹿と阿呆と正直者は真っ先に消されます。私は馬鹿でも阿呆の類でもありません。
シモン しかし、こうもしぶとく生きているとは、正直者でもあるまい。
ローファル けれど、私は誠実に生きてきました。嘘は述べません。単刀直入に言いましょう。私はゲルモニーク聖典を探しています。二十年前、ここでその聖典の在ること無いこと、様々な噂が飛び交うのを聞いて育ちました。噂が出るからには火元があるはずです。その幻の聖典はここにあるはずです。貴方は、今更それを知らないとは、言いませんね――?
シモン あの神殿騎士らは、聖石を探しに――奪いに来たと聞いたが――
ローファル 勿論、聖石も探しています。ですが、それはあの子たちがすぐに回収するでしょう。我々は――少なくとも私は――聖石の真価を知っております。あれがただの権力の器ではないことを。我々が欲しているのは、権力でなく、その古代の叡智――誰かが知識を受け継ぎ、継承していかなければ、歴史は途絶えてしまいます。ご安心ください。我々は、その叡智を受け継ぎ、新たに歴史を築いていこうとしているだけのこと。修道院を襲撃させ、少々手荒い業となりましたが、こうでもしないと、王家は聖石を手放してはくれないでしょうから。
シモン (苦しげに)そ――それを聞いて――安心――した。クリスタルは継承すべきもの、しかし聖典は――何人たりとも、世に――出しては――
ローファル その聖典はどこにあるのです? 我々がその聖典を貴方に代わって守り抜きます。さあ――どこにあるのです?
シモン 地下に、ある――はずだ。だが、約束してくだされ、聖典を見つけたら、決して世に出さないと――必ず――(息絶える)
ローファル 騎士の誇りに誓って、約束しましょう――ゲルモニーク聖典を見つけ出し、必ずやそれを葬り去ると。(シモンに)ファーラム。汝は汝の欲する眠りを得よ。(立ち去る)
第四場 場所指定なし。
バルク、クレティアン。それぞれ技師、学者の格好に扮している。しばらくしてローファル登場。
バルク フォボハムくんだりまで行くのか。えらく遠いな。
クレティアン 何をしに行くのだろうか。
バルク そりゃあ決まってるだろ。城でお偉いさん方と話しをするためだ。
クレティアン お前はいつ諸侯と同席出来るほど偉い身分になったのだ? ヴォオルマルフ様が大公との歓談のため、リオファネス城へ行くのは自明の事。私がそんなことをわざわざ聞くと思うか。お前は少しは気を回し給え――お前がそんな気配りが出来ればの話だが。
バルク 悪いな。オレはおまえ如きに回すほど度量の広い気は持ち合わせていないんでね。だが、いくらミュロンドの神殿騎士団長とはいえ、わざわざ大公と話し込むことがあるのか。身分が違いすぎるだろう。
クレティアン その発言、とても団長直属の配下の忠臣の言葉とは思えないな。
バルク おっと、オレは騎士の忠誠を誓ったが、それは義務を忠実に果たすための言葉にすぎない。あの団長への忠義を果たす言葉ではないのさ。お前だって、あの男に忠誠を果たしている訳ではあるまい。
クレティアン 私は本当に信頼のおける者にしか頭を下げない主義なのさ。そうだな、たしかにヴォルマルフ様に心酔しきっているのはローファルくらいだろうな。彼のまめまめしさにはまったく頭が下がる。
バルク そのローファルはどこへ行った?
クレティアン オーボンヌへ寄ってから我々と合流すると言っていた。もうじき戻るのではないか。彼はどうやら新生ブレイブ達がきちんと仕事を遂行しているかが心配なようだ。大方、目付役だな。
バルク そうか、まだ戻らないか。ならここらで一杯酒でも浴びていくか――目付役が居ないうちに。
(戻ったローファル、バルクの後ろに歩み寄る)
ローファル (眉間に皺を寄せて)――お前達、うるさいぞ。何を騒いでいる。
クレティアン バルクが、フォボハムまで行くのは遠くて面倒だから私に酒を買ってこいと。
バルク (クレティアンに)言ってないだろうが! 含みのある要約だな! (ローファルに)わざわざオーボンヌ修道院で何をしていたんだ。
ローファル (バルクに)いいか、嫌ならこのまま貴様をバグロスの海に捨て置いても良いのだぞ、いいな? 修道院に何をしに行ったかだと? ――いや、たいした事ではない。彼らが無事聖石を見つけ仰せたか心配でな。しかし杞憂だったようだ。だがもう一つの宝は見つからなかった。あのゲル――(慌てて)おっと、何でも無い。
クレティアン (独りうなずいて)そうか、ゲルカニラス・バリンテン! 我々が、こうやって、神殿騎士の身分を隠して、ヴォルマルフ様と別隊でリオファネス城まで行けというのも理由あってのことだろう。秘密裏に行動せよというからには、決して公に出来ない仕事だろう。大凡の見当は付いたぞ。ゲルカニラス――あの大公を始末しに行くのだろう。
ローファル 向こうでの仕事は、城でヴォルマルフ様から直々に話があるはずだ。だからフォボハムまでの道中は気に揉まずとも良い。ただ己が身上を隠すことだけを考えるのだ。
バルク 団長の話を待たずとも、オレたちの仕事といえば要人始末以外にないだろ。
クレティアン 教会が表沙汰に出来ない仕事を担うのが我々の役目だからな。まあ、想像には難くない。
バルク 今度は大公の始末か。これは大物だ。腕が鳴るぜ。オレはゴーグでも名の通った凄腕の始末屋だったからな、良い獲物に出会うと血が沸き立つ。たまらねえ。
ローファル (無言で歩く)
クレティアン 凄腕の始末屋か。お前、足と腕しか狙えないだろう。(笑う)
バルク (言い返して)ここで心臓を狙ってやろうか、兄さんよ? お前が魔法をちんたらと一発撃ってる間に、オレは弾を六発撃てるぜ。
クレティアン 凄腕の始末屋のくせに六発も撃たないと仕留められないのか、可哀想な腕だな――
ローファル やかましいぞ。
バルク おおっと、目付役を怒らせたら大変だ。――しかし、大公を殺そうってのはこれはまた随分と大仰な話じゃないか。次代の国王にもなり得る貴族を葬り去るんだからな。
クレティアン 戦局を攪拌させるのが猊下の狙いだろうか。大公は武器王の称号を持っている。今のところ大公は両獅子勢力、どちらにも与していないが、甚大な戦力を持っているだけあって、危険視もされているのだろう。リオファネス城が落ちれば、戦局も変わろう。いや、予防線か。
ローファル (無言で歩く)
バルク だけど他にも貴族はいるだろうよ。先に獅子どもを始末した方がいいんじゃねえの。たとえばゴルターナ――
クレティアン 黒獅子公は直に教会の者が始末することになっている。
バルク ラーグ――
クレティアン 白獅子公は、既に教会が片付ける手配を済ませている。
バルク それは大層なこった。今のイヴァリースで一番力を持っているのは、誰だと思う? それは教会だ。その教会に栄光に誰よりも貢献しているのがオレたちだ。つまり、オレたちが一番力を持っているということだ。素晴らしいことじゃないか。
クレティアン 残念ながら、民衆は、新しきゾディアックブレイブの連中こそが教会に威光をもたらすと考えている。私達が表舞台に立つことはないだろう。
バルク それが唯一癪に障るが仕方ねえな。あいつらが聖石を一個見つけてくる間にオレは毒を撒いて一旅団を殲滅出来る。考えてみろ、どっちが効率的な――
ローファル (低い声で)お前達、うるさいぞ! いい加減に黙らないか! 私の陰陽術をここで披露しても良いのだぞ。今の身分を忘れたか? 何のためにヴォルマルフ様と別行動をしていると思っている。我々の存在を誰にも悟らせないためだぞ? 分かっているだろうな?
クレティアン もちろんだとも。暗殺者が目立ってはいけない。「私は都市から都市を渡り歩く遍歴の学者。リオファネスの城下町にいる学僧を訪ねに旅をしている」
バルク 「オレはリオファネス城にに仕事を探しに行く建築家」だ。ちなみにロマンダの建築技術に詳しい――おっと、これは事実だぜ。
クレティアン 技師という話ではなかったのか。
バルク どっちでも変わらんよ。同じ職人だ。いっそ機工師を名乗るか。そうすれば素のままでいける。
ローファル 黙――
バルク (ローファルに)大丈夫、アンタも立派に修道僧に見える。どこからどう見ても戒律にうるさい、小言を並べ立てるやかましい僧だ。とても神殿騎士には見えない、大丈夫だ。その格好、随分板に付いているな。
ローファル (無視)
クレティアン (小声で)だがしかし、その僧服の下に鋭い剣を隠し持っているとは――
バルク (小声で)誰も気付くまい――
第五幕 地下書庫。地下一階。
オーボンヌ修道院の書庫。高低差のある舞台。背面に書架があり、手前に階段。書架に繋がっている。ラムザとウィーグラフが対峙している。お互い手に剣を携えている。
ウィーグラフ (独白)私には夢があった。とても大きな夢だった――。(振り返り、ラムザに)こんなところで会えるとはな! 久しぶりだな、ラムザ! 我々は既に処女宮のクリスタルを回収している。。もはやこの陰鬱な修道院に何らの用はないが、ここでおまえに会ったからには、ミルウーダの仇を取らねばなるまい。(階上に向かって)イズルード! 後は頼んだぞ!
ラムザ おまえはウィーグラフ! 生きていたのか! 何故そこまでして聖石を欲するんだ。あさましいぞ!
ウィーグラフ ベオルブの御曹司が何をたわけたことを。私はおまえよりずっと物を知っている。世間を知っている。現実を知っている!
ラムザ 僕はもうベオルブの一員でもない――あなたも、世間を知っているというのなら、枢機卿の死も知っているはずだ。あれがただの不幸な死ではなかったことを。聖石は悪魔の石だ。それを知っていてなおも望むとは――あなたもイズルードと同じ様に、何も知らないだけだ――
ウィーグラフ 何だって? 枢機卿がどうしたと? 私が聖石を求めるのは、私がゾディアックブレイブの一員だからだ。おまえに想像出来るか? 私がいかほどの期待と重荷を背負っているか――私たちは何としてでも、聖石を持ち帰らねばならないのだ。ここまで来て聖石を持ち帰らないことは許されない。私は私の義務を果たすまでのこと。
ラムザ 義務! 義務だって! 本心では権力を欲しているくせに、それを体の良い言葉で取り繕っている。偽善だ! あなたは、権力を得るために教会に取り入ったのだ。
ウィーグラフ 私が欲しかったのは権力などではない。だが、権力がなければ理想は実現出来ないという事を知ったからこそ、力を欲したのだ。私は、権力の先にある理想を得ようとしただけのこと。おまえは辛い現実を知りもせず、家名を棄てて逃げ出し、掴めようもない夢を追い求めている。私は辛い現実を知ったからこそ、その悲惨な生活の上に理想の生活を築けるよう、最も堅実な道を選んだのだ。理想は実現しなければ、ただの夢で終わってしまう。だから――
ラムザ 偽善だ、偽善だ! さっきから理想理想と叫んではいるが、具体的に何をしようというんだ。今の支配体制を壊して、そこに新たな支配体制を作るだけのことだろう? その頂点にグレバドス教会があるならば、それは今の王権制度と何ら変わらない! ただ支配者が変わるだけであって、搾取され続ける民の苦しみは全く変わらない! 真の革命家は、旧体制を壊して、そこに新たな価値体系創造する人達だ。彼らはこの世の中に革新の息吹を吹き入れる。あなたの思想や行動は人々の価値観に影響を与え、それは我々貴族の古い慣習にも一石を投じた。だけど――あなたは、もはや革命家でも理想家でもない。ただの教会の犬に成り下がってしまったのだ――
ウィーグラフ 私は――
ラムザ もしあなたが本当に現実を知っているならば――知ろうとしているならば――神の奇跡で民を導こうとは思わないはずだ。本当にそれが出来ると?
ウィーグラフ 出来るさ――民の心は弱い。神の奇跡を願わねば生きていけない程、この世に悲惨で、暗黒に満ちている。私はその暗澹な日々をこの目で見てきた!
ラムザ いくら理想を語ろうとも、教会の犬になり果てたあなたにそれは為し得ない。夢や理想は、誰かの手を借りて実現しても価値が半減してしまう! そうじゃないのか、ウィーグラフ! あなたは、あなたの考えで行動するところに意義があったのだ。ミルウーダやあなたの仲間だった人はたとえその選択しかなかったとしても、今のあなたを残念に思うだろう。
ウィーグラフ 残念に思う? 何も知らないおまえには言われたくないな――ジークデン砦で何もかもを棄てて遁走したおまえには、私の事など分からないだろう――全く! 私の苦労など! 私の仲間が私を哀れむとでも? まさか! 見ろ、奴らは今の私を見て鼻で笑っていることだろう! ――(間)――そうだ、私は、権力を欲したのだ。もはや私はギュスタヴを斬り捨てた過去の私とは決別した。教会の犬と罵られようと、いっこうに構わない。何とでも言え! おまえたちに責められる覚えはない! だが――(呟く)――何故こんなにも惨めなのだ――
ラムザ ――それはあなたが夢を持っているからだ。あなたは誇りを棄てた。それでもあなたは、なおも夢を見続けようとしているからだ――僕はあなたの思想に共感していた。尊敬すら――
ウィーグラフ (剣を抜く)いいや、おまえはありもしない革命家の存在を信じ、その幻想を見ていただけだ! 望みもしない称賛を受け、望みもしない軽蔑を受ける覚えはない! 私は、おまえたちに責められる覚えはない!
ラムザ (剣を構える)
ウィーグラフ (独白)イズルードもいつか私に幻滅し、軽蔑するのだろうか――
(両者、激しく打ち合う。剣戟の音)
第六場 森。
夜明け前。オーボンヌ修道院近郊。地面には枯れ木が散乱している。場面中央に廃墟。中でイズルードとアルマが身を潜めている。
イズルード ウィーグラフを置いてきてしまったのが気がかりだ。だが、今更修道院には引き返せない。
アルマ あの人――
イズルード ウィーグラフを知っているのか。
アルマ あの人たちがお金欲しさにティータを攫って、人質にして殺したのよ。
イズルード そんなはずはない! 彼は高潔な騎士だ! 身代金のために誘拐を犯すなんて、そんな卑劣な行動を許すわけがない! そもそも、彼の妹ミルウーダはラムザに殺されたというじゃないか!
アルマ そんなはずはないわ! ラムザ兄さんはベオルブ家の中で一番正しい人よ! 何も考えなしに誰かを殺すような人じゃないのよ!
イズルード 彼だって!
(二人、沈黙)
アルマ あなた悪いひとね。
イズルード そんなことはないさ。オレたちが目指しているのは、アジョラの唱えた理想郷。誰しもが平等に暮らせる世界だ。家を飛び出したきみの兄貴も同じことを考えているのだろう。どうして教会に刃向かい、我々と対立しようとしているんだ。
アルマ それは兄さんが正義を重んじる人だから。残念でも何でもないけれど、あなたと兄さんは全く違うわ。どうか同じ志を持った人だなんて思わないで。兄さんは、夜中に修道院を襲ったりはしない。
イズルード きみはまだ子供だな。世の中、話せばわかり合える人ばかりじゃないんだ。
アルマ どうやらその通りみたいね。あなたも、私に話すより早く気絶させたしね。(顔を背ける)
イズルード (機嫌を取って)――すまなかった。次は、平穏に話し合える場所で出会いたいね。そうすれば、きみが望む言葉を、好きなだけあげるから――(アルマの手を取る)
アルマ (払いのけて)礼儀を知らない人は嫌いだわ。
イズルード どこにそんな不届き者がいるんだ。そんな男はオレがすぐに始末してくれよう。
アルマ なら私は、どうやって自分が自分を始末するのか楽しみに見ているわ。
イズルード 冗談だって――やれやれ、婦人相手のサーヴィスは気骨が折れるな!
アルマ 頼んでもないご奉仕をしてくださるなんて、世の中には随分とお節介な人がいるものね。それに、私聞いたわよ。あなた、貴族の腐った豚は嫌いだって。
イズルード それは言葉の綾というもの。きみは豚なんかじゃない!
アルマ (怒って)当然よ!
イズルード ただの比喩を――いいや、ややこしくなるからたとえを使って話すのはやめよう。きみは、もっと、ずっときれいなひとだ。
アルマ まあ! あなたは嘘をつく悪いひとね――
イズルード そんなことない――これは嘘ではない――(顔を伏せる)
(二人、沈黙。互いに伏し目がちに視線を交わす)
イズルード ――(間)――どうやら、悪い魔法に掛けられたようだ。
アルマ 私は傷を癒やす魔法しか使えないの。だけど、(赤面しながら)この傷は私にも癒やせそうにないわ――
イズルード オレだって魔法は使えない。
アルマ じゃあこれは魔法じゃないのね――(二人、キスをする)――いけないことだわ! 魔法でもないのに! こんなこと、恥ずかしくてとても出来ないわ!
イズルード ならば、酒に酔えば良いだけのこと。飲み干そうではないか、恋の杯を――
アルマ 飲みたくないわ。
イズルード 飲ませてあげるよ――(二人、キスをする)――(独白)オレはさっきから何を言っているのだ! 何をしているのだ! 早く聖石を持っていかなければ! ウィーグラフから託されたこの聖石を!
アルマ 悪いひとね。こうやって適当に言いくるめて、私を攫ってあの人たちの元へ連れて行くのでしょう。
イズルード そんなことは――
アルマ そして私を殺すのでしょう。
イズルード そんなことはしない!
アルマ いいえ、きっとするわ。あなたが手を下さなくても、きっとあなたの仲間たちがそうするでしょう。ティータが――私の親友がどういう目に遭ったか、私はよく覚えているわ。利用され、利用する価値さえなくなったら家畜のように殺されるだけ! 兄たちは理想のための革命だ、国のための戦争だと言うけれど、いつだってその皺寄せにされるのは私達底辺の人間よ! 私は貴族で、恵まれた家に生まれ、多くのものを持って暮らしてきたけれど、私はちっとも幸せじゃなかった! 私はベオルブの家に生まれて、生まれたその時から修道院に預けられて、祈りと勉強の他に楽しみはなく、外の世界に出る時は、誰か兄たちが見つけてきた人と結婚する時なのよ。私は、私の生まれたこの時代が好きよ――だけど、この世に生まれた時から、その人生を呪わなければいけない人たちもいるのよ。あなたたちはそういう人を踏み台にして、新しい世界を築こうとしているのよ。あなた、地に這って暮らす人々の――修道院から出ることさえ出来ないような人々の――涙に気付いたことがある? (泣く)
イズルード アルマ――(抱きしめる)
アルマ (抱き付く)お願い、私をあの人たちの元へ連れて行かないで、せめて一人でこのまま行かせて。このまま誰かに人質にされ、利用され、何をすることもなくただ殺されるのはたまらなく嫌! 私は誰のものでも無い、私の人生を生きたいの。
イズルード (独白)どうすれば良いんだ。ベオルブの娘を連れてこいとの父の命令だ。オレ一人ではとても判断出来ない。父の命令ということは、即ち教皇猊下の命令でもある。このまま、彼女を行かせたら、命令に盛大に反することになる。宣誓不履行だ。騎士の名折れだ。民衆の期待を裏切る。オレはこのゾディアックブレイブの称号をたった数日で手放すのか? こんな形で――それに、瀕死のウィーグラフから聖石を託されたというのに、その信頼をも裏切るのか? 彼女のために? それとも、彼女をこのまま行かせるべきなのか?
アルマ (抱き付いたまま)お願い――
イズルード (続けて)だが今ここで、このひとを手放したらおそらく、二度と会えない――
アルマ (そのまま)よく考えてみて、あなはきっと真面目で誠実な騎士だわ、イズルード。あなたは今すぐ教会から手を引いて足を洗うべきよ。兄さんは、聖石を見てこういったの。悪魔の石と。兄さんは枢機卿が聖石に魂を吸われたと言っていたわ。だって、ライオネル城の惨状を聞いた? 死体はどれもひどい圧死だったそうよ。枢機卿は病死したんじゃないわ。聖石の呼び出した悪魔に殺されたのよ――恐ろしい力だわ。教会は神殿騎士団に聖石を集めさせているけれど、それは何のためだか考えたことがある? あなたは何も知らされていないだけよ。いずれ真実を知ったら、きっとあなたは兄さんと同じ決断をするわ。きっと! だから早く、手遅れになる前に、その剣を棄てて――!
イズルード (アルマを離して)オレが教会を棄てるだって! (独白)――どうして殉教でなく背教をしなければならないんだ! おぞましい! オレはずっと教会に忠誠を誓って、神殿騎士として誇りを持って生きてきた。その誓いの剣をどうして、いとも容易く棄てられようか。そんなことは絶対にありない!
アルマ どうして黙っているの。あなたはきっと、自分で考えて、自分で選択をしたことがないでしょうね――だからこうして修道院を襲撃して聖石を強奪――その聖石は王女様のものなのよ――したんだわ。兄さんだって、かつてはそうだったの。でも、兄さんは、自分で自分の道を選んだのよ。全てを棄てて逃げ出すという選択を。名前を棄て、騎士の剣も持たず、仲間と道を違い、異端者の烙印を押され、それでも兄さんは自分の正しいと思う道を歩んでいるわ! 教会がイヴァリースを戦乱に陥らせ、裏で手を引いていると知っているのよ。だから、全てを敵にまわしてでも、教皇の陰謀を阻止しようと――
イズルード それは事実ではない! グレバドス教会が、そんなことをするはずがない! するはずがない!
アルマ 兄さんはその目で真実を見てきたのよ! 私は、あなたにそんなことをして欲しくないのよ。あなたはきっと悪いひとじゃないもの――
イズルード (独白)この剣を決して手放すものか! この忠誠を決して破るものか――全てを棄てて敗走することなど出来るものか――
アルマ 夜が明けたら、誰かに見つかるわ。それまでに行かないと。あなたが本当に求めているのは平等の世を築くことでしょう? それとも神の国の名前が欲しいだけ?
イズルード (沈黙)
アルマ あなたが名誉のためだけに生きるのではない、本当の騎士なら――
イズルード (無言で腰の剣に手を掛ける)
アルマ (黙って見詰める)
(イズルード、震えながら剣を地面に置く)
イズルード (静かに)――一緒に行こうか。
アルマ やっぱり一人では行かせてくれないのね。
イズルード 父の元へは連れて行かない。
アルマ じゃあ兄さんの元へ連れて行ってくれるの。急がないと、もう日が昇ってる。もし誰かに見つかったら――
イズルード 兄貴の元へも返さない。(キスして)一緒に逃げようか。そして世界の涯を見にいこうか。そしてその先にある永遠の夜の国へ。まぶしい光でなく、穏やかな暗闇が住まう憩いの国へ――(再びキス)
アルマ 私を攫おうっていうのね。ああ、あなたはやっぱり悪いひとだったわ――とても――
(アルマ、タウロスとスコーピオをイズルードに手渡す。イズルード、それを丁重に受けとる。突如、暗転。襲撃の物音)