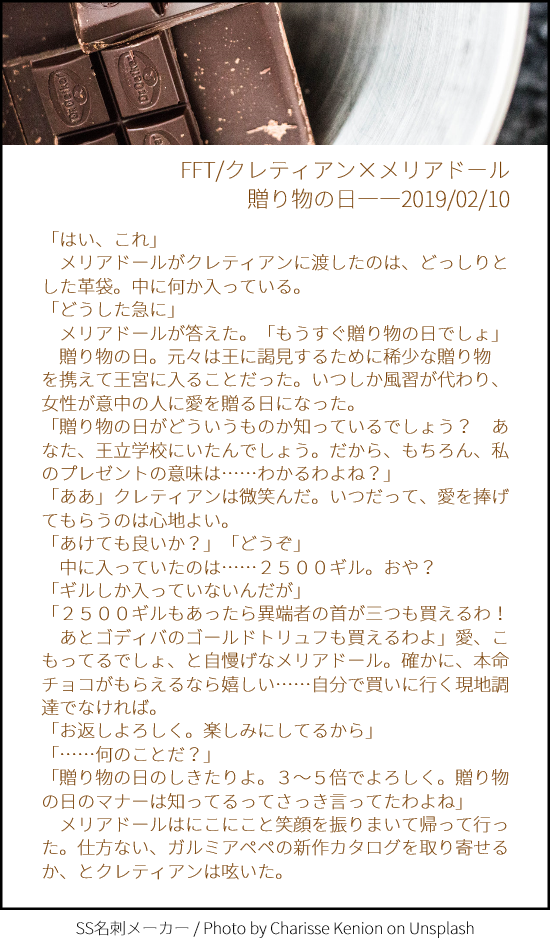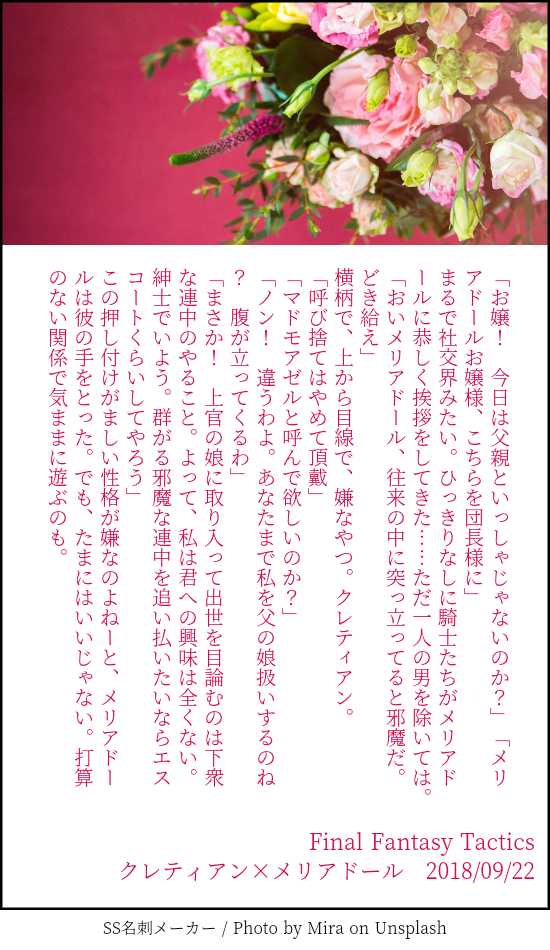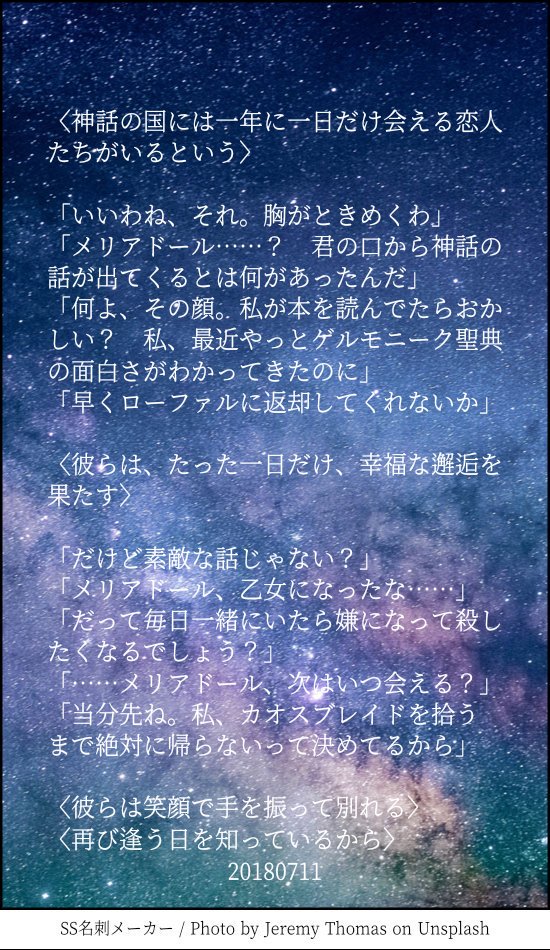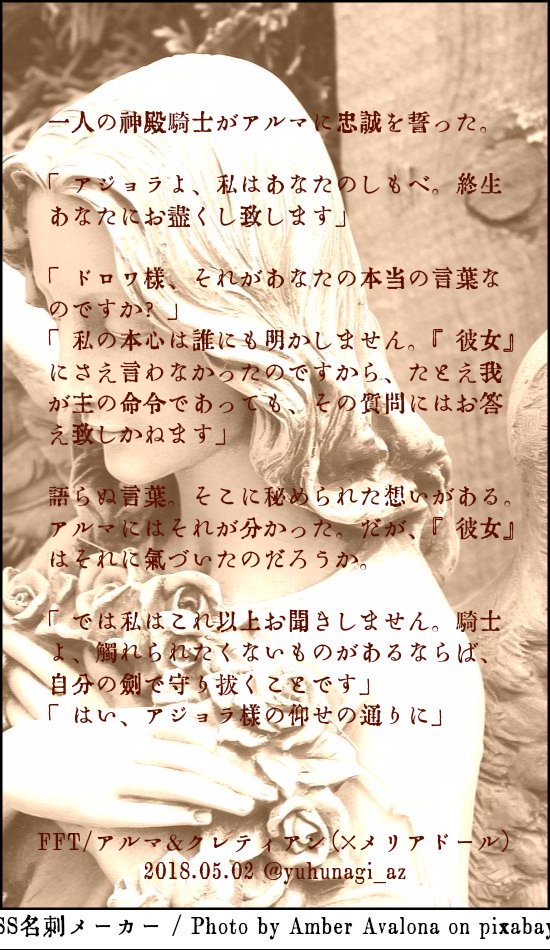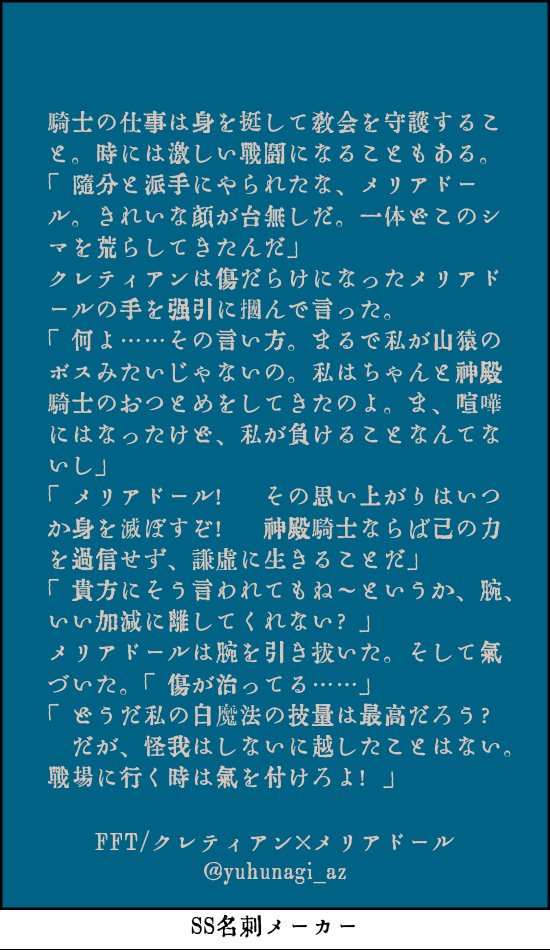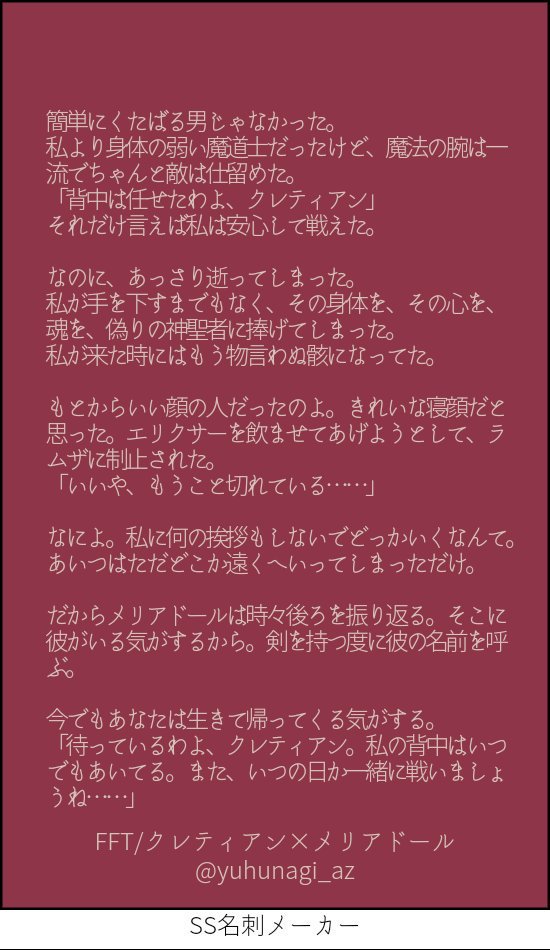.
・クレティアン誕生日記念SS
・メリアドール→クレティアンへ誕生日の贈り物。本人不在でメリアドールとラムザの会話文です。
To C. From M. with LOVE.
「よし、今日はこのあたりで野宿にしよう。日が落ちたら盗賊たちの動きが活発になる。夜に行軍するのは危険だ」
森の中を行進中の一隊に向けてラムザは指示を出した。ちょうど日が暮れ始めた頃、彼らは運よく、森の中の開けた場所に到達できたのだ。隊の仲間たちはリーダーのラムザの指示に従って休息のためのテントを組み立て、火をおこしている。
「この進み具合だと、明日には近くの街に入れるはずだ。そうすれば、まともな食事にありつけると思うけど、今日は残念ながら……」
ラムザは隊のチョコボに運ばせていた携帯用の食料を見た。しばらく森の中の行軍が続いたせいか、食料の備蓄が底をつきそうだった。今日は節約しないとまずいな、とラムザは呟いた。
「ラムザ、だったら、これを」
どうしようかと思案していたラムザに声をかけたのはメリアドールだった。肩にクアールをかついでいる。
「ここに来る途中で仕留めたの。さばいて焼けば今日の食事の足しになると思う。他にも狩れそうなモンスターが近くにいないかちょっと見てくるわ」
「ありがとうございます」
これ、借りていくわね、私の剣は大きすぎて狩りに使うのには向かないから、と言ってメリアドールは自分の剣をラムザに預けた。ラムザは彼女の剣の重さに少し驚いた。
――メリアドールさん、こんな重い剣を使ってたんだ。すごいな。
最近、ラムザの隊に入ったメリアドールのことは、ラムザもまだよく知らなかった。信仰に篤い修道女のような外見で、重い大剣を軽々と振り回して相手の鎧を叩き壊す。見た目からは想像もできない膂力だ。どうも、つかみどころのない不思議な人だった。
「メリアドールさん、このお礼は――」
「別にいいわよ、これくらい――あ、そうね、だったら街に着いたら買い物につきあってくれる?」
いいですよ、とラムザが答える前にメリアドールは槍を背負って狩場に向かってさっさと出かけていた。
「メリアドールさんの買い物か……なんだろう、僕は荷物持ちかな?」
「え、贈り物?」
「そう。もうすぐ昔の知り合いの誕生日なの。ミュロンドで一緒に暮らしていた頃はわざわざ誕生日の贈り物なんてあげなかったけど……黙って騎士団を出てきちゃったし、消息便り代わりに何か贈ってあげようかなと思って。それなりに親しくしてもらってたから」
街に買い物に行きたいと言ったメリアドールの目的を聞いて、ラムザは意外な気持ちだった。メリアドールの昔の知り合い……神殿騎士団の仲間だろうか。
「でも、贈り物選びなら、ムスタディオの方が詳しいと思いますよ。この前もアグリアスさんにこっそりプレゼントを贈っていたみたいで」
「そう? でも、『彼』、あなたと同じ貴族の身分で、ガリランドの士官学校の出身なの。似たような経歴だと思うから、好みのセンスも似てるんじゃないかなって思ったの」
「アカデミーの? じゃあ、僕も知っている人?」
「多分知らないと思うわ。『彼』は私よりも年上だから」
メリアドールが誕生日の贈り物をしたいという「彼」とは一体、誰のことだろう。名前を聞いても分からないだろうが、興味本位でメリアドールに聞いてみたいとラムザは思った。でも、出会って間もない彼女の交友関係を尋ねるのは、少し、気が引けた。だからラムザは黙って彼女の話を聞いていた。
「ラムザ、付き合ってくれてありがとう。私、ミュロンドから出たことがなくて外の風習のことはよく知らないの。買い物なんてしたこともないし、貴族の人が何をもらって嬉しいのかも全然分からないのよ」
「うーん、でも、僕は貴族といっても、家は騎士の男ばかりだったし、候補生だった頃もそういう華のある生活とは縁遠かったなぁ。アルマは兄さんたちから装飾品を色々ともらっていたけど、僕は戦場で役に立つ装飾品とか、そういう実用品しかもらわなかったよ」
「そういうのでいいわ。『彼』も騎士だし、あまり信仰に生きる人だから派手なのは好きじゃないと思うの」
「なら、街の武器屋を紹介するよ」
「坊ちゃん、今日は何をお探しで?」
異端者。街では何かと目をつけられる存在だ。でも、この武器屋の主人はラムザが候補生だった頃から世話になっているためか、ラムザが教会に追われるようになった今でも、変わらず武器や道具を都合してくれる。
「マスター、今日は僕じゃなくて、彼女が買い物を……」
武器屋の主人は、ラムザに続いて店に入ってきたメリアドールを見て、驚きの表情を見せた。
「ゾディアックブレイブ様! 坊ちゃんと教会の騎士様が一緒に来店するとは、珍しいことで」
メリアドールは注目されることに慣れているのか、武器屋の主人に仰天されても、何一つ動じずに棚に無造作に置かれた商品を眺めている。その中から一つのものを手に取った――金細工の髪飾り。
「それにするんですか?」
「そうね……『彼』はアッシュブラウンの髪にお揃いのヘーゼルの瞳で、こういう金の飾りはきっと似合うわ。陽にあたるとね、明るい髪だったの。それに、これは魔道士にも役に立つ加護があるみたいね」
「へえ、メリアドールさんの『彼』さんは魔法を使う方だったんですか?」
「そう、魔法の才能だけは随一だったわ。ふふ、結構な努力家だったのよ、『彼』」
メリアドールはそっと笑った。ラムザの知らない彼女と仲間たちの思い出。
「メリアドールさん、楽しそうですね。きっと、素敵な方だったんですね」
「そうでもないわよ。顔を合わせる度に喧嘩していたし、裏切られた今となっては本気で殺してやりたいと思ってる。そういう人だったのよ――あら、こっちのナイフもいいかも」
メリアドールが髪飾りの次に手にしたのは、メイジマッシャーと銘がついたナイフだった。
「いいわね、これ。魔道士を殺せるんでしょう。プレゼントにぴったり。ラムザ、どうかしら?」
「えっと……」
メリアドールがあまりにも笑顔でナイフを持っていたので、ラムザは返答に困った。
「ところで騎士様、お手持ちはありますか?」
しばらくプレゼントの物色に夢中になっていたメリアドールに武器屋の主人が声をかけた。
「代金は神殿騎士団のミュロンド支部のヴォルマルフ・ティンジェル宛によろしく」
「騎士様、うちは現金のみです。あいにく、手形は受け付けていないので」
ラムザはメリアドールに言った。
「僕が立て替えますよ」
「そんな気遣いは無用よ、ラムザ。昔の仲間にあげるものだから、隊の軍資金を使うわけにはいかないわ。それに、私も手持ちがないわけじゃないから」
メリアドールはローブの下に吊るしていた麻袋から、小さな瓶を取り出した。いい香りがする。香水だ。
「店主、これは売ったらいくらになるかしら? もういらないから換金して」
「え、メリアドールさん、それは大事なものじゃないんですか?」
イヴァリースで香水は貴重品だ。
「ミュロンドにいた頃に、ある人から貰ったんだけど、もういらないわ。私はミュロンドに戻るつもりはないから。どこかで捨てようかと思ってたけど、売った方がお金になるわね――店主、この香水と同じくらいの値段のアクセサリーを頂戴」
私は贈り物のセンスはないわ。何を選んでいいか結局わからなかったもの。メリアドールはさらりと言った。
「騎士様、でしたら、こちらの指輪はいかかでしょう。その香水と似たような効果があって、死を防ぐ加護がついております」
主人が持ってきたのは天使の装飾がついた指輪。メリアドールはうなずいた。
「それでいいわ」
「ではお包みいたしましょう。贈答用ですよね? 恋人さんですか?」
「……簡素なものでいいわ。相手は清貧の教会の騎士だから」
メリアドールは武器屋の質問をさらりとかわした。答えるつもりはないらしい。
「香水代でおつりは出るかしら? もしあったら、届けてほしいのだけれど……私は事情があって、直接渡しにいけないので」
「いいですよ、教会の騎士様でしたらそれくらいサービスします。宛名はどちら様で?」
「神殿騎士団の団長か副団長宛に。横に『C』とだけ書いておいて。それで分かるから。二人のところまで届いたら『彼』も気づくはずだから」
「差出人の騎士様のお名前は添えますか?」
「それはまずいわ。名乗りたくないわね……私たち、ちょっと事情があって」
メリアドールは武器屋の主人からペンを借りると、指輪の包み紙の裏に「From M」と走り書きをした――それから、少し悩んでから「with LOVE」と。
「ラムザ、つき合わせて悪かったわね」
「いいえ……でも、一つ聞いてもいいですか? 武器屋で聞かれてたこと――『彼』はメリアドールさんの恋人の方なんですか?」
ふふ、とメリアドールは笑った。
「どちらでも。その答えは、お好きなようにどうぞ。でも安心して、もう私はあなたと一緒に戦うって決めたの。昔の仲間に会うつもりは、微塵もないから」