
004
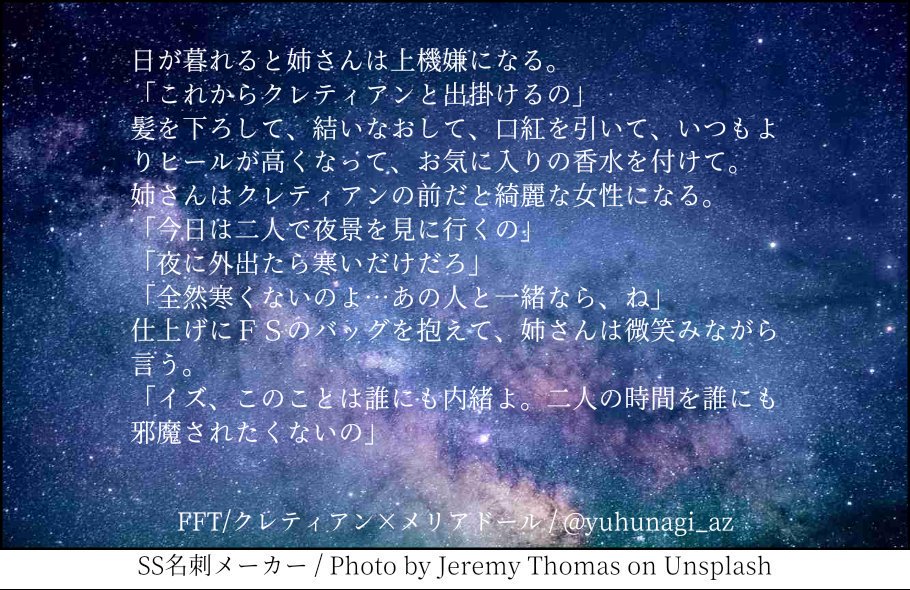
003
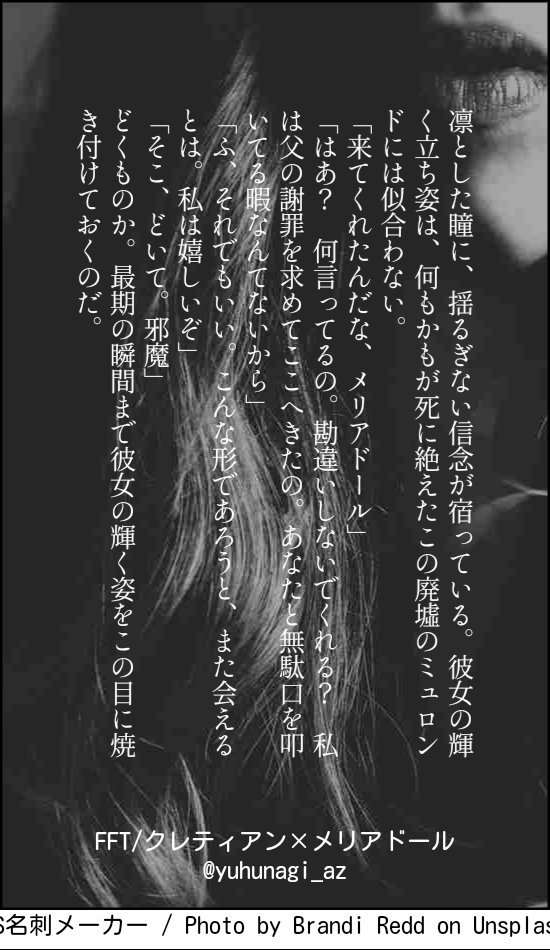
002
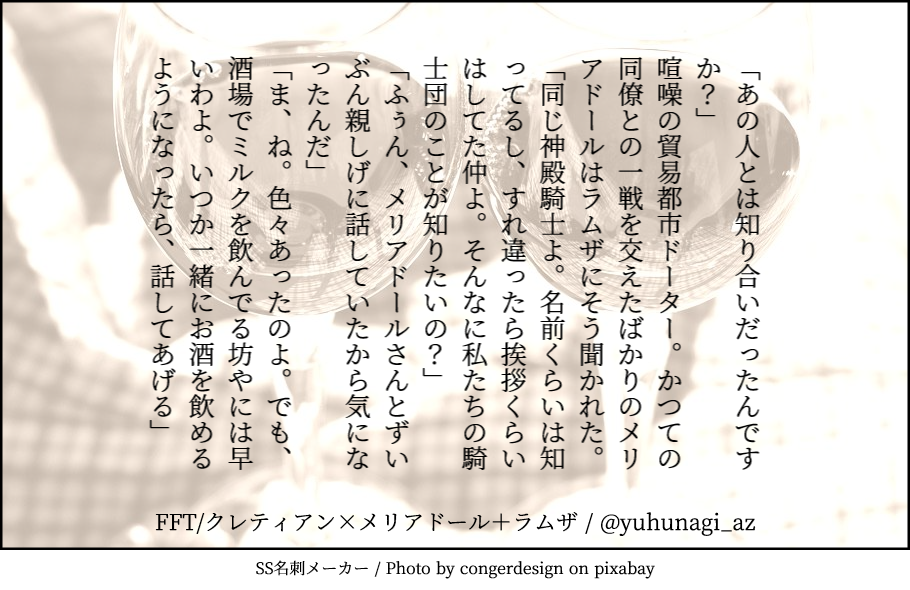
001
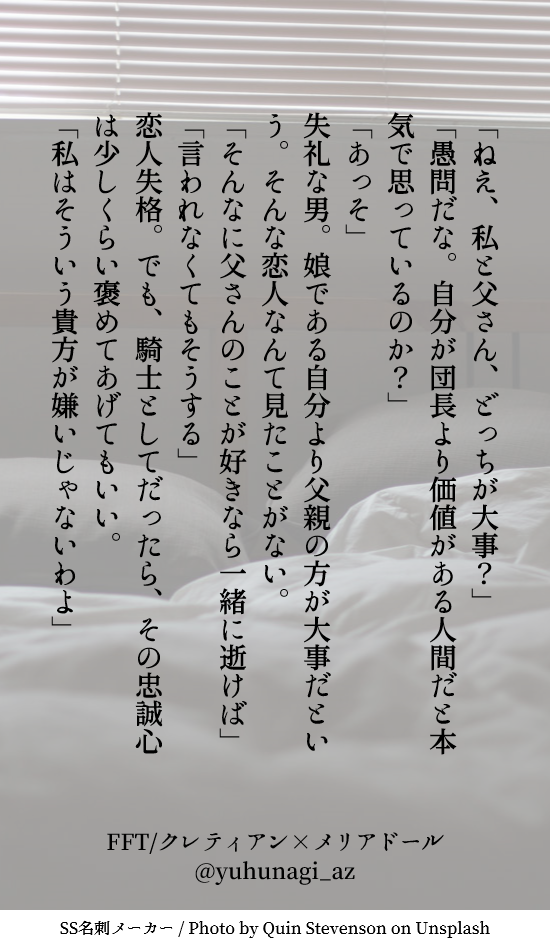
おひざでおひるね
.
・メリアドール(十代前半)、クレティアン(十代後半)、ローファル(永遠の年齢不詳∞)
・イズルードが登場させられなかったのですが、行外で元気に飛び跳ねているということで……
おひざでおひるね
今日はとても暖かい日だわ。
メリアドールは城館の裏口に座って午餐の後の穏やかな時間を満喫していた。伐り出された薪に肩を預けて城館で働く使用人や騎士団の人たちが忙しなく働いている様子をぼんやり眺めていた。こうしていると時々、騎士団の若い男たちがかまってくれることがある。
「お嬢さん、お暇でしたら私が相手をいたしましょうか」
メリアドールは声の主をちらりと見た。騎士団の制服を着た栗毛色の髪の青年。一日の大半を一緒に過ごしているためか、騎士団の人間の名前はたいてい覚えている。
「ええ、とっても暇。イズルードは裏の果樹園に行っていて、今日は誰も私の相手をしてくれないの。でもクレティアン、あなたは仕事中ではなくて?」
クレティアンは両手に本の束を抱えていた。見るからに重そうだった。
「副団長様の命令で書庫でさがし物をしていたんです。ですが急ぎの用事というわけでもないので、少しくらいなら……」
メリアドールが砂埃を払って隣のスペースを作ると、クレティアンはそこに腰をおろした。「一緒に本でも読みましょうか」そう言って持ってきた荷物に手を伸ばした。
まずい。そんなことになったら途中で寝てしまう。
メリアドールはあわてて首を振った。「わ、私はいいわ……あなたが隣で読んでくれるのならそれで結構」
本を読んだり歌を歌ったりするのはメリアドールにとって退屈極まりないことだった。それよりもメリアドールは身体を動かしている方が好きだった。木に登ったり森を駆け回ったりする方が性に合っている。でもこの人はそういう野遊びにはつきあってくれない。彼は騎士団にいる有象無象の山猿たちとは違って、由緒正しき士官学校を卒業してきた貴族の青年だった。
メリアドールはしばらくの間クレティアンの声に聞き入っていた。メリアドールのことを見もせずに隣で黙々と本を読み上げている。この人は、副団長が読むような本を私が楽しめると本当に思っているのだろうか。あたまのいい人の考えることはよく分からない。本の内容もさっぱり分からない。でもきれいな声。低くていい声をしてるわ。ずっとこうして隣に座っていたくなる。魔法を使う人はみんなこんなに穏やかなしゃべり方をするのだろうか……ちょうどいい心地よさにメリアドールはだんだんと眠くなってきた。
「あら、二人してかわいい」
通りすがりの使用人の声にはっとしてメリアドールは顔をあげた。暖かい日差しの中でつい船をこいでしまっていたらしい。
それにしても昼寝に最適なあたたかさだった。そう思って膝の上を見ると、いつの間にか寝落ちしていたらしいクレティアンが小さな寝息を立てている。気がついたらメリアドールが膝枕する形になっていた。どうりでぬくもりが気持ちいいと思ったわ。
「どうやら若騎士さまはお疲れのようだな」メリアドールは背後に人の気配を感じた。そして膝の上の若騎士を起こさないように、そっと聞き返した。
「ローファル? どうしたの?」
「その若いのを回収にきた。仕事の途中だ」
「あら、だめよ、お昼寝の途中で起こしたらかわいそうだわ」
メリアドールはローファルに向かって人差し指を立てた。もう片方の手で寝ているクレティアンの髪をそっと撫でた。穏やかな寝顔を見ていると無理に起こしてしまうのが忍びなかった。
「私、この前うっかり寝ているイズルードを踏んじゃったんだけど、そうしたらすごく機嫌が悪かったの」
「その男はイズルードより五歳以上も年上なのだから、その心配は無用だ。今すぐにたたき起こせ。午睡の時間はとっくに過ぎている」
「そう?」
だがメリアドールが声をかけるまでもなくクレティアンが気配を察したらしく飛び起きた。ローファルの無言の圧力を感じ取ったというべきか。
「クレティアン、さぞや良い目覚めだろうな」
「ウォドリング様――わ、私は決して惰眠をむさぼっていたわけでは……」
「そうか、レディに添い寝するのが騎士の流儀とでも言うのか。貴殿は士官学校で一体何を学んできたのだ?」
「い、いえ……」
クレティアンがその場から身体を引いてたじろいだ。
「そんなにいじめたらかわいそうよ、ローファル。それに私はレディじゃないから何も問題はないわ」
「……お嬢さん」クレティアンは気まずそうな雰囲気だ。「お膝を失礼いたしました。ですが、途中で起こしてくださってもよかったのですよ? 重くて邪魔だったでしょう……」
「別に? ちょっと重たい布団だと思ったくらいよ。それに、あたたかくて気持ちよかったわ」
「そうですか……布団ですか。あなたの布団になれたのなら光栄です――ですが、お父様にはどうかご内密に」
クレティアンはローファルの顔色をちらちらと伺いながらメリアドールに話しかけていたが、最後に一言念を押していくのを忘れなかった。
「で、では私は先に下がらせたいただきますので……」そう言って荷物をまとめるとその場から逃げるようそそくさと城館の中へと戻っていった。
「メリアドール。あなたには騎士団長の息女として身につけるべき礼儀作法がある」
「何?」
「もし今度若い騎士に膝の上を占領されることがあったら即刻蹴り落とすこと」
「そうなの。知らなかったわ。じゃあ次からはそうするわ」
メリアドールは満足げにうなずき、仕事場に戻っていくローファルを見送った。外はそろそろ日差しが傾いて来る頃で、メリアドールも何か手伝いに行こうとすぐに後を追った。
十十
日月 え の日(10/10)の記念SSです。
O daughter, never more bemoan
.
O daughter, never more bemoan
――眠れぬ夜に
『最近、眠るのが怖いの。そのまま起きれそうもない気がして』
部屋の入り口に女性が立っていた。寝間着姿のままで。
「メリアドール。こんな時間にどうしたんだ」
「一人で寝るのが怖くて」
ローファルはやれやれ、と言ってメリアドールを部屋に招き入れた。
メリアドールはこうして時々、ローファルの部屋を訪ねた。誰にも知られずこっそりと――といっても真夜中の逢瀬といった艶めかしいものではない。
これは父親に甘えたがる娘のようなものだ。ローファルはそう思った。実の父親が厳格すぎるせいか、いつしかメリアドールはローファルに甘えてくるようになった。ローファルにとってもメリアドールのことは家族同然に愛していたので、こうした関係を疑問に思うことはなかった。それどころか、年頃の女性になった今でも、昔と変わらずあどけない少女のような感情をローファルに向けてくれるメリアドールのことを愛していた。
「一緒に寝てもいい?」
メリアドールはローファルに聞くと、すかさず彼のベッドに潜り込んだ。彼女はここが最も安全で、心安らぐ場所だと心得ていた。
ローファルは毛布を引き上げ、横になったメリアドールの身体を優しく包んだ。メリアドールはローファルの服の裾を引っ張った。仕方ないな、というそぶりでローファルはメリアドールの隣にすべり込んだ。
「悪夢にうなされるの」
「どんな?」
「弟が……異形の怪物に殺される夢」
「それはただの夢だよ」
“そう、それはただの夢であってほしい”
「でも、弟は死んだわ。それは夢じゃない」
「そうだね、夢ではない」
“そう、それは夢ではない”
ローファルは寒さと底知れぬ恐怖に震えるメリアドールの手を握った。今だけは、このぬくもりが伝わるように――
ノックもせずに誰かが入ってきた。ローファルはすぐに分かった。長年の騎士修行のおかげで、人の気配だけでその動き察することができるようになった。ローファルはメリアドールを起こさないようにそっとベッドから這い出ると、部屋の片隅に置いていた剣を手に取った。そして、いつでも抜けるように身構えた。
「娘を探しにきた」
騎士団長の声だった。
「娘がいないと思って探しにきてみれば……」
ヴォルマルフは途中で言葉を切ると、ちらりと部屋の様子を見た。メリアドールは毛布にくるまってベッドの上で丸くなっている。ヴォルマルフの視線をローファルは感じ取った。
「神殿騎士として、お互い何もやましいことはしていませんよ」
ローファルはきっぱりと答えた。手に剣を持ったままで。
「誰の娘だと思っている――私の娘だ。勝手に連れ出さないでもらおうか」
「<誰の>娘ですと?」
「私が父親だ。そこをどけ」
「父親は死んだ。あなたは父親ではない」
ローファルは迷わず剣をヴォルマルフに向けた。
「息子に剣を向けられ、娘に逃げられ……おまえも私を拒むのか」
「これが、イズルードを殺した報いですよ」
それを聞いてヴォルマルフは鼻で笑った。
「器にならぬ人間を殺して何が悪いのだ? あいつの肉体は――」
ヴォルマルフが言うより先にローファルが剣を振り下ろした。その切っ先はヴォルマルフの顔をかすめて壁をしたたか叩いた。乾いた金属音にメリアドールがかすかに身じろぎした。ローファルはその気配をすかさず感じとった。
「誰であろうと――たとえ騎士団長であろうと、死者の名誉を汚すことは許されない。彼は正しい理想に殉じた――<私たち>には到底、為し得ないような偉業を果たしたのだ」
剣を握る拳に力が入った。
「ふっ……おまえがそう思いたいのならせいぜい勝手に想像しておくんだな。だが忘れるなよ。おまえは私の眷属であることを」
「ですがその前に、私は誓いを立てた騎士なのです」
ヴォルマルフはローファルの手にしていた剣に一瞥をくれるとそのまま部屋を出て行った。
「騎士か……騎士なら戦え。その剣で血を得よ。それがおまえの役目だ」
ローファルは剣を床に投げ捨てると、ベッドの縁に身体をあずけてその場に力なく座り込んだ。そして膝に顔を埋めた。騎士の誓いを立てたのが大昔のことのように思える。どんな文言を唱えたのかすら記憶にあやしい。
とはいえ、目を閉じれば思い浮かぶのは色あせた昔の記憶ではない。つい最近のことだ。色鮮やかな――鮮血の記憶だ。
“彼は死んだのだ”
“いいや、殺されたのだ”
“誰に?”
“父親<だった>男に殺されたのだ”
若い騎士の姿が思い浮かんだ。栗毛色の髪をしたあどけなさの残る少年だ。彼がどうやって最期を迎えたかは、同じ城に居合わせたブロンドの少女から伝え聞いた。
『彼は勇敢に戦って亡くなりました』
ああ、イズルード。おまえは年は若いが立派な騎士だった。メリアドールがその死を悲しんだように、ローファルもまた悲しんでいた。人知れず流した涙を誰も知ることはなかったが。
「しかし……さすがに父親に剣を向けるのはしのびなかったか……」
『それでも彼は最期まで手放そうとしませんでした』
彼がどんな気持ちで剣を握っていたのか……想像するだけで胸が潰れそうだった。
『そして、彼は私に彼の聖石を託してくれたのです』
彼は騎士だった。守るべきもののために戦った。その行為は報われるべきだ。たとえそれが、不幸で惨めな『死』で終わったとしても。そこに栄誉を認めることが彼への弔いになる――もはやそれ以外に為す術はないのだから。
“それでは私の剣は何のためにあるのか”
ふわりとした感触が肩を覆った。
「そこで何をしているの?」
メリアドールがベッドの上から不安そうな顔を見せていた。
「寒くて凍えているの? 震えているわ」
メリアドールはさっきまで自分がくるまっていたあたたかい毛布をローファルの背中に羽織らせた。
ローファルはメリアドールの温もりを肌で感じた。
「起こしてすまなかった」
「誰か来たの?」
床に落ちた剣をメリアドールは見つめていた。ローファルは首を振った。「いいや、誰も来ていない」そう言うと、ベッドの上で身を起こしているメリアドールを毛布でくるみなおした。
「心配ないよ、さあ、寝て」
「……だめ、怖くて眠れないの」
「何が怖いんだい」
「……」
メリアドールはうつむいた。
「ほら、おじさんに言ってごらん」
暗がりの中でメリアドールがふふっと笑うのが聞こえた。しかし、声は悲哀の色を含んでいる。
「……もう剣は持ちたくないの。ごめんなさい……私、もう戦えないわ……」
「イズルードのことか」
メリアドールは答える代わりにローファルの服をきゅっと握りしめた。声にならないすすり泣きが聞こえてきた。
ローファルはたまらず、メリアドールを抱きしめた。深く、優しく、そっと。
“この光景を団長が見たら怒るだろうか”
“いや、かまうものか。彼女を守る家族はもはやいないのだから――”
“私が父親だ”
父親が娘に願うことはただ一つ。その身の幸せ。限りない幸福。
「でも、私……弟の仇を討たなきゃって思うの。なのに、どうしてだか、身体が動かないのよ……」
“メリアドール。剣を持ちたくないというのなら持たなくていい”
“君が復讐の血でその手を汚す必要はないんだ”
“父親ならそう思って当然だろう?”
「ローファル、誰が弟を殺したか分かる?」
ローファルはこの質問をおそれていた。なぜなら、答えることによって、メリアドールを血の復讐に巻き込むことになってしまうからだ。まして、父親の身体に宿る悪魔が弟を殺したと、どうやって説明すれば良いのだろうか。
“私は彼女がこの悪夢から解放されることを望んでいる”
“悪夢から解放するすべただ一つ――私が彼女を手放すことだ”
「ローファル? どうしても私は弟の仇を討たなければならないの。お願い、知っているなら教えて」
ローファルは答える代わりに、メリアドールに尋ねた。
「どうして、そこまで復讐にこだわるんだ? 剣を持つのが怖いというのなら、無理に戦いに挑む必要はあるまい……」
「だって、イズルードは私の家族だもの。弟の死が無駄ではなかったと、価値あるものだったと私は証明したいの」
「そうか……しかし私は何も言えない」
「なら、一つだけ教えて。再び剣を持つ勇気をどうやったら思い出せる?」
「自らの道を信じることだ――その剣を持って行くといい」
ローファルはさっきまで自分が持っていた剣――ヴォルマルフに突きつけた――を指し示した。青白く光る刀身を持つ、特別な騎士剣だった。<守護>の銘が刻まれている。そう、騎士の誓いが刻まれているのだった。
“もはや、私には必要のない剣だ”
“彼女が持つに相応しい”
ローファル・ウォドリングはかつて偉大な騎士だった。時は無慈悲に流れようと、かつての騎士の誇りが完全に消えてはいなかった。
“剣よ、同伴かなわぬ騎士に代わって彼女に尽きせぬ守護を与えよ”
メリアドールは夜明けに旅立っていった。
「私の娘はどこへ行ったのだ」
ヴォルマルフはメリアドールが行方をくらましたことにすぐ気づいたようだった。
「行方を知っているのだろう。ローファルよ」
「さあ。彼女は弟の仇を討ちに行くとだけ言っていましたが」
「その言葉の意味を分かっているのだろうな」
「ええ。遅かれ早かれ、彼女は事の真相に気づくでしょう。そうしたら――あなたを殺しに戻ってくる」
ヴォルマルフは馬鹿げた話だ、とだけ言った。
「出来るはずがなかろう。愚かな姉弟だ。共に血の海に沈めてやろう」
「あなたは父親ではない。娘と呼ぶ権利はない」
「ほう……? それがどうした。些細なことではないか」
“そう。これは些細なことだ”
“騎士団長の身体に、父親ならざる異形の者が住み着いているとは誰も気づいていない”
“メリアドールはいずれ弟の仇を討ったとき、父親を殺すことになったと嘆くのだろう”
“だが、その復讐が死んだ父親の魂の無念を晴らすことになるのだ”
それは決して『些細なこと』ではないとローファルは知っていた。
――娘よ、嘆くことなかれ。たとえその手が復讐の血で汚れようとも。
――その両手は無辜の死者らが流した涙によって清められるのだから。
ボスは愛娘を手放さない
.
ボスは愛娘を手放さない
◆1
年頃の娘を持つ父親として、いつか言われるであろう台詞を覚悟してた。“娘さんを私にください”というあれだ。
もちろん、絶対にくれてやる気はない。
「団長、参謀から申し上げたいことが……」
「クレティアンか。なんだ、言いたまえ」
「二十歳の娘の父親はそろそろ子離れする時期かと」
「貴様……次元の狭間に葬られたいのか?」
だいたい、求婚するにしてももっと言い方があるだろう。私はそんな礼儀も知らない男に娘を渡すわけにはいかない。
「私の娘はそのことを知っているのか」
「いえ、でも承知の上かと。それに父親に先に話をしておくのがマナーかと思いまして」
まるで娘と結婚できるのが当然だと思いこんでいるこの求婚者の態度が私は気に入らなかった。私の優秀な部下であるのに、私の許可なくいつの間にか“そういう仲”になっていたらしい。腹立たしい。
「ローファル、例の本を持ってくるのだ」
私は騎士団長として様々な権限を持っている。気に入らない娘の求婚者を消し去るのはたやすいことなのだと、この恐れ知らずな参謀に思い知らせてやろうと思った……が、副団長は私の命令が聞こえなかったのか聞こえて無視しているのか、何食わぬ顔をしてそっぽを向いている。
副団長はどうやら中立を決め込んだようだ。
こいつはどっちの味方だ? 大事な娘の将来がかかっているというのに。
そういう訳で、私は一人でこの問題に話をつける必要があった。
「おまえは私の娘を手に入れられると思っているようだが、それは間違いだ」
「何故です? 私はお嬢様の愛を得るにふさわしい人物だと思っていますが。恥じるべき行為は何一つしていません」
悪びれる風もなく、涼しげな声で私に口答えをする。私に物怖じせず言ってくるのは後にも先にもこいつと副団長くらいだった。「団長が参謀の助言を無視するのはいかがなものですか」とまで言ってくる。これで無能な部下であればすぐにでも娘の手の届かない場所に左遷してやるのだが……。
「そんなに娘に惚れ込んでいるのなら教えてやろう……我が娘は家出中だ」
さすがにこの言葉は居丈高な若き参謀にも多大なショックを与えたようだった。当たり前だ。私も娘の家出で言葉を失ったのだから。
「お、お嬢様は今どこに……?」
「分からない。私が知りたいくらいだ」
さて、どうしてものかと私が考えあぐねていると、副団長がそっと私に助言をしてきた。彼の助言は参謀の戯れ言よりも結構役に立つのだ。
「良い青年ですよ」
「なんだね、ローファル。おまえまであいつの肩を持つのか」
「参謀が傍にいれば誰も手出しできません。最適な虫よけではありませんか」
「そ、そうか……そうなのか?」
「それに、彼は誰よりメリアドールさまに惚れ込んでいますよ。結婚許可を出せば、彼は確実にメリアドールさまをつれて帰ってくるでしょう」
娘が帰ってくる。その言葉に私は心を動かされた。激しく癪に障るが、それならばこの参謀に頼んでもいいかもしれない。だが、娘の相手に選んでも良いかということとは全く別問題だ。
「さあ、クレティアンよ。娘をつれてこい。団長の命令だ。話はそれからだ」
「当然です。お嬢様の身に何かあってからでは遅いのですから。団長の命令があろうとなかろと私は迎えに行きます」
そう言い残してさっさと部屋を出て行った。
「可愛げのない奴め……」
ああ、娘よ、あんな男のどこが良いのだ……。
私は頭を抱えた。これは深刻な問題だ。
◆2
「メリアドール……さっきから僕たち付けられてないか? 人の気配を感じるんだ」
「あら、だってここは貿易都市だもの。たくさん人がいるわ」
「いや、もっと執念深い気配を感じるんだけど……ストーカーみたいな」
「ああ、あの人なら大丈夫よ。無害な人だから放っておけばいいのよ。ただの父の部下だから」
「お嬢様! そこまで気づいているのなら私を無視しないでくださいますか?!」
ああもう、うんざりだわ。せっかく家を出たっていうのに、父の部下が探しにきたなんて私の面目が立たないじゃないの。ああ、ほら、ラムザが怪訝そうな顔をして私を見ている。
「それで、一体何をしにきたの。ドロワさん?」
はやく家に帰ってこいというお小言を父に代わって言われるのだと思った。
「あなたを愛しています。心から愛しています」
私は全く予想していなかった言葉に度肝を抜かれた。
「私はあなたのお父上と話をしてきたのです。なのにお嬢様が家出中では話になりません。ですから、早くお父様と和解してください。そして家に帰ってきてください」
「そ、そういう話は……私が家を出る決断をする前にしてほしかったです……」
タイミングが悪すぎるのよ。
「ええ。そのつもりでしたが、気づいたらお嬢様が相談もなしに家を飛び出してしまっていて……」
当たり前じゃない。家出するのに相談するわけないじゃない。それに――
「――父に言う前に私に先にプロポーズをすべきではありませんこと?」
「では、ここでお嬢様に正式に求婚します。指輪の銘はお嬢様の好みを聞いてから作らせようと思ってましたが……では、『我が唯一の望み』と『我が心は永久に』のどちらが良いですか――」
「ちょ、ちょっと、お待ちなさい! こんな街中でのプロポーズなんて私認めませんからね!」
あまりに恥ずかしさに顔が赤くなるのが分かった。このやりとりを隣で聞いているラムザは何を思っているやら……。
「僕は席をはずしますから、あとは二人でどうぞ」
あ、よかった。紳士だわ。
そうしてドーターの街角を二人で歩いていた。クレティアンは私をちゃんとエスコートしてくれたけれど、時々心配そうに後ろを振り返った
「お嬢様が迷子になっていないか不安で……」
この人は私を何だと思っているんだろう。私はもう二十歳なのに、まるで手の掛かるお嬢様だとでも言わんばかりの態度だった。
「ラムザにどう思われているか心配だわ。私の実家がとんでもないところだって思われてないかしら。ああ、それにきっと、私は世間知らずのお嬢様だって思われてるに違いないわ……」
「お嬢様が世間知らずなのは事実でしょう」
この失礼極まる発言は聞かなかったことにしてあげた。彼は方々を訪ねて周り私のことを探してやっと見つけてくれたのだから、多少はその苦労に報いてあげようと私は思った。それに、年上の騎士に愛を捧げてもらう喜びが分からないわけでもなかった。
「あの方はベオルブ家のご子息様でしょう? あとで挨拶に行かないと――お嬢様が失礼なことを言っていないと良いのですが。まさか出会い頭に喧嘩を売ったりしていないでしょうね」
「で、でも、ちゃんと、和解したわ」
ああ、もう本当に、にくたらしい人ね。……悔しいけど、全くその通りなのよね。
「思いこみで行動してはだめだとあれほど言っているのに……あなたという人は……」
余計なお小言よ。
「あなたは、私に求婚しにきたのではなくって? それとも御託を並べにいらしたわけ?」
「そんな……分かりきったことをわざわざ聞かないでください、お嬢様。それで、私ははるばる求婚しに来て、快い返事の一つももらえずに帰るのですか?」
「同じことばをそのままお返ししますわ。ドロワさん――私が快くない返事をするはずはありませんもの」
◆3
お嬢様はどうやら父親と和解したらしい。そもそもの喧嘩の発端は定かでないが、あの気むずかしいお嬢様をなだめて連れ帰ってくるのは大騒動だった。
「……ヴォルマルフ団長。私の働きには報いてくださらないのですか」
彼女は私がつれてきたのだ。私が迎えにいかなければ、今頃彼女はベオルブの御曹司と一緒に鴎国観光を満喫していたことだろう。それに団長とはまだ話の続きがある。お嬢様の家出騒動の前にしていた話が。
「何のことだね。言いたまえ」
知っているくせに。しらを切るつもりだろうか。
団長はご機嫌だ。なぜなら、大事な箱入り娘が帰ってきたのだから。繰り返すが私が迎えにいったのだ。お嬢様もご機嫌よろしく父親にくっついて「お父様、ごめんね」と言っている。団長も「よしよし、メリア。仕方ないなぁ」などと甘やかしすぎである。副団長もそんな様子をにこやかに見守っている。
そんな穏やかな団らんの中で私にこんな台詞を言わせるのだから、我が団長はさすがとしか言いようがない。この娘にしてこの父親、というものだ。
「……娘さんを私にください。お嬢様の許可はいただいています」
団長は驚いたようにお嬢様を見た。私の言葉はひとまず無視するようだった。
「そうなのか、メリア」
「うん」
「どうしてそういう大事なことを先に父さんに話さないんだ」
「だって、大好きなお父様ならゆるしてくれると思ったから」
「そうか……そんなにこの男のことが好きなのか? 嘘じゃないのか? 本当なのか? 本気なのか?」
「うん。ちゃんとプロポーズしてくれたのよ」
団長は難しい表情をしている。何を考えているのかは想像に難くないが……
「クレティアン」
「はい」
「どうやら娘はおまえのことを認めているようだ――だが私は断る。私が娘を手放すつもりはない」
「まあ、そうですよね……」
「もう、お父様ったら。あ、でもそれって私はお父様とずっと一緒に暮らせるってこと?」
お嬢様は嬉しそうだった。メリアドール、そこは喜ぶところじゃないぞ、私は言いたかった。これでは子離れができていないのか、親離れができていないのか、どっちだか分からなくなってくるじゃないか。
私の内心を悟ってくれたらしく、お嬢様がそっと助け船を出してくれた。
「でも、ドロワさんはお父様のためなら命を捨ててくれるって。立派な騎士だと思わない?」
「うむ、それはそれで心配だな……父親としてはまずは娘に命を捧げてほしいものだが……いや、おまえの献身は分からなくもないが、それは団長として嬉しいのだが、それと娘のことは別なのだよ」
「まあ、もういいですよ……」
ここは私が折れるところなのだろう。結局、私が騎士である限り、団長には頭があがらないのだから。そうしてその団長の娘を愛してしまったのだから。
◆4
「メリアドール、こっちへおいで」
「ローファル?」
父とクレティアンに聞こえないように私を近くに呼び寄せた。
「あとでクレティアンの部屋へ行ってなぐさめておあげ」
「何を?」
「今日のことを。クレティアンはヴォルマルフ様にちゃんとプロポーズしたかったんだよ」
「だって私は彼の求婚にはちゃんと答えたわ」
「それとはまた別のことなんだ。男はプライドが高い生き物だから、好きな人の父親の前ではいい格好をしたいと思うんだよ」
そういうものなのかしら。でも、ローファルはクレティアンとは長いつきあいがある友人だし……彼の言うことなら間違いないのだろう。
「でも、ドロワさんは私より父に忠義を尽くしてくれているんじゃないかと思うの……」
「多分彼も同じことを思っているよ」
「え?」
「お嬢様は一番愛しているのは父上ではないかと胃を痛めていた。有り体に言えばとても嫉妬している」
「だって……お父様のことは愛しているけど……それは家族だもの。当然でしょう? なんで父親に嫉妬するわけ?」
「男というものはそういう生き物なんだ。いつまでたっても娘を手放さない父親と殴り合いの一つや二つはするものだ――相手が騎士団長でなければね」
「ドロワさんがお父様に喧嘩売りにいく姿が見てみたいわ。お願いしたらやってくれるかしら」
「おそらくね。そうやって頼んで彼を困らせておいで」
ローファルはどこか嬉しそうだ。私はどうしてそんな顔をするのかと尋ねた。
「何故かって? 大事なお嬢様をそう簡単には手放したくないんだ。お嬢様への求婚者はこうやって少し困らせてやるくらいがちょうど良いのさ」
ローファルがこの二人(クレメリ)の仲人をしてくれるのは、「大事なお嬢様であるメリアドールの思い人だから」であって、クレティアンには「お嬢様に求愛するなら少しくらい覚悟しとけよ」という気持ちです。ローファルはメリアドールの第二のお父さん(?)です。みんなメリアドールのことが大好きなんです。末永く仲良くしてね!
転がる死体、ついえた野心、高凜の花
.
転がる死体、ついえた野心、高凜の花
メリアドールはミュロンドの大聖堂を訪れた。剣を突き立てられ血を流した死体が転がっている。グレバドスの名の冠する寺院にあってはならない光景である。彼の名前はマリッジ・フューネラル五世。メリアドールを神殿騎士に叙勲した教皇のなれの果てだ。
その無惨な姿にメリアドールは息を飲んだ。
「ひどい……ひどい殺され方だわ」
普段会うこともなかったが、教会の騎士であったメリアドールのとって教皇は無関係な人物ではない。血の海に沈んだその屍に、メリアドールはおそるおそる近づいた。
「メリアドール?」
柱の陰からメリアドールのよく知った声が聞こえた。
「……クレティアン? そこにいるの?」
腕を組んだまま柱に寄りかかってすでに息耐えた死体を見つめている。その冷酷な視線には敬意はみじんも感じられない。
「あなたがやったのね?」
返事をする代わりにクレティアンは死体に刺さった剣をまっすぐ指さした。「あれを見ろ」
「まあ、セイブザクィーンだわ。私の持っている剣と同じだわ……ということは……ああいやだ、あの人が刺したのね……いやだ、おそろしいわ……」
「そうだローファルが」
「で、あなたはそれを見ていたというのね、クレティアン? 自分の手は汚しもしないで、ローファルにやらせたというのね?」
「……ヴォルマルフ様の命だ」
「また! 父のせいにして! 本当に甲斐性のないひとね」
ささいなことをあげつらって、クレティアンに言いがかりをつけようとしているのはメリアドールも分かっている。多少いじめたところで相手が気にする質ではないことをメリアドールは知っている。気が付けば同じ騎士団の中で十何年一緒に暮らしてきた。勝手知ったる仲なのである。
「メリアドール。言いたいことはそれだけか? 余程気が立っているようだな。少しは落ち着いたらどうだ」
「済んでない!」
「教皇を殺したことがそれほど気に障るなら自分で弔いをしてくるがいい」
クレティアンは腕をふってメリアドールにうながした。さあ、あの剣を引き抜いてこい――出来るものなら、と。
その仕草にメリアドールはますます腹が立った。
「何なの? 私はもう騎士団を抜けたのよ。悪事を働く教会には愛想を尽かしたの。もう教会とは縁を切ったわ。私に弔いをさせる前に、自分がファーラムしてあげたら? あなたたちの指導者なんでしょう?」
「教皇の私たちのヴォルマルフ様を捨て駒の如く使い捨てようとしていた。教皇の意は騎士団の意向ではない」
「ふうん……」
思いがけず父の名前に遭遇してメリアドールは黙った。そうだった。この男は、私をそうそうに見切ったくせに、父には心酔している。
「そう、そんなに父のことが好きなの」
メリアドールの小さな呟きはクレティアンに届かなかったようで、彼は淡々と言葉を続けた。
「それに、私は個人的にこの男は好きではなかった。私は――教会の不正を正すために騎士団に入った。グレバドスの教えが、野心ある権力者の食い物にされているのが気に入らなかった。戦争の混乱に乗じて、グレバドス教会は世俗の力を求めすぎてしまった。その指導者だったのだ――この男こそが」
クレティアンは力を込めて拳を握った。過ぎ去った理想を語り続けるクレティアンの横顔を見つめていた。
「――と、私も昔はそういう志があったのだよ。まあ、今となってはそんなことを思っていたかどうかさえあやしいがな……」
「知ってる」
メリアドールはクレティアンから視線をそらした。床を見つめ、下を向いたまま答えた。
「あなたが意外に気高い理想を持っていたのは十年前から知ってたわよ。私が騎士団に入ったとき、あなたはまだ士官学校を出たての、若い貴族みたいな人で、理想を持って生きる人なんだなって思ってた……」
世間知らずの十幾つの娘には、それはそれは、格好良く見えたのよ。と、メリアドールは付け加えておいた。勿論、声には出さずに。
「そんな日々もあったかな……」
「あったわよ。私があんなにも憧れてたんだから、忘れないでおいてほしいわ」
「え、今、何と言った?」
「なんでもありません!」
彼が理想高き高潔な騎士だったのはとうの昔のこと。見初めたのが間違いで、今となってはそこらの腐りきった野心家と大差ないとメリアドールは悟った。彼が革命家だとか言った日にはウィーグラフに詫びに行かなければならない。でも、時々、メリアドールの目には昔の面影が見える。彼女が憧れていた騎士の姿が。
「そう、だから困るのよね……」
メリアドールはクレティアンに少しだけすり寄った。
「メリア?」
「……あなたの考えについてはこれ以上聞かないわ。父のことも。どうせ私が聞いたって理解できないでしょうから」
「聞く気はあるのか?」
「ない」
「だったら話は早い。メリアドールさっさとここを離れるんだ」
有無を言わせぬ物言いだった。クレティアンはメリアドールの身体をそっと押し返した。さっさと行けとでも言うように。
「どういうこと?」
「殺人現場に居座りたいのか? この剣を見ろ。この騎士剣はディバインナイトのものだ。おまえのものでもある」
「それはローファルのものよ。私のじゃない」
「でも私がおまえのものだと言えば、誰もがそう信じる。異端者一味が寺院に押し入り、教皇を殺害したと。あの異端者には前科があるだろう――枢機卿を殺したのは誰だったかな?」
「ひどい人ね。教皇殺害の罪を私たちになすりつけようと言うのね……!」
「私はヴォルマルフ様がそうするかもしれないと忠告しているんだ」
「そうね……リオファネス城でやったことを思えば、父はそうやって私を抹殺するかもしれないわね。でも、その前に私が、教皇を殺したのは神殿騎士団の者だと密告するかも」
「そんなことをすれば――」
「そうね、そんな謀反を起こした神殿騎士団は即刻解散させられるわね。こんな暴挙をしでかした以上、生かして解散させる訳がないわ。残っている教皇派の者がきっとあなたたちをすぐに処刑するわ。吊し首になるわよ」
「さもなければ首を刎ねてさらし台行きだな。落ちぶれた野心家のたどる道だ。よくある光景だ。で、おまえはそれを見て満足するだろう。正義の断罪ができて」
言ってはみたものの、そんな光景を想像しただけで足がすくむ。教皇の無惨な死に様に立ち会っただけで、こんなに心が痛むというのに、家族が、かつて愛した者たちが処刑される場を想像することなど出来るはずがない。やめて! 耐えられない――!
「お願い、クレティアン、はやくここから逃げて――だれか来る前に――」
「逃げる? 私が? メリアドール、おまえは誤解している。私は殺人の罪を被るつもりはない。逃げるのはおまえの方だ」
メリアドールはこの期に及んでしれっと答えるクレティアンをひっぱたきたくなった。
「クレティアン! その自信はどこからくるの? あなたったら憎たらしいほどの自信家ね――そうだったわ、あなたがそういう性格なのすっかり忘れてたわ」
「それはどうも」
「いい? まだ分からないの? こんな悪事が露見しないはずがないわ。異端者が消されるか神殿騎士団が潰されるかどっちかしかないのよ! 私が死ぬかあなたが死ぬか、そのどちらかよ! 道はそれだけよ!」
「メリア――」
まくしたてるメリアドールを牽制しようと手を伸ばした。メリアドールは今度こそ彼の手をひっ叩いた。
「私の話を最後まで聞きなさい! 私は――私はあなたにそんな不名誉な死に方をさせたくないのよ――私の気持ちも分かってよ……!」
「メリア、教皇を殺した事実は事実だ。確かに私がやったに相違あるまい。否定はしない。私はそれを不名誉だとは思わないし、ここで教皇派の手にかかるつもりもない」
「その自負心を捨てなさい! 少しは謙虚になりなさい、クレティアン――! あなたたち、一体どれだけ人に迷惑を掛けてきていると思っているの? その罪を償いなさい!」
堂々巡りの言い争いにメリアドールは憤慨した。
「なるほど、私に罪の購いをさせたいのだな。ならば今すぐこの剣を引き抜いて司祭を探しに行ってこよう。そうして私はひどい罪を犯したと告解をしてこよう――懺悔が終わった時に私は自分の首の皮が繋がっているとは思えないのだが」
「私を怒らせたいの? それともあなたはただの莫迦なの? 私がそんなことを言いたいんじゃないって分かってるくせに……!」
「そうか、ならば君は私にこうして欲しいんだな」
クレティアンはメリアドールの目の前ですっと膝を付いた。その意図が分からずメリアドールは困惑した。
「私はここで慈悲を乞う」
「え……何よ……」
「もし、君が慈悲の心を持っているなら、メリアドール、私をここでひと思いに貫いて欲しい。人の手にかかって死ぬより、死んだ後永遠にその名前を晒されるより、誰ににも知られることなくここで葬って欲しい。戦士の求める慈悲がどういうものかは知っているだろう――?」
「ま、待って――慈悲を乞う相手が違うわ――私じゃない――私はもう教会から離反したのよ」
「この死んだ男に頭を下げて懺悔するつもりはない。神の恩寵は地上の王のものではない」
「だったら神に赦しを――いいから顔をあげてよ――請うべきよ」
「私は……もはや信じるものを失ってしまった。拠り所とするものは何もない。頼れるものは何もないんだ……」
うつむいたまま、そんな寂しげに言われては心が揺らぐ。メリアドールはこの、うなだれて小さくなっている男を心から抱きしめてあげたい衝動に駆られた。かつての同僚。少しだけ年上のこの騎士の背中をメリアドールは憧憬のまなざしで見てきた。それから十何年、心通わせた同胞。それが、こうして落ちぶれた姿になっている。どうしてこうなってしまったのだろう。互いに反目し合った訳ではないのに、どうして私たちはこうして真逆の道にいるのだろう。
「クレティアン……私は……」
だが、メリアドールの胸に温かいものがあふれてくる前に、彼女は現実に気づいた。
「ちょっと! どこまでも都合のいい人ね。あきれて物も言えないわ。自分の好きなように生きて、父がルカヴィになったと私に知らせもしないでひたすら嘘をつき続けておいて、今更私に何を請うというの? 思い上がりも甚だしいわよ、クレティアン! あなたは一度死んでくるべきだわ! 然るべき方法で罪を償いなさい」
「メリア! 私は!」
「……」
もうこんな男には二度と関わらないとメリアドールは意を決した。メリアドールはクレティアンを置いてその場を立ち去った。振り返ってしまったらまた何かの情が湧いてしまいそうだったので、後ろは見ないことにした。
「メリア!」
「……」
聞かない。見ない。立ち止まらない。
「メリアドール!!」
執拗に無視し続けていたら大声で呼び止められた。この人が本気で怒鳴った場面を知らない。こんな怒り方をするのかと、メリアドールは今更思った。そしてさすがに足を止めた。けれど後ろは振り返らない。それは彼女なりのプライドの表れである。
「……何よ」
「真実を知らされなかったと不満げだな。言っておくがな、この男はな、おまえの父親を殺したんだぞ! 聖石を押しつけ、唆し、教会の権力を傘にして契約を結べと迫った! この権力者は――身勝手で低俗な己の野心のためだけに、ヴォルマルフ様の身体を奪い、魂を汚した!」
「父の――父の名前を出さないで!」
「いいか、奴を殺せと言ったのは確かにヴォルマルフ様だ――だが、これは私とローファルの意志でもある」
「こ、こんなところで父の仇を討てなんて私は頼んでいないわ……第一、私は父があんなバケモノだなんて今まで知らなかったもの……」
「そうだ、だからこれはおまえには関係のないことだ。ヴォルマルフ様には尽くしても尽くしきれないほどの恩義をいただいている。私はそれを返したかった。ローファルもそう思っている」
「ヴォルマルフ、ヴォルマルフって、いつだって口を開けば父のことばかり……! そんなに父を愛しているなら、父と心中してくればいいじゃない」
「もちろん、私はヴォルマルフ様と最期まで共にいくつもりだ」
「そればっかり。どうせ、私のことだって、父の娘だから気を引こうとしたんでしょ――ん……ッ――!」
後ろから抱き留められた。突然の出来事にメリアドールは呻き声をあげた。
「ちょっと――離してよ……!」
「そんな意味じゃないって分かってるだろう――私が誰かを利用しないと出世できない器の小さい男に見えるか――?」
これでイエスとうなずかれたら男がすたるというもの。そんなことになる前に、クレティアンはメリアドールの唇を奪った。颯爽と。
「……これでも分からないか?」
「あ――わ、わかったわ……」
「――だから言ったんだ。ここから逃げろと。死体の転がる戦場や野心にまみれた権謀の世界は君には似合わない。出来るものなら、こんな腐りきった世界からは離れて、どこか私の手の届かない場所へ――」
「ご忠告をどうも。だけど私は剣を捨てるつもりはなくってよ」
「ならば忠告ではなく伝言だ。お仲間に伝えておけ。“オーボンヌ修道院で待つ”と」
用件だけ伝えるとクレティアンは去っていった。
「まったく! そのすがすがしさに逆に惚れるわよ。仲間に伝言? 私だって行くわよ――すぐに追いついてみせるんだから」
メリアドールまだ口元に残っている甘い感触を確かめた。まだあたたかい。
「それでもやっぱり、あなたはやっぱり高嶺の花なのね、クレティアン――追いかけても、追いかけても、私には手の届かない人だった。いつも、こうやって私を置いて一人で遠くへ行ってしまうのね――」
もう、仕方ないわね、そう言いながらメリアドールはミュロンド寺院を後にした。
・父親のことなど色々あったけれどタフなメリアドールと開き直って超自信家なクレティアン。私の理想w
・二人とも気の強い性格だといいなぁ…と思います。
遅咲きの薔薇
.
遅咲きの薔薇
僕はアルマと一緒に、久々にゼラモニアから故郷のイヴァリースへと戻った。両親も兄弟もなく、家も土地も持たない僕は帰る場所がなかったため、学生時代、共にアカデミーで学んだ友人の邸宅に身を寄せていた。彼とは青春の一時期を共に分かち合った人で、首席で卒業をしていった碩学の大先輩でもあった。お互い、道を違ってからは消息も知らない。
この邸宅の細君は僕と面識のある人物だった。……彼女はかつて共に旅をした仲間で、もう、あれから随分と時間が経ってしまったけれど、立ち振る舞い、その身のこなしにはかつての面影があった。彼女は今でも優雅で可憐な女騎士だった。いつまとまったのかは知らないけれども、この夫婦の間では、まだ恋人同士のような、新婚のような、甘酸っぱいやりとりが交わされていた。僕たちが広間に入ると、僕を迎えた彼女はさっぱりとした、薄衣の上着を纏っていた。「どうかしら?」一緒に出迎えた彼はアルマの手を取り案内しながらも、細君に視線を送っていた。「美しいよ」そこで二人まるで始めて出会った若い恋人のように連れ添って歩いて行くのだった。彼女は黙って彼の側に座っていたり、あるいはそっと椅子を引いたり、彼のために、誰にも気づかれないような細やかな愛情を示していた。
僕と彼とで、昔語りに花を咲かせている間、彼女はアルマと一緒に外で過ごしていた。緑の草地の上に、二人の婦人のスカートが丸く円を描いて広がっていた。二人とも微笑みながら、僕たちには聞こえない会話を楽しんでいるようだった。全く影のない世界だった。僕たちが歩いてきた道に投げかけられた、暗い翳りは、二人のささやかな笑顔の中には入り込もうとしなかった。
「そういう運命だったのさ。ラムザ、私の話を聞き給え」
「聞いているさ。僕だって随分骨を折ったんだよ」
僕が妹の姿を視線で追っている間、彼は細君の方に顔を向けていた。そのまなざしが、恋慕の情愛か、思慕の歓びなのかは、ついぞ伴侶を持たなかった僕には知り得ぬことだった。
僕はふと、壁に掛けられた小さくも美しい、可憐な少女の肖像画に気づいた。澄んだ明るい油絵で、丈の長い薄緑の上着を羽織り、こざっぱりとまとめた金の髪の上に瀟洒なヴェールを載せている。紅に染まった頬に、少女らしい、かわいげのある愛嬌が乗っていた。その少女が誰なのかは想像に難くなかったが、彼に一応尋ねた。「この少女は?」
「私の妻のものだよ」つまり、と彼は付け加えた。
「私の総長の愛娘で、私に剣を向けた凜々しき騎士で、そのあとで私の妻になってくれた女(ひと)の肖像さ。元々は母親が娘の成長した祝いにと贈ったものだったらしい。母亡き後は両親の形見としてメリアドールが大事に持っていたのが、この家にやってきた」
彼はその肖像をちらりと眺めた。
「どういういきさつで結婚を?」僕の問いに彼は答えず、ついと席を外してしまった。
僕は肖像の前に歩み寄った。僕の前の肖像の少女は今、美しき夫人となり、庭でアルマと幸福なひとときを過ごしているようだった。「大きなイチジクが二つ熟れているわ! アルマ、それを一つ、もいできてちょうだい」
彼女はそのイチジクをもって、広間へとやってきた。
「アルマがこのイチジクを取ってきたのよ。あとでタルトでも作ろうかしら。ラムザも一緒にどう?」
甘酸っぱい芳香が広がった。
「メリアドール、驚いたよ。君が結婚してたなんて」僕は繰り返した。「どういういきさつで結婚を?」
彼女はさっと顔を赤らめた。一瞬の沈黙の後、彼女は語り始めた。
「あの後、そう、ラムザとオーボンヌで別かれてからのこと。私にはもう家族もなく、誰も心を許せる人なんかいないって思ってた。ただ一人で静かに過ごしたくて、修道院を転々としながら日々を送っていたのね。部屋にただ一人で座って、考えて、この暗い壁の中の世界で、もう俗世に還ることなくひっそりと一生を終えようと心から思っていた。でも、ちょうどその時、偶然あの人と再会したのよ。お互い世捨て人みたいになってて、もう関係なんか持つ気はなかった。でも、図書室であの人が本を朗読するのが聞こえてきたの。古い文豪の詩だった。あたりには私たちの他には誰もいなかったわ。私たちが古の恋人と共に船出をするのを、誰も、何もさまたげなかった」
船は軽やかにすべってゆく。寂しい真昼どき、姫は甲板の上に坐っている。夏の風が彼女の金髪にそよいでる。しかし、故国を恋う悲しみから、また、やがて老王の妃となるべき異境にたいする怖れから、彼女の眼からは涙があふれる。騎士は彼女を慰めようとするが、彼女は彼をしりぞける。彼女は彼を憎んでいる。彼が彼女の家族を殺したからだ。大気はむし暑い。そして彼女はのどがかわく。しまいかたの粗忽から、姫の胸を老王に対して燃えさすための恋の媚薬が、はからずも船房に出たままになっている。
『ご覧あそばせ、このようなところに、葡萄酒がございますのを!』
「こうしていにしえの詩人の魔術が始まるのよ。甘美な詩句は口からとどめなく流れだし、密やかな胸の上に情火を燃え上がらせる。私は、若々しい美しい二人が舷に一緒に身を寄せる様を思い描いたわ。彼ら恋人は、自分たち二人の手がひそかに握り合わされるのを見ないように、遙かな水を眺めている。彼ら、お互に酔いしれながら、海のこと、霧のこと、風のこと、波のこと、目に見えることをささやき合う……
「全くその時だったわ。いにしえの文豪の差し出す盃の香りが立ち上って私にもまた魔法をかけてしまったの。私はまだ喪が明けてさえいなかったというのに、私の中に眠っていた青春の炎が燃え上がったわ。全く恋の盃というのは恐ろしいものだわ。私たちは幾杯も飲み交わして。
「本当に、恋の盃というのは……本当に……そうして私はあの人と…」
彼女はそれ以上話を続けることが出来なかった。青春の恥じらい故か、彼女はその場から立ち去った。僕の前にはよく熟れたイチジクが一つ、残った。
細君の退出と入れ替わりに、主人が戻ってきた。「その続きは私が話そう」
「私の知っている限り、妻は、メリアドールは、いつも黒い喪服を纏っていた。彼女の喪が明けることは永久になかったのだ。家族を理不尽な理由で失いったことは彼女を十も老けさせていた。ある時、私は彼女からこの肖像画を見せてもらった。これが家族の唯一の形見だと。しかし、絵の中の可愛らしい面立ちを、喪服を纏った黒い婦人の輪郭に見いだすことは出来なかった。
「何が彼女を変えたのか? 誰が黒の喪服を脱がせたのか? それが恋の盃、不思議の飲み物、あの媚酒だったのか? 恋の盃とは、単なる象徴ではないのか?
「しかし私たちが小さな修道院の片隅で日がな恋の狂乱に耽っていたと考えるのは間違いだ。そう、あの頃の私たちは世捨て人も同然だった。いにしえの詩人の呼び起こしたひとときの魔法は、次第に色あせていった。一日、一日と、日々は静かに平穏に過ぎ去っていった。私も事を荒立てる気はさらさらなかった。ただ誰にも邪魔されず、心静かに過ごす事だけを望んでいた。
「静寂を求めた私のお気に入りの場所がその修道院にはあった。裏庭に小さな薔薇園があったのだ。そこには誰の邪魔も入らなかった。何の関わりにも乱されることなく、私は永遠の古歌に読みふけっていた。私は、彼女が、ときおりそばに坐って聞いているのを知っていたので、声をあげて読んだ。すると、熱心に動いていた彼女の手は覚えず仕事を忘れるのだった。私はあの戦乱の時代のせいで、ろくに一芸をきわめることが出来なかったが、多少は歌うことが出来た。彼女も、歌う心得はあった。
「ある時私は、あの肖像、君の前にあるその肖像を再び眺めた。美しい、若々しい顔にじっと見入っていた。この若い、笑っている眼が見入っている世界は暖かな、たしかに陽の光に満ちあふれている世界に違いないと気づいたのだ。私はたまらなかった、彼女の暮らすべき世界は光輝くものでなければならない! 私は両腕を肖像の方へのばした。彼女はもう一度この姿に戻らなければならない、悔恨と憧れとに引き裂かれながら、そう願った。
「過去を悔いることは山のようにあった。彼女に黒の服を纏わせているのは、私のせいでもあるのだから。しかし、ただ一つ分かっていることがあった。この肖像の愛らしい若々しい姿は、まだ永遠に過去のものとはなってはいないということだ。かつてはこうだった彼女――その彼女は今も生きている。そして自分のすぐ側に、この手の届くところにいる。自分は今の、この瞬間にも、彼女のそばにいられるのだ!
「私はすぐに彼女を探す必要があった。彼女は薔薇園の中にいた。彼女はほほ笑みながら私を見た。しかし、私は時を移さず黙って彼女の手を取り、彼女を連れて歩いた。私たちは並んで歩いた。白い朝の光の中、彼女のほっそりとした手が任せきったように私の手の中におかれた時、私はこらえきれなくなって彼女の前に跪いた。私がふたたび顔を上げたとき、彼女は、もう黒いヴェールを被いてはいなかった。彼女は、自分の手で、喪服を脱ぎ捨てた。……私は、彼女が闇の中に居るとは最初から思っていなかった。朝靄の中、私の側にたたずむ彼女は、あの肖像と何ら変わりはしなかった。光輝く、美しい姿だった。
「こうして私たちは、再び恋の盃から飲んだのだった。もう幾杯も飲み交わす必要はなかった。心からの、深い一滴で十分だった。いや、初めから恋の盃なんて必要なかったのかもしれない。そして、私たちは遅過ぎる青春を、二人で連れ添ってすごすことに決めたのだった」
その晩、僕はアルマと夕飯をとった。テーブルには夫人の作ったイチジクのタルトも並んでいた。次第に夕闇がせまってきて、全てがひっそりとしていた。しかし、外の庭には灯りが点いておりわずかな輝きを見せていた。歴史から退いた僕たち兄妹がこうやって静かな、幸せな食事をしているとは誰が知っていようか。庭の茂みから、夜の中へ低いアルトが歌い出すと、それに寄り添うに可憐なソプラノが唱和した。『おお青春よ、うるわしの薔薇咲く頃よ!』僕たちはそれに耳を傾けながら、幸福なひとときを過ごしていた。
・パロディ元…シュトルム著『みずうみ』(関泰祐訳)、岩波文庫、1992年、117-136p