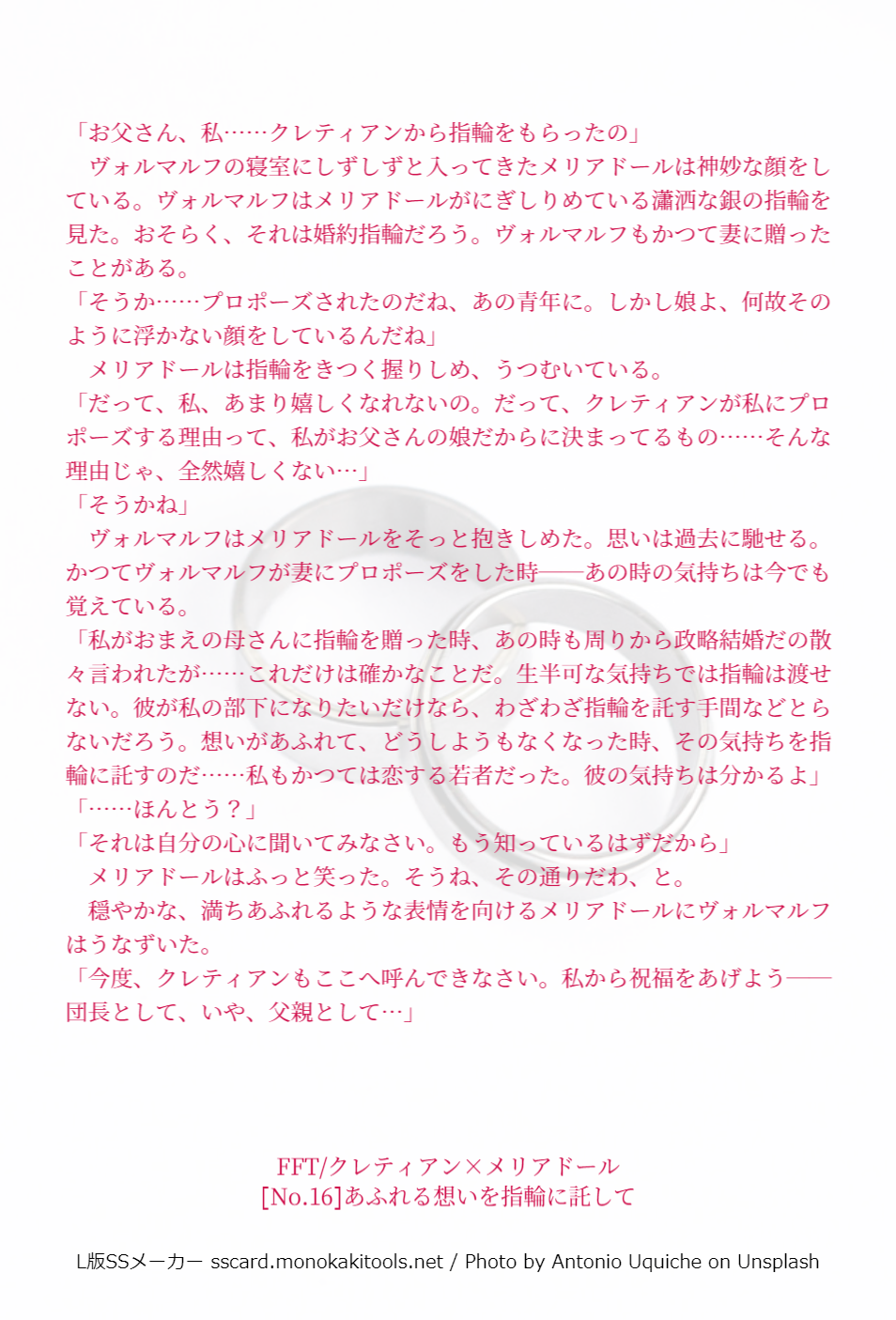.
THE INTERVAL
・お題提供元様→https://shindanmaker.com/524501 (*印除く)
◆ヴォルマルフ「あの時の私でもそうしてたと思う」
「――ヴォルマルフよ、久しいな」
「エリディブズか、戦争の時以来ではないか。どうしてこんな孤独な場所に隠遁しているのだ」
「私は聖石と契約した身。もはや人の世で暮らす義理はない。おまえはそうではないのか?」
「私は……人の世で暮らすことを選んだ」
「何故だ? 聖石の力は厄災でもあることは分かっていての選択か」
「分かっている。だが、それでも私は家族と暮らしたかったのだ。あの時の私はそう思った――今でも後悔はしていない」
(ディープダンジョン再深部。エリディブズ氏があの孤独な場所にいる理由…「聖石を手にしてルカヴィになったものの定めとして人の世に還ることはできない」と蛇使い座は言うのです。それに対して獅子座は一貫して人の世に関わり続け、教会と世俗の権力と戦い続けた。この対比)
◆ローファル「平凡な毎日だけど、これが案外幸せなんだよな」
M:ローファル、貴方には幸せになる権利があるのよ。貴方は私達にとても尽くしてくれたわ。だから、今度は貴方は貴方の幸せのためだけに生きて欲しいの…貴方は…時々とても孤独に見えるから…。
L:私は充分幸せですよ、お嬢様。こうやって過ごす毎日、その中にこそ幸せがあるのですから。
(ローファルとメリア。ローファルの経歴は謎めいているけれど天涯孤独で教会に拾われて、そのままずっと教会に忠義を尽くした人生だったとか。そして騎士団に入ってからは団長に自分の魂と肉体を犠牲にしてまで忠誠を誓う……ストイックな人生。だけど長い長い人生で時には肩の荷を降ろして憩う場所が時には必要である。貴方も誰かのためでなく自分の幸せを願って肩の荷を降ろして、と気遣うメリアお嬢様は、ローファルのそんな人生を隣でずって見てきていたのです)
※LはローファルのLです(Loffrey/北米版)です。
◆バルク「先の事は全然わからないけど、今は幸せだよ」
「未来?夢?そんなものは俺にはなかった。あるのは現実だけ。それも先の見えないどん詰まりの袋小路だ。俺はそんな現実を粉々に砕いてやろうと思った……そしてそれを実行する力があった。搾取され続けた俺にもこんな力があったなんて、幸せなことだろう?」
(失われた聖域の悲痛な叫びから察するにバルクさん相当悲惨な生活を送ってきてると思います。ブラックリストに載るくらいの凄腕テロリストだったそうなので、下っ端戦闘員じゃなくてやり手の幹部だったんじゃないかな。でも神殿騎士団に入ってからは統制者に良い様に使われちゃって…w)
◆ウィーグラフ「案外気付いていないのは自分だけかもね」
「ギュスタヴがゴラグロスと組んで侯爵を誘拐した? ミルウーダ、知っていたのか? 何故止めなてくれなかったんだ……いや、もしかして、お前もあいつらに賛成だというのか?」
「みんな言ってるわ、兄さんのやり方は甘すぎるって」
「私だけか……私だけが知らなかったのか…」
(ゴラグロスは貴族出のギュスタヴと違ってウィーグラフの同郷の出で旧友ポジションを押しています。なのでゴラグロスがギュスタヴにくっついて誘拐事件を企ててるのを知ったウィーグラフの心境「ゴラグロス、お前もか」)(ミルウーダとゴラグロス、仲良いといいなぁ!兄の友達と妹!)
◆クレティアン「あのとき君がああ言ってくれたから、私はここに立っていられる」
私がこの狂気の世界で正気を失わずにいられたのは、一人の正しき人間を知っていたからだった。彼もまた謀略の渦巻く世界でただ一人、義を貫き国王から「ガリオンヌの守護」の称号を賜った――ザルバッグ・ベオルブ。私が尊敬するただ一人の人間だった。
かの若き将軍が信仰と正義を掲げ、正しき道を示したからこそ、私もそれに倣ったのだった。しかし――罪よ赦されよ――私は道を過った。ベオルブ家の道は閉ざされた。将軍よ、若き日の理想は叶わぬものであると、あなたもやがて知るでしょう。
(クレティアンは根が清廉な人なので、やり手の政治家肌のダイスダーグのことは好きになれないけれど、正義を掲げて生きる武人肌のザルバッグのことは尊敬してる……と良いなと思います。クレティアン、ダイスダーグが聖石と契約するのは気にならないけど、ザルバッグが兄の外道極まるやり方を知って落胆する様を見たくなくて、ベオルブ家に聖石を持っていく任務だけはどうしてもこなせなくて結局ローファルが聖石を渡しに行った、という裏エピソードがあったりしたら楽しいwクレティアンも元々(学生時代)はザルバッグみたいな理想高い潔癖の人で、でもそういったドロドロとした現実を知ってしまったから自分に妥協して神殿騎士団に入った、若しくは、政治野心の汚い世界から離れたくて信仰の世界で騎士となることを選んだ、という理由だと良いなと思ってます!)
◆:メリアドール「全然力になれないかもだけど気休めにはなるだろ」
M「誤解していたことは謝ろう。微力ながら貴公に協力したい」
R「本当に微力ですね。剛剣は役に立ちますか」
M「獅子戦争なので問題ない」
R「もう4章の終盤ですが」
M「我が父に会いに行くのだから問題ない」
R「雷神がry」
M「我に合見えし不幸を呪うがよい!星天爆撃打!」
(メリアさん、アグさんと対比して女性らしい口調で話してもらってるけど、もっと武人らしく無骨な感じの方がよいですかね? どうしても香水つけたお洒落なレディのイメージが……アグさんも口紅つけてるけど…!)
◆イズルード「◎◎の前だとうまく言葉が出て来ないよ」
ディリータ。彼はそう名乗った。経歴は言わなかった。初めて会った時、並々ならぬ気迫を感じた。オレと年齢もそう違わないだろう。なのに、圧倒される。オレは言葉を失った。存在だけで圧倒されそうだった。オレは恐る恐る聞いた。「どうしてそんなに頑なに高みを目指す?」
彼は答えた。「愛だよ」 オレは訳が分からないという風に肩をすくめた。彼の口からこんなロマンチックな返答が聞けるとは想像していなかったためだ。彼は再び答えた「愛だよ。愛があるから、俺は孤独に耐えられるんだ」 不可解な会話はそこで終わった。
(イズルードはディリータのことを「友」と呼んでいましたが……イズルードは「持つ者」、ディリータは「持たざる者」。二人が同じ立場の「友」になれたのは、ディリータが過去の自分を隠して「持つ者」として振る舞っていたからでは、と思いました。それはとても孤独だったに違いない)
◆クレティアン×メリアドール「What do you have to lose?」(失うものはないんだからやってみな)*
二人きりになると、彼だけは私のことをミスと呼んだ。私は決まって「私だって騎士なのよ」負けじと応戦したが、「そんな不粋なことを」とたしなめられて終わった。夜の密会に剣は相応しくないと私もうなずき、「お嬢様、お嬢様」と彼が甘やかすのに身を任せた。
そうして、ひそやかに愛を交わした幾度めかの夜に私はとうとう言った。「父のもとを離れます」 別れの挨拶はそれで充分だった。翌朝、私が目を覚ます前に彼は私の枕の下に手紙を残していた。What do you have to lose?[もはや失う物は何もない]と。
信仰、家族、愛――私は全てを失った。だからもう恐れず前に進むことができる。長い甘美な時間の後で、再び私が剣を取る時が来たのだ。「さっさと行け」と彼は言い残したかったのだろう(随分と遠回しなやり方ではあったが)。だったら、私はそれに応えるしかない。「粋にやりましょう」
最後の夜であったのに挨拶もなかった(或いは私と顔を合わせたくなかったのかもしれない)。私は書き置きに別れの言葉を綴った。farewellとだけ。彼ならその意味を分かってくれるだろう。[よき旅をせよ]――各々別の道を歩む時が来たのだ。旅路を祝福せよ。私は私の道を行く。
(Parting is such sweet sorrow.別れは甘く、切ないもの。しばしの感傷に浸ったら、メリアさんは凛として剣を携えてライオン討伐にいって欲しいです。復讐の炎!!とかじゃなくて、騎士として正しい道を示すために……粋にやってほしい)
◆ザルバッグ×クレティアン「……電話越しでも泣いてるのわかるから」 ※手紙で代用
「手紙を書いているのか?」私がそう尋ねると彼は慌てて紙を隠した。「詩を書いていたのです。ほんの暇潰しですよ。ベオルブ先輩もご覧になりますか?」 見ると技巧を凝らした詩連が幾つも書き付けてあった。人目見ただけでも、彼の並外れた才能が伺える。
「私には手紙を書くような人はいませんから」自嘲気味に彼は呟いた。だからこうして退屈しのぎに詩を書いているのだという。若い学生が己の技術を競うために詩を作るのは珍しいことではない。彼には優れた才能があり、それは誰もが認めることである。首席入学。他の誰の追随も許さない。 彼の詩には誇り、自負――そういったものだ。しかし私は詩を書く彼の別の姿も知っている。誰もいない教室でたった一人、ペンを握りしめて、語らう友もなく、詩を書く彼の心境は想像するに難くない。「寂しいだろう」私は呟いた。彼は「いいえ」と呟いた。虚栄心だろうな、と私は思った。
(若かりし頃のクレティアンは騎士時代とは比べ物にならないほどプライドが高くて「あんな烏合の衆とは交わりたくない」とか言ってしまって、孤高の学生時代を送ってたんじゃないかな~ザルバッグはそれを見て「出る杭は打たれるぞ」とやんわり忠告したんだけど、効果はあまりなく。自分は貴族で才能もあって周りが自分にひれ伏すのが当然、くらいでちょうどいいと思います。信仰に篤い人だから、人にひれ伏さず神の前でだけ膝まづく…というタイプですよきっと! 10代の若者はそれで良いよ~)
◆シド&ローファル「もしかして……好きな人、いるん?」
夜中の夜営地。物音がした。私は剣を取り、物音の主を探った。私は異端者と呼ばれる者たちと同行している。私らの首を狙うものは後を絶たない。そこで雷神として名を馳せた私もラムザの身の安全の確保に協力している。私は足を忍ばせ、侵入者を探した――居た。僧帽を目深に被った男だ。 顔は見えない。だが、その格好から神殿騎士とすぐに分かった。「何の用だ」 「私は貴方がたに危害を加えるつもりはありません」 私は鼻で笑った。散々悪事を働いた、どの口が喋っている。彼は続けた。「私はただ……彼女のことが気掛かりで」 メリアドールのことだと私は察した。
「私は、彼女が、異端者と一緒にいることが心配でならないのです。異端者の名前のせいで、彼女に何か危害が加えられるのではないかと……」だからこうして夜な夜な、彼女の側を守っていたのだと彼は告白した。私はこの男のメリアドールに対する心情に、尋常ならざる思慕の念を感じた。
「分かっています。私たち神殿騎士団が何をしたのか。でも、彼女にはその汚名を背負ってほしくない。たとえ我が身が血塗られていようとも、彼女にはそのような汚れた道を歩んで欲しくない」 私は答えた。
「だったら疾くその身を引かれよ。彼女にはラムザがついている。心配は不要だ」
「ええ、私はもう二度と彼女には近づきません……ですから、この剣を。たとえ神殿騎士が汚名を背負っても、彼女の魂は永遠に気高いままです。彼女は私たちが失ったミュロンドの騎士の心を持っています。この剣はその証しです。私は……もうこの剣は持てない。どうか彼女に」
彼は一振りの騎士剣を置いていった。それはディバインナイトに授けられる最高の栄誉の剣であった。私はそれをメリアドールに渡した。そして彼女に尋ねた。この剣の持ち主を知っているかと。彼女は答えた。
「ええ、私のとても尊敬する方でした」
(シドとローファル→メリアドール。ローファルはメリアドールのことをとても慕っていて、メリアドールも彼のことを尊敬してます。ローファルは自分ら神殿騎士団がどうしようもない悪事を働いていると自覚しているけれど、その罪をメリアドールには背負って欲しくないと切に願っています)
◆バルマウフラ「……なんてね。嘘だよ。」
「私、ヴォルマルフを殺そうと思うの」そう言ったら彼は慌てて机の書物をばらばらと取り落とした。「お、おまえ……なんてことを」そのあまりの動転ぶりを見てしまい、私はこう付け足す羽目になった。「なんてね、嘘よ。嘘に決まってるじゃない。私がほんとに騎士団長を殺せると思う?」 彼が慌てるのも無理はない。この人は王都出身のアカデミアン。私の師。母親を殺され、身寄りがない私を引き取っくれた。母は魔女として告発され、私も魔女の娘として教会から名指しされていた。そんな私に一から魔法を教え込み、「魔女」ではなくソーサラーにしてくれた。
彼は騎士団の中でとても影響力のある人だった。そんな人の弟子だった私はもう誰からも「魔女」と言われない。私がこうして暮らしていられるのはこの人のおかげ。だけど、私の母に魔女の宣告を下したのは、ヴォルマルフだった。私が魔法を学び、極めたのも復讐心からだった。
私が、こうして得た魔法を、母の仇敵を倒すために使うと知ったら、この人はどんな顔をするのだろう。だって彼はヴォルマルフの側近。ヴォルマルフの言うことには絶対に逆らわない。もし私が今尚、憎悪の念をヴォルマルフに持っていると彼が知ったら……でも本心はまだ誰にも言わない。
(オチは特になし\(^o^)/バルマウフラとクレティアン。バルマウフラの生い立ちはヴォルマルフやメリアドール、オーランとも関わってくるので教会の中で複雑なことになっているのですが……いずれ書きます。同じソーサラー同士(バルマウフラはソーサレス)仲良くしてて欲しいです。バルマウフラはFFTきっての知性派で、オーランも同じく頭の切れる人でした。クレティアン、ディリータも然り。そういう知性派に囲まれて暮らしていたので、彼女が惹かれる人物も自然とスマートな性格の人になっていったのではないかと思ってます)
◆オーラン「なかったことに出来ないなら、もう一度やりなおせばいい」
オーランは立ち上がった。「私は意義を申し立てる」公会議の出席者は伯爵の突然の発言を非難した。だが伯爵は構わず続ける。「私はこの会議を弾劾する。真実が歪められている。事実をなかったことには出来ない。真実が否認されるというのなら――何度でも繰り返す。私はこの会議を弾劾する」 だが、伯爵の意見は聞き入れられなかった。伯爵は諦めなかった。彼は議論の最中に自著を掲げた。――クレメンス公会議にて、オーラン・デュライは『デュライ白書』を上梓した。その後の経緯は後世の歴史に詳しい。往時の歴史家は伯爵の著作を解さず伯爵の命と共に葬っり去った故である。
(ということで例の公会議でのオーラン。伯爵の地位は継いでるものと思ってます。公会議だから宗教絡みの会議だったのでしょう。きっと、彼は伯爵の地位を持ち、グレバドス教会の中でも地位ある人だったのでしょうね。オーランはこの後、火刑に処されたということですが……私の中でオーランとクレティアンが旧友同士という設定があって、クレティアンは死都で死んでなくて(ルカヴィと契約してて不死の肉体を持っていて肉体の死を迎える為には火で焼くしかないとかそんな前提)、彼は神殿騎士としての行いに恥じるところがあり、罪滅ぼしのため、今まさに火刑に処される友人の身代わりとなり……そしてオーランは妻子とともに大陸へ亡命して……という壮大な妄想がありますw バルマウフラは知ってるけど、メリアドールはこのこと知らない。メリアドールはクレティアンは死都で死んだものと思っていて、バルマウフラだけが彼の改悛を知っているという……全部妄想ですけど、そんなifがあってもいいと思う……オーラン助かるし、クレティアンは罪を告白して善き人として昇天できる…win-winじゃないですかww)
◆ゴラグロス「(……何でこいつ嘘つくの下手なんだろう)」
「王都へ行く」 ウィーグラフはそう言った。村を離れてルザリアへ行って騎士を目指すのだという。大好きな兄と離れなければならないと知ってミルウーダは泣いていた。泣きじゃくる妹に向かって「もうこの村には戻ってこないかもしれないが……」と兄は馬鹿正直に言いかける。
『まったく、こいつは嘘の一つもつけないのか?』 俺は呆れた。「おい、ウィーグラフ!ここは『いつか英雄になって村に戻ってくる』くらい言えっての!ミルちゃんを泣かすんじゃねーよ!」「ゴラグロス、俺は……」 まだ何か
言いかけるウィーグラフの背中を蹴飛ばして送り出した。
ウィーグラフが帰郷したのは村が黒死病で壊滅してからだった。久しぶりに再会したウィーグラフは俺に言った。「俺は王都で騎士になると誓ったのに、騎士にもなれず、英雄にもなれなかった」 落胆して話す友の姿を見て俺は思った。『相変わらず嘘が下手な奴だ』
「おい、ウィーグラフ! 久々に帰ってきてその様はなんだ」 「だが、これは事実だ」 「うるさい奴だ。故郷に帰ってきた。その理由は『家族の顔が見たかった』でいいだろ?」 「しかし父も母も黒死病で死んでしまった…」「ならこう言えばいい。『故郷の友に会いたくなった』」
(ウィーグラフとゴラグロス。仲良いです。もしかしたら幼馴染みとか。ゴラグロスはミルちゃんのことも可愛がってます。で、少年時代のウィーグラフは世渡り下手で、人を疑ったりとか出来ない真っ直ぐな性格でした。その後の艱難辛苦が彼の性格を変えて…でも真っ直ぐな性格はそのままです)
◆ミルウーダ「正直に言ってくれてありがと」
「ミルウーダ……どうしても言わなければならない事があるんだ」 沈痛な顔。「骸騎士団は役目を終えた。本日限りで解散する」 兄はそう言った。「正直に伝えてくれてありがとう……でも、それは兄さんの本当に気持ち? 兄さんは骸騎士団が役目を終えたと本当に思ってるの?」
「それはどういう意味だ?」「まだ私たちの『役目は終わってない』ということよ! 騎士団がこんな不本意な形で解散なんて……何の恩賞も貰えず……使い捨ての駒みたいに……私はこんな侮辱は許さない。兄さん、私たちは立ち上がるのよ! そして――骸騎士団の遺志を継ぐ!」
(骸騎士団。王国の救済という名目を掲げていたはず。騎士団結成当初は、見返りや恩賞など求めていない愛国心ある若者の同盟でしたが、泥沼の戦争の間、貴族に使い捨てにされた団員たちに怒りが募り……いつしか救国の同盟が反貴族の結盟団になっていったのではないかと思っています)
◆ギュスタヴ「何を言おうと言い訳になるだけだから」
「おまえは素行が悪すぎる」 ウィーグラフはギュスタヴを呼び出した。暴言、窃盗、乱暴、乱闘……数え上げればきりがない。こんな奴が副団長の座にいるのだから示しが付かない、とウィーグラフは頭を抱えた。「俺に指図をするなよ、ウィーグラフ」
ギュスタヴは自分が貴種の生まれであることを暗にほのめかしているのだ。だがそんなことにウィーグラフは怯まなかった。「ギュスタヴ、おまえは自分の生まれを行動で汚している」 「俺に説教を垂れる気か? 俺は貴族の権利を行使しているだけだ。何を言ってもどうせおまえには言い訳じみて聞こえるだろうから俺は何も言わない。俺は正しい」 ウィーグラフは溜め息をついた。こんな奴でも北天騎士団から寄越された副団長なのだからお膳立てしなければならない……だがもう限界だ。「ギュスタヴ、次はないと思え」 そう言い捨てた。
(ギュスタヴの立ち位置。本社から出向してきたお偉いさんみたいな立ち位置ですよね。北天騎士団から追放、左遷されたとはいえ、副団長というポスト付で平民騎士団にやってきた貴族。ウィーグラフはさぞ扱いづらかったことでしょう……)
◆ウィーグラフ→イズルード(Ch.3オーボンヌ修道院)「最期の言葉 I」*
彼は去って行く。
戦場と化した修道院で交わした最期の言葉。
私を置いて行け、と。
若き戦士には希望を託さなければならぬ。
私は彼の為に道を作る。
去りゆけ――彼女を連れてここから去ってゆけ――私の悲憤と苦悶の声の届かぬ場所へ。
然らば、彼は知るはずもない。
神に屈した私の最期の言葉を。
――彼は一顧だにしなかった。
◆ラムザ→ウィーグラフ(Ch.3オーボンヌ修道院)「最期の言葉 II」*
修道院に放たれた焔は赤々と炎上し、地を掴み倒れし男の顔を照らす。
妄執の響き、怨讐の叫び声。
その悲哀の響きが彼をその地に繋ぎ止める、しかし彼の憎みし仇の他に誰がその叫びを聞こうか。
満身すべてに言葉を捩り、誰に看取られず狂乱に終わる。
それが聖石を手にした男の矜持か、もしくは呪詛か――それを知る術はもはやなく。
「哀れ、理想に破れし騎士よ」と剣を手に弔うのみ。
公開日:2016.09-2016.10頃